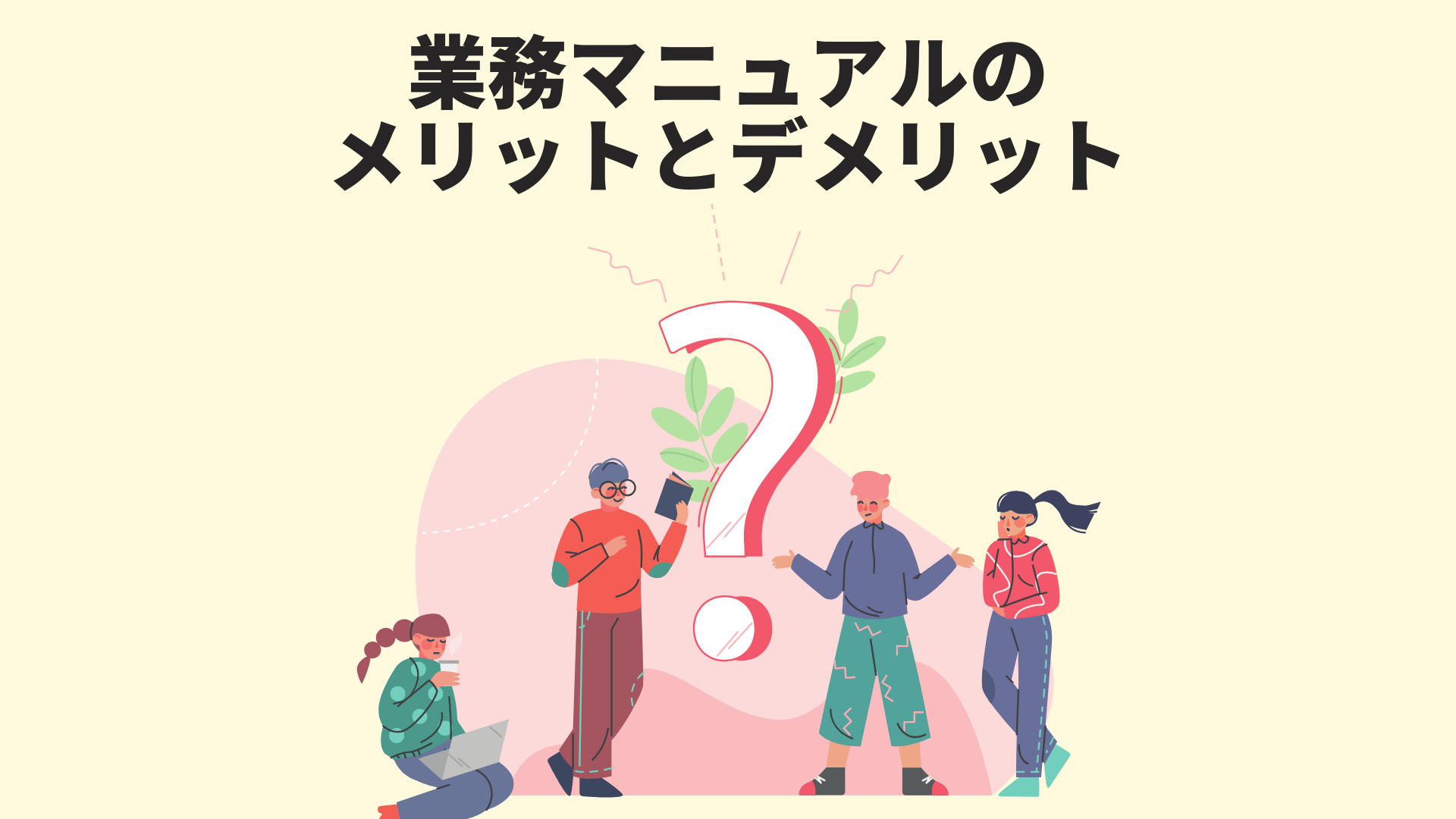

業務マニュアルは、業務の手順や注意点、必要な情報を誰が見てもわかる形でまとめたものです。
主な目的は、業務の属人化を防ぎ、誰でも同じように業務を遂行できる状態をつくることです。
特に、情報システム部門やバックオフィスのように問い合わせが多い職種では、対応の品質とスピードが安定します。
結果として、人材育成の効率化や引き継ぎ時の混乱回避にもつながり、組織全体のパフォーマンスを底上げする基盤となります。
本記事では業務マニュアルを作るメリットとデメリットを紹介します。マニュアルを利用定着させるための施策をお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
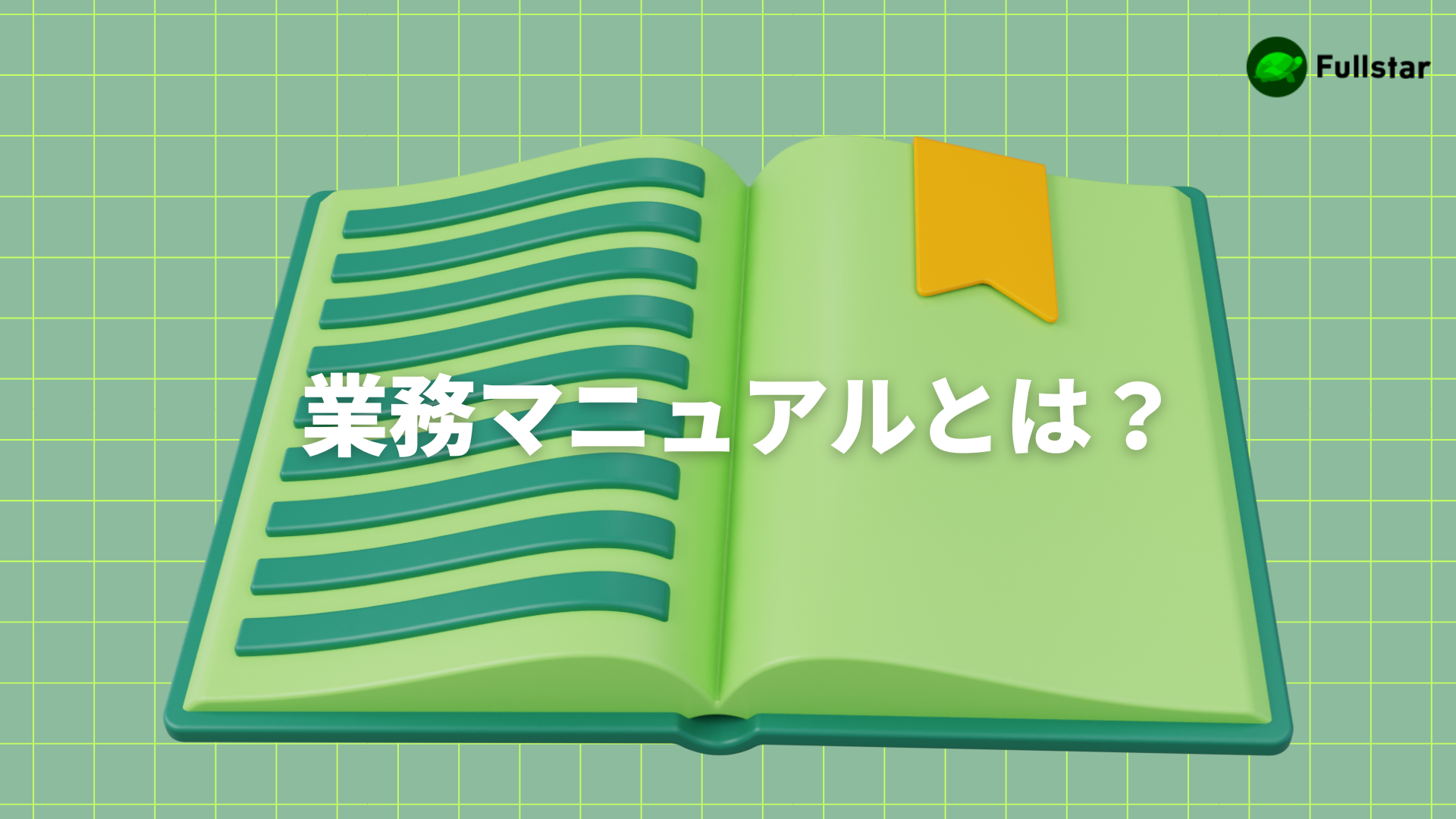
業務マニュアルを作ることで、情報共有しやすくなり、業務を標準化できるようになります。
どんなに優秀な社員がいても、やり方が人によってバラバラでは組織としての一貫性は保てません。マニュアルを活用すれば、対応フローや判断基準を共通でき、誰が対応しても同じクオリティが担保できます。
また、ノウハウも明文化され、社内のナレッジが“個人のスキル”から“全体の資産”へと変わっていきます。これは、チーム運営の安定だけでなく、業務改善やリスク管理にも大きな効果をもたらします。
マニュアル化は、「とりあえず作る」ではうまくいきません。
まずは「なぜ作るのか」「どこに課題があるのか」を明確にすることが重要です。
たとえば、「教育期間を半分に短縮したい」「定型的な問い合わせを月◯件削減したい」など、具体的なKPIを設定しておくと、必要な内容や運用体制が見えやすくなります。
目的と数字をセットで定義することで、マニュアルが“作って終わり”ではなく、“活用され続ける仕組み”を作ることができます。
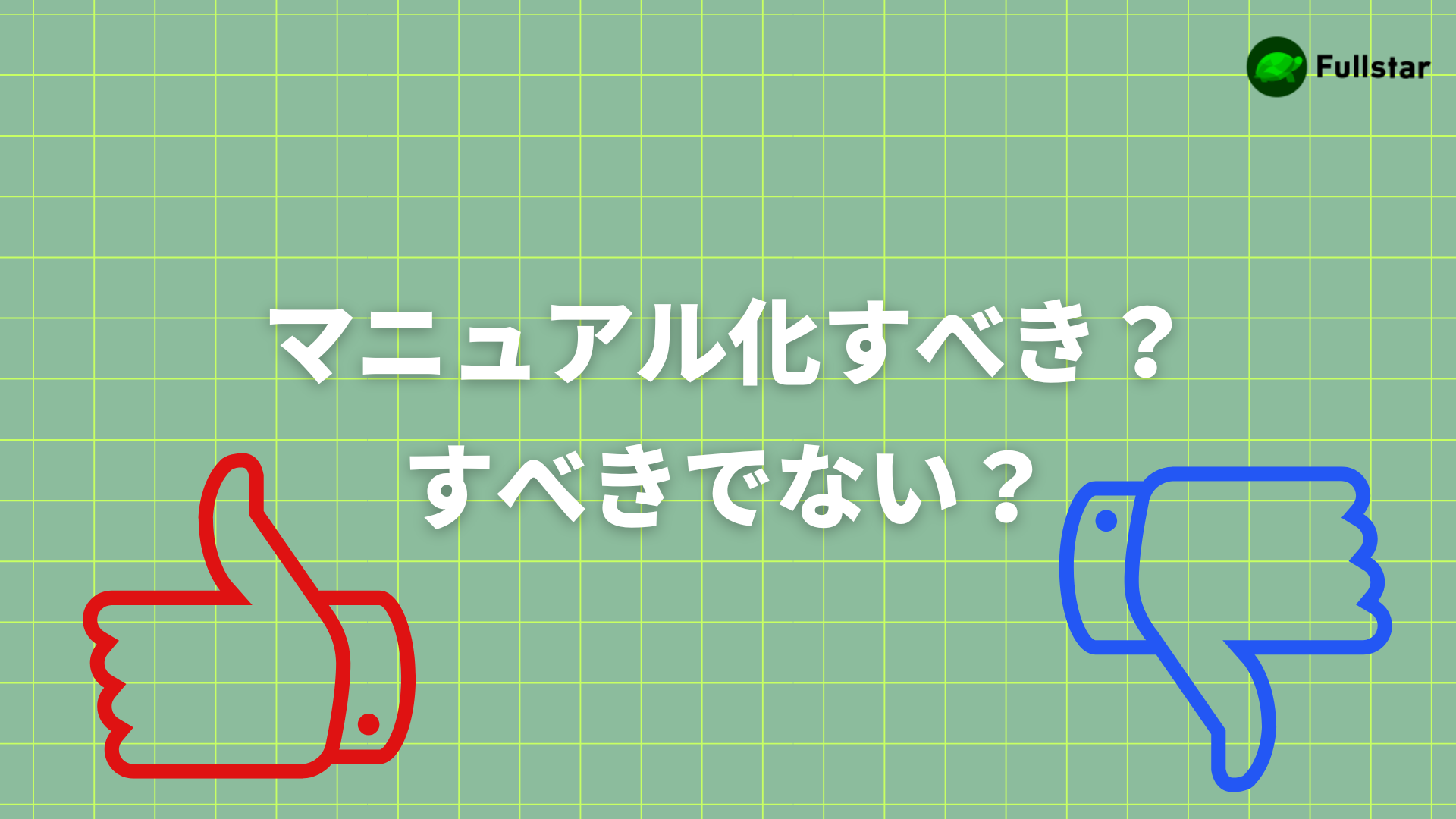
実は、マニュアル化に向いている業務と、そうでない業務は明確に分かれます。
ルールや手順が明確で、繰り返し行われる業務はマニュアル化した方が良いですが、都度判断や対応が求められる業務は、逆にマニュアル化が足かせになることもあります。
ここでは、マニュアル化に「適した業務」と「向かない業務」の特徴を深掘りし、組織全体の生産性を向上させるためのヒントをご紹介します。
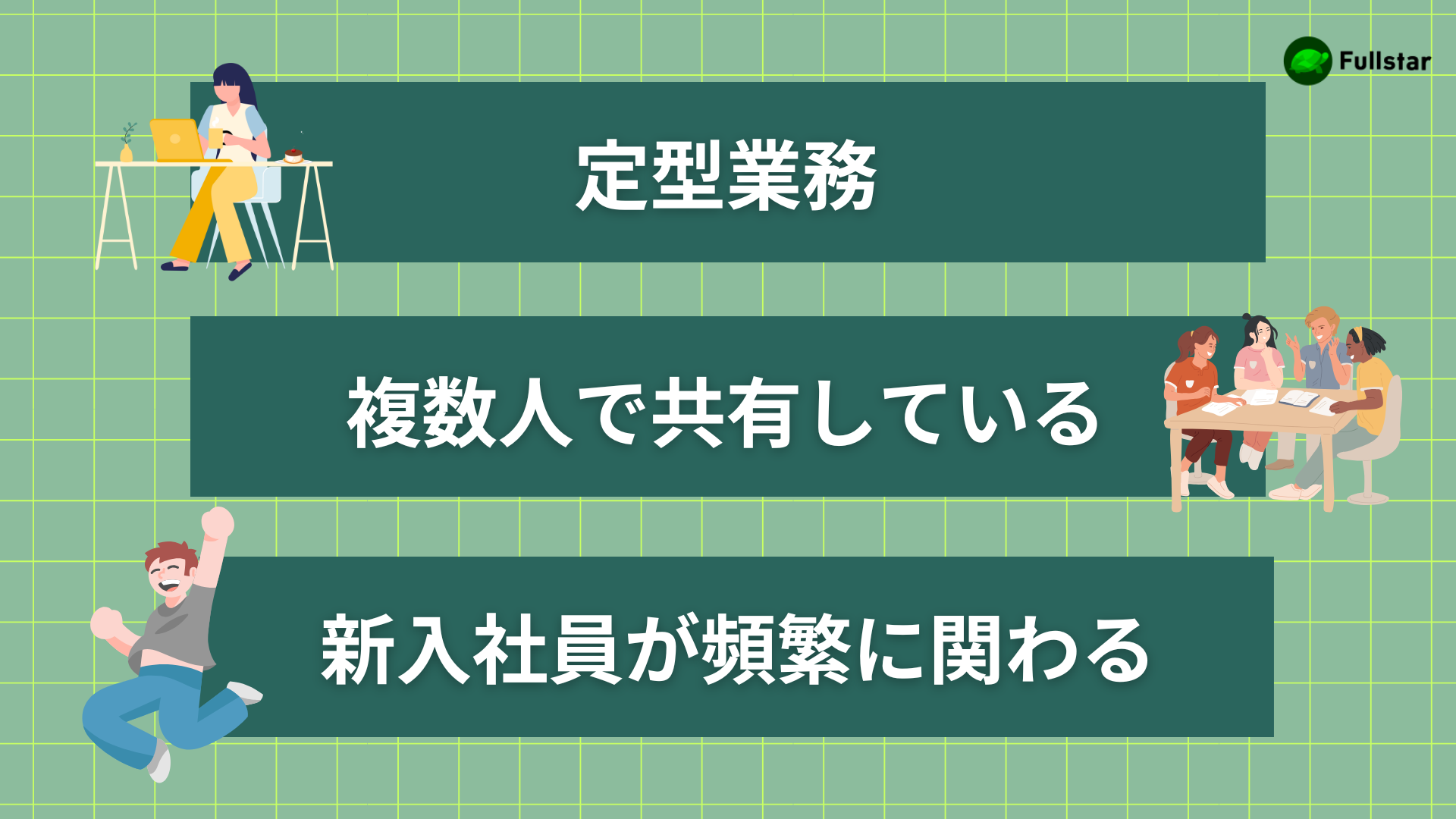
結論から言うと、「判断よりも作業が多い」業務がマニュアル化に最適です。誰がやっても同じ成果を出せる業務は、マニュアルにすることで効率が上がり、ミスも減らせます。
具体的には、以下の3つのタイプが挙げられます。
1. 定型業務(ルーティンワーク)
毎回手順が決まっている作業は、マニュアル化の王道です。
例: PCの初期設定、経費精算、勤怠修正の申請フロー
効果: 作業スピードが上がり、手順の漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
2. 複数人で行う業務・引き継ぎがある業務
担当者しかやり方を知らない「属人化」は、業務が滞る原因になります。マニュアルで手順を共有することで、このリスクを回避できます。
例: チームでの進捗報告ルール、顧客情報の管理方法
効果: 業務が標準化され、担当者の不在時や退職時の引き継ぎがスムーズになります。
3. 新入社員が担当する業務
基本的な業務をマニュアル化しておけば、新しいメンバーもマニュアルを見て、仕事を覚えられます。
例: 社内システムの操作方法、電話応対の基本フロー
効果: 教育担当者の負担を減らし、新入社員の早期戦力化を助けます。
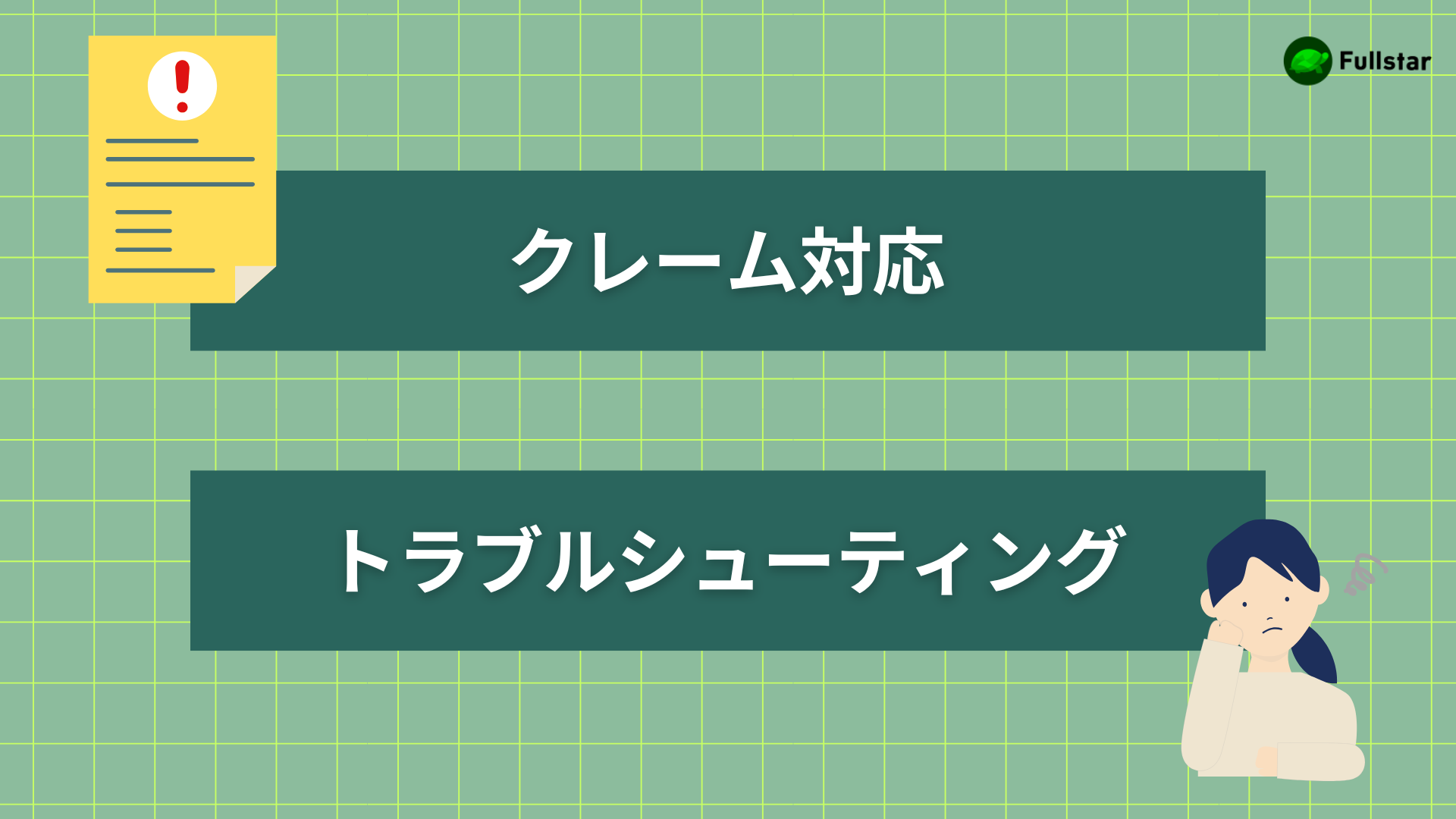
一方で、クレーム対応やトラブルシューティングのように、毎回ケースバイケースで対応が変わる業務は、完全なマニュアル化には不向きです。
手順を固定化すると、かえって柔軟な対応を妨げてしまうからです。
しかし、まったくの丸投げでは対応品質にばらつきが出てしまいます。 そこで有効なのが、「部分的なマニュアル」です。
「判断基準」を示す
「最低限の対応フロー」を定める
マニュアルは万能ではありません。効果的に活用するコツは、「“全部を載せる”のではなく、“迷わないためのガイド”」と捉えることです。
完璧なものを作ろうとせず、まずは骨子だけでも作成し、現場で使いながら改善していく姿勢が大切です。マニュアルは、組織とともに成長させていくツールと考えましょう。
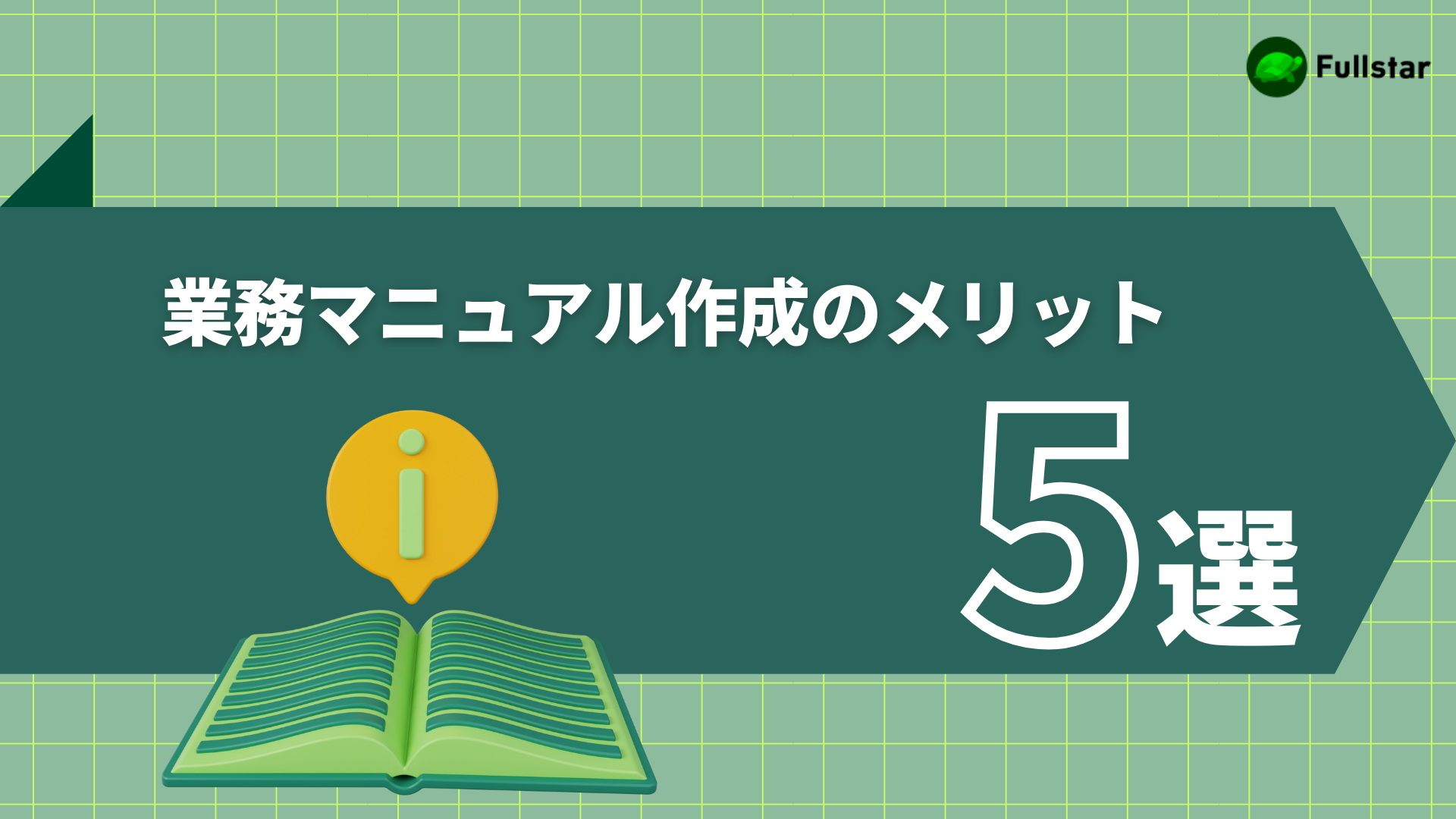
マニュアル化は、個人の経験に依存する「属人化」を解消し、組織全体で共有できる「会社の資産」へと変える効果的な手法です。
特定の社員しかできない業務は、その人がいない時に事業が停滞するリスクになります。マニュアルによって個人の「暗黙知(言葉にしにくいノウハウ)」を誰もが見える「形式知」に変えることで、業務の安定化とノウハウの共有が可能になります。
例えば、多くの中小製造業では、ベテランの熟練技術が若手に伝わらず、技術継承が大きな課題となっています。この課題に対し、写真や動画を取り入れたマニュアルを整備し、OJT(実地研修)と組み合わせることで、若手が視覚的・体系的に技術を学べる環境を整えることができます。これは、ベテランの頭の中にあったノウハウを、組織の共有財産に変えるプロセスです。
このようにマニュアル化は、属人化という経営リスクを解消し、組織全体の技術力を底上げする重要な取り組みです。
マニュアルを整備することは、新人教育にかかる時間と労力を削減し、教育の質を均一化させるために大切です。
教育担当者が毎回同じ内容を説明するのは非効率であり、教える人による質のバラつきも生じがちです。基本的な知識をマニュアルに集約すれば、新人は自分のペースで学習でき、教育担当者はより実践的な指導に集中できます。
多くの企業で、基本的な社内ルールやシステム操作方法を網羅したマニュアル(特に動画マニュアル)が活用されています。新人はまずマニュアルで自習し、不明点だけをまとめて質問する形式を取ることで、研修の時間を大幅に短縮し、教育担当者の負担を軽減できます。結果として、人件費という直接的なコスト削減だけでなく、新人の早期戦力化にも繋がります。
したがってマニュアルの導入は、教育コストを削減するだけでなく、教育の質そのものを高め、人と組織の成長を加速させます。
業務マニュアルは、サービス品質のバラつきをなくし、「誰が担当しても同じ価値を提供する」という顧客からの信頼を築くための土台となります。
担当者によって品質が変わると、顧客は「当たり外れ」を感じ、ブランドへの信頼が揺らぎます。マニュアルで業務手順や判断基準を標準化すれば、従業員のスキルに依存せず、安定した顧客体験を提供できます。
この有名な成功事例がマクドナルドです。ポテトを揚げる秒数から接客まで、あらゆる業務が詳細にマニュアル化されているため、全世界のどの店舗でも、新人クルーでさえ一定の品質を保つことができます。これにより、顧客は安心してブランドを利用できるのです。この考え方は、コールセンターの応対品質の標準化や、チェーン店の店舗運営など、多くの業界で応用されています。
このようにマニュアルは、業務品質のブレをなくす「設計図」であり、安定した顧客満足度を確立するために不可欠です。
参考元)マクドナルドのファストフード経営「ターンキー革命」とは | SUMITAI RECRUITING
業務マニュアルは、異動や退職に伴う引き継ぎの手間と時間を削減し、業務が滞るリスクを最小限に抑えます。
業務内容が文書化されていないと、担当者の不在時に後任者は何から手をつければよいか分からず、業務の停滞や混乱を招きます。マニュアルがあれば、後任者は業務の全体像と手順を迅速に把握でき、スムーズな引き継ぎが可能になります。
無印良品では、「MUJIGRAM」という詳細なマニュアルが全店舗の運営を支えています。このマニュアルには、単なる作業手順だけでなく、「なぜそうするのか」という業務の背景や思想まで記されていることが知られています。このようなマニュアルがあることで、担当者が変わっても業務の本質的な理解が早く、前任者に依存しない円滑な引き継ぎが実現します。
だからこそマニュアルは、組織の「継続性」を担保する生命線であり、人の入れ替わりが多い組織ほどその重要性は高まります。
引用元)MUJIGRAMを完全解説。無印良品の最強のマニュアル運用術
マニュアル作成のプロセスは、普段意識していない業務を「見える化」する機会となり、継続的な業務改善(PDCA)を始めるための起点になります。
「なんとなく」「昔からこうしている」という業務は、見えないが故に改善されません。
マニュアルを作るために業務手順を一つ一つ書き出すことで、初めて「この作業は重複している」「もっと良い方法がある」といった課題が明らかになります。
多くの職場で、マニュアル作成をきっかけに「実は部署内で各々が非効率な手順で作業していた」という事実が発覚するケースは少なくありません。
業務フローが可視化されることで、無駄な作業の廃止やプロセスの標準化に繋がり、結果としてチーム全体の生産性が向上します。一度作成したマニュアルを定期的に見直す文化ができれば、それは業務改善を生み出し続ける「生きたツール」になります。
このようにマニュアルは、単なる手順書に留まらず、業務の無駄を発見し、組織の生産性を向上させるPDCAサイクルの強力なエンジンとなります。
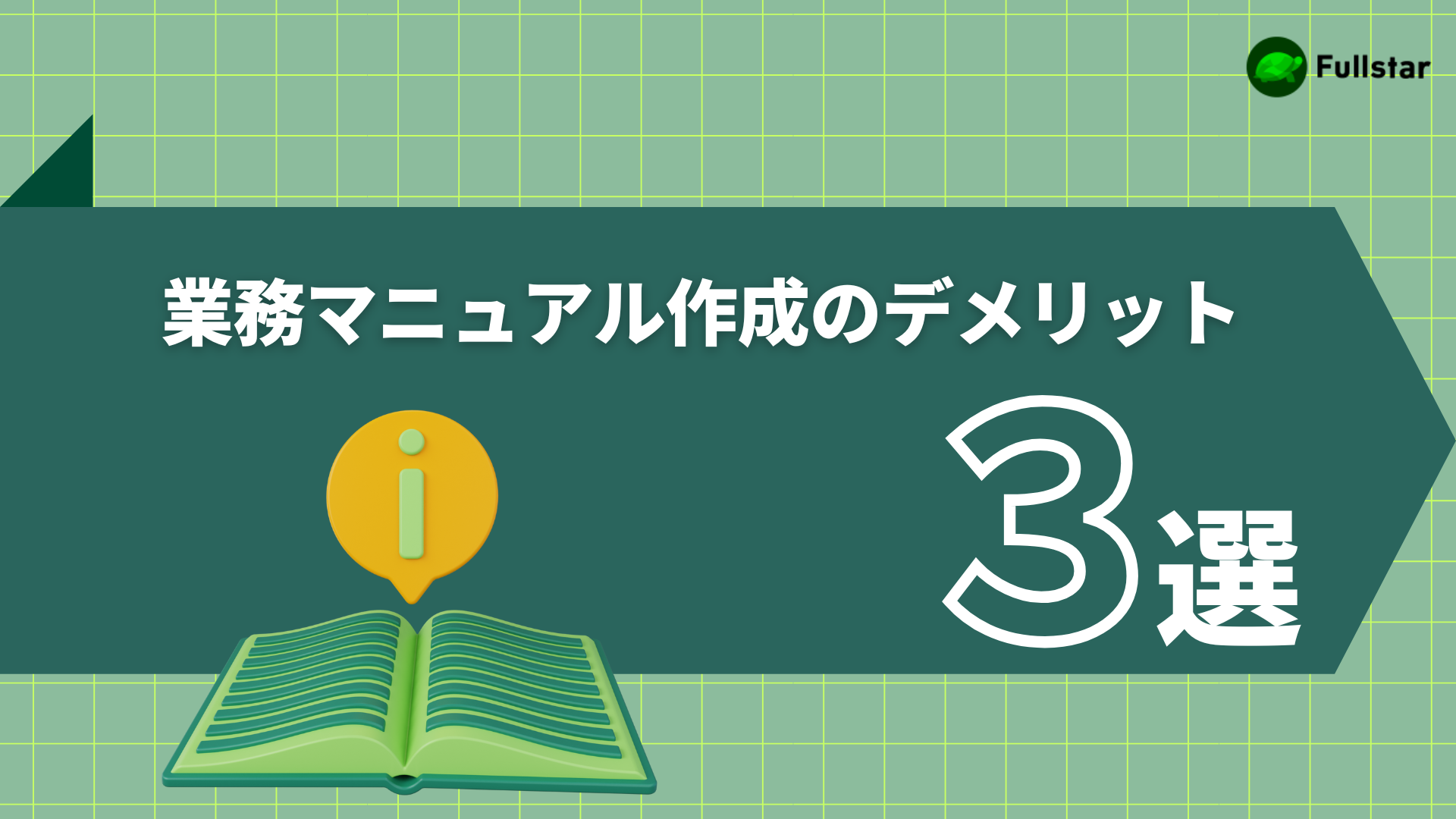
マニュアルをゼロから作ろうとすると、「手順の整理だけで丸一日かかった」といった声がよくあります。実際にコストとして計算すると、その深刻さが分かります。
例えば、ある業務システム(30画面分)の操作マニュアルを1本作るとしましょう。 時給2,000円の社員が担当した場合の工数を試算してみます。
① 業務担当者へのヒアリング: 2時間
② 構成案の作成: 3時間
③ スクリーンショット撮影・加工: 1画面1時間 × 30画面 = 30時間
④ 本文の執筆・説明文の作成: 20時間
⑤ 関係者によるレビューと修正: 5時間
合計工数は60時間となります。
複雑な業務であれば、この工数とコストはさらに膨れ上がります。結果として作成が後回しにされたり、途中で頓挫してしまうケースは少なくありません。
一度作ったマニュアルも、業務フローやツールのアップデートに伴い、すぐに情報が古くなってしまいます。「このマニュアル、情報が古いから使えない」というのは、最も避けたい事態です。
例えば、年に4回システムがアップデートされ、そのたびにマニュアルの一部を修正する必要があるとします。1回の更新に10時間かかるとすれば、年間で40時間がメンテナンスだけで失われます。
更新のルールや担当者が曖昧だと、誰もが「誰かがやるだろう」と考え、マニュアルは価値のない“負の遺産”になってしまいます。
最も悲劇的なのが、時間とコストをかけて作ったマニュアルが誰にも見られないことです。
「存在すら知られていない」「どこにあるかわからず、探せない」といった理由で、マニュアルの閲覧率が10%にも満たないことは珍しくありません。
読むことを前提とした数十ページのPDFマニュアルでは、多忙な現場の従業員は敬遠してしまいます。結局、上司や関係者に直接聞いた方が早いとなり、問い合わせが増えてしまいます。それに答える時間も含め、組織全体で見えないコストが発生し続けます。
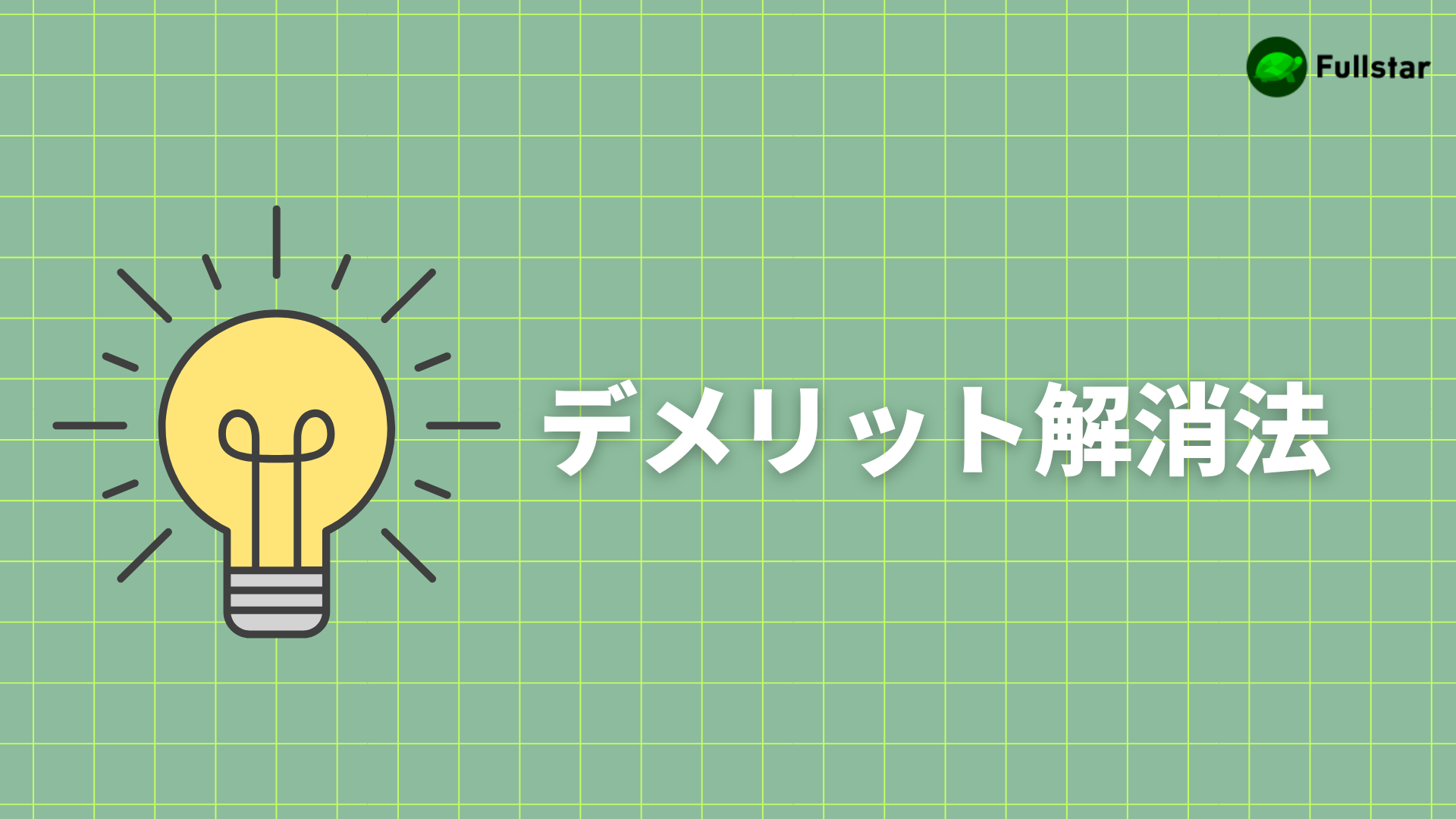
ゼロから作るのではなく、テンプレートを活用すれば、考える負担が減り、品質も安定します。先ほどの60時間かかった作成工数も、テンプレート利用である程度は短縮できるでしょう。
さらに、DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)のようなツールを導入すれば、この課題をより簡単に解決できます。
DAPは、実際のシステム画面上で操作ガイドを自動作成するため、スクリーンショットの撮影・加工・執筆といった工程がほぼ不要になります。
ある企業のデータでは、DAPを導入した結果、マニュアルの作成時間を従来の1/5に短縮できたと報告されています。
先ほどの例で考えると、60時間かかっていた作業が、わずか12時間で完了する計算です。
情報の鮮度を保つには、「四半期ごとの見直し日」や「業務ごとの更新責任者」を明確に定めることが不可欠です。
これに加えてDAPを利用すれば、システムのUI変更にも柔軟に対応でき、ガイドの修正も数クリックで完了するため、メンテナンス工数も大幅に削減できます。「更新日」も自動で記録されるため、現場は常に最新の正しい情報に安心してアクセスできます。
どんなに優れたマニュアルも、見られなければ意味がありません。
この問題の根本的な解決策は、「マニュアルを探しに行かせる」のではなく、「必要な時に、表示される」ことです。
DAPを導入すると、ユーザーがシステムを操作するその画面上に、必要なガイドや入力ルールが画面上にポップアップで表示されます。
これにより、従業員は迷うことなく自己解決できるため、マニュアルの閲覧・利用率が80%以上に達したという報告もあります。
これは、マニュアルを、ユーザーを助ける“動的なガイド”へと進化させるアプローチです。マニュアルの価値を最大化する、最も効果的な解決策と言えるでしょう。
参考:【Fullstar】DX推進およびDAPに関する実態調査第1弾(2024年度)
FullstarのDX推進およびDAPに関する実態調査では37.3%の企業ではマニュアルがあまり利用されていない、また4%の企業が全く利用していないと回答しています。
利用されていないマニュアルは内容の見直しやアクセス方法の改善が必要と言えるでしょう。マニュアル利用の促進のためには、従業員の理解と活用を助けるための教育やサポートや利用状況を把握・管理する体制を強化することが求められます。
マニュアルを“読んでもらう”ためには、「読みやすさ」「探しやすさ」「使うタイミングで自然に表示される」ことが重要です。
具体的には、業務システムと連動して必要なタイミングでマニュアルをポップアップ表示する仕組みや、チャットツールと連携させて“今見るべき情報”を届ける導線が有効です。
こうした「運用の工夫」があるかどうかで、マニュアルの活用度は大きく変わります。
つまり、“見る前提”ではなく“見せる設計”が必要なのです。
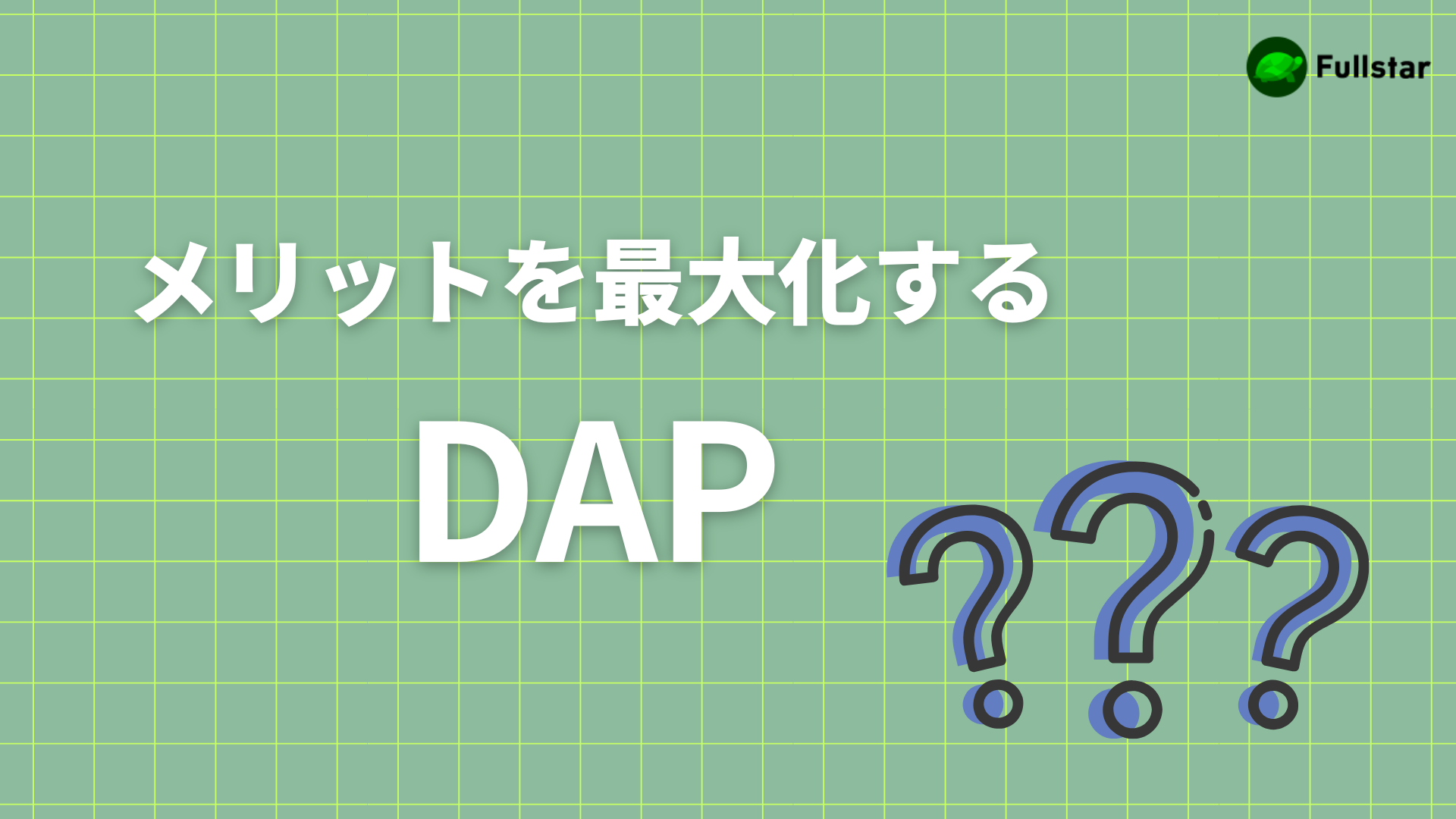
DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)は、ユーザーがシステムやツールを迷わず使えるように支援する仕組みです。
マニュアルを「探すもの」から「必要な場面で自然に表示されるもの」へと変えることで、現場の活用率を飛躍的に高めます。
具体的には、操作画面上にチュートリアルやガイドを表示させることで、マニュアルを読まなくても直感的に業務を進められるようになります。
特に新しいシステム導入時や、問い合わせが多い業務においては、高い効果が期待できます。
ジョブカンでの活用事例

アニメ制作会社のトムス・エンタテインメントでは、社内業務の問い合わせ対応や研修に多くの時間を取られていました。そこでDAPを導入した結果、業務に合わせたガイドを現場で即時表示できるようになり、紙やPDFマニュアルを大量に作成する必要がなくなりました。
その結果、マニュアル作成の工数が従来の5分の1にまで削減され、現場の自己解決率も向上しました。
引用元)"真のDX推進"のためのデジタルアダプションプラットフォーム導入! これからの成長戦略を見据え取り組む社内システム活用。

株式会社RYODENでは、情シス部門への定型的な問い合わせが業務を圧迫していました。DAPを導入し、ERPや業務システムに直接ガイドを表示させる仕組みを構築し、マニュアルを“見に行かなくてもわかる”環境を作ることができ、問い合わせ件数が劇的に減少しました。
特に「初めて操作する画面」や「トラブルが起きやすい箇所」に限定してガイドを配置することで、ピンポイントで支援ができるようになり、現場からも高評価を得ています。
引用元)社内問い合わせを90%削減!デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」を選び、成果を最大化した裏側とは
業務マニュアルは「業務を効率化するための仕組み」であり、「育成・品質・引き継ぎ・改善」のすべてを支える土台です。
しかし、作るだけでは意味がなく、「見える」「見られる」「使われる」状態を実現してこそ、真の効果を発揮します。
その第一歩が、今の業務の見える化です。
何を、誰が、どうやってやっているのかを整理することで、マニュアル化すべき業務・不要な業務も見えてきます。
迷ったらまず“見える化”から始めましょう!

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行