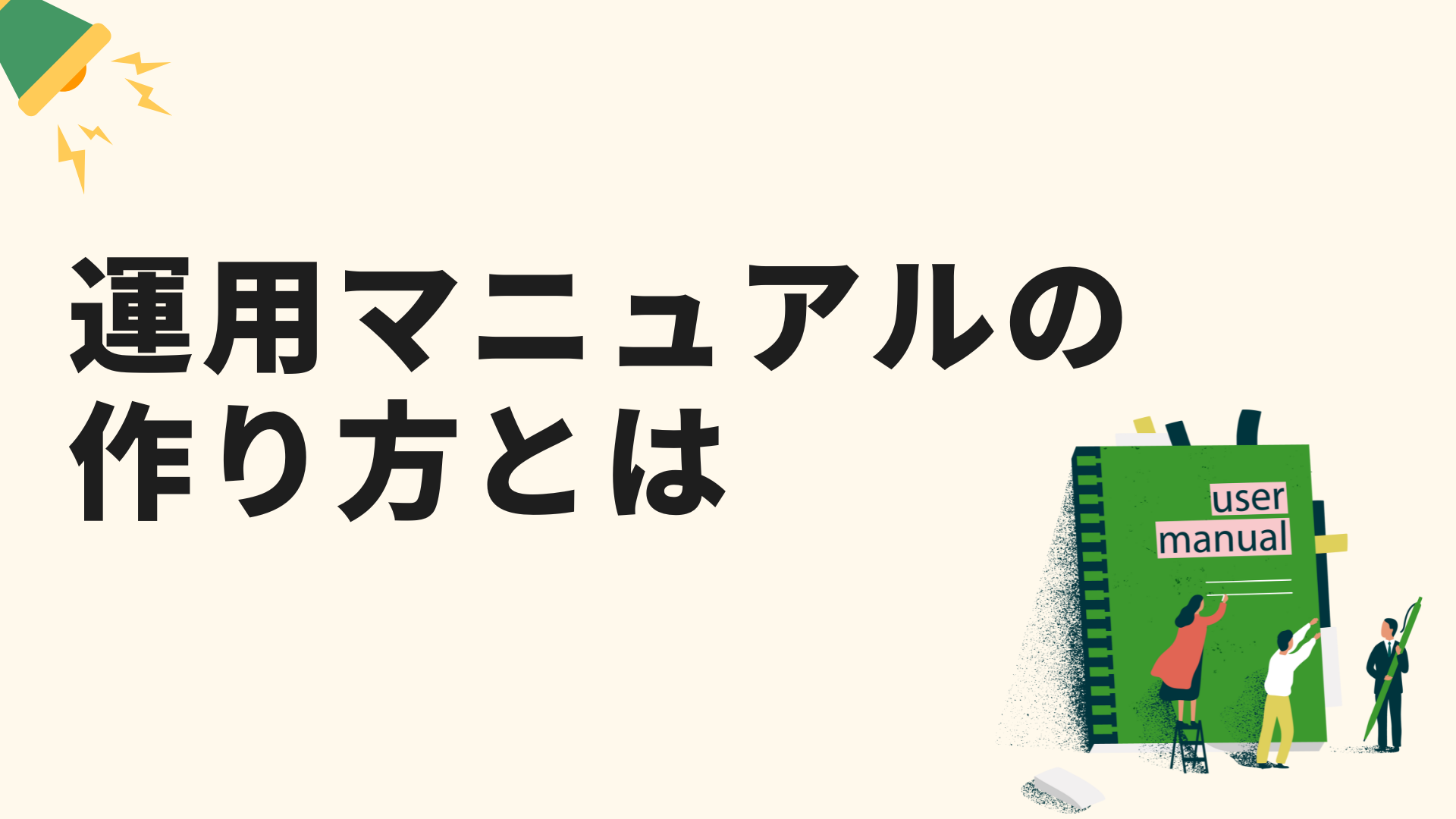

企業活動において、システムやツールの安定稼働は事業継続の生命線です。その安定稼働を支えるのが運用マニュアルであり、システムの運用保守に関する手順やルールを体系的にまとめた文書を指します。担当者のスキルレベルに依存せず、誰もが一定の品質で運用業務を遂行できるようにすることを目的としており、特にDXを推進する企業にとっては、業務の標準化と効率化を実現する上で不可欠な存在です。
本記事では、効果的な運用マニュアルの作り方から、作成を効率化するツールの選び方、さらには形骸化させないための運用ポイントまでを網羅的に解説します。
このような課題をお持ちのDX推進・管理部門のご担当者様に特におすすめです。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
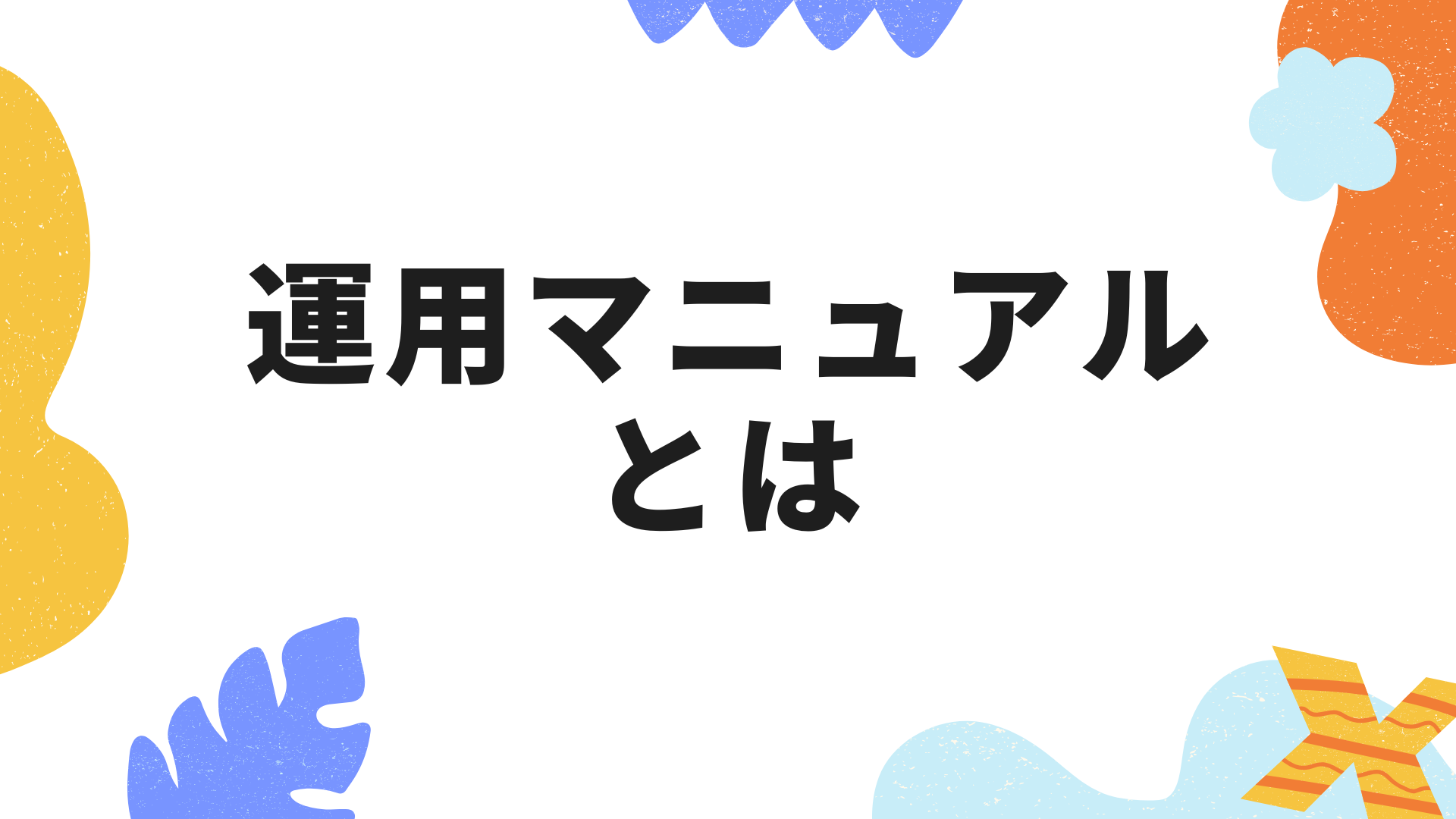
運用マニュアルとは、特定のシステムやツールを安定的に稼働させるための、運用・保守業務に関する手順やルールを体系的にまとめた文書のことです。このマニュアルの主な目的は、担当者が変わっても業務の品質を維持し、トラブル発生時には迅速かつ的確に対応できるようにすることにあります。本セクションでは、まず運用マニュアルの基本的な定義を確認し、混同されがちな他のマニュアルとの違いを明確にします。
運用マニュアルは、システム全体のライフサイクルを支える「縁の下の力持ち」のような存在です。システムの日常的な監視、定期的なメンテナンス、障害発生時の復旧手順、セキュリティポリシーの遵守など、安定稼働を維持するために必要なあらゆる情報が集約されています。
このマニュアルが整備されていることで、運用業務は個人の経験や勘に頼るものから、誰が担当しても一定の成果を出せる標準化された業務へと変わります。例えば、深夜にサーバーダウンが発生した場合でも、運用マニュアルがあれば、駆けつけた担当者が迅速に状況を把握し、定められた手順に沿って冷静に対応することが可能です。これにより、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。
運用マニュアルは、「業務マニュアル」や「操作マニュアル」としばしば混同されますが、その目的と対象範囲には明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、適切なマニュアルを整備する上で非常に重要です。
| 種類 | 目的 | 対象者 | 内容の例 |
|---|---|---|---|
| 運用マニュアル | システム全体の安定稼働の維持 | システム管理者・運用担当者 | サーバー監視、バックアップ手順、障害対応フロー |
| 業務マニュアル | 特定業務の全体の流れを標準化 | 業務担当者全般 | 経費精算の手順、新規顧客の登録フロー |
| 操作マニュアル | 特定ツール・機能の「使い方」の習得 | システム・ツールの利用者 | 勤怠管理システムでの打刻方法、CRMでの顧客検索手順 |
簡単に言えば、運用マニュアルが「システムを守る」ためのものであるのに対し、業務マニュアルは「仕事の進め方を定める」もの、操作マニュアルは「ツールの使い方を教える」ものと言えます。DXを推進する上では、これら3つのマニュアルがそれぞれの役割を果たし、連携することで、企業全体の生産性向上につながります。
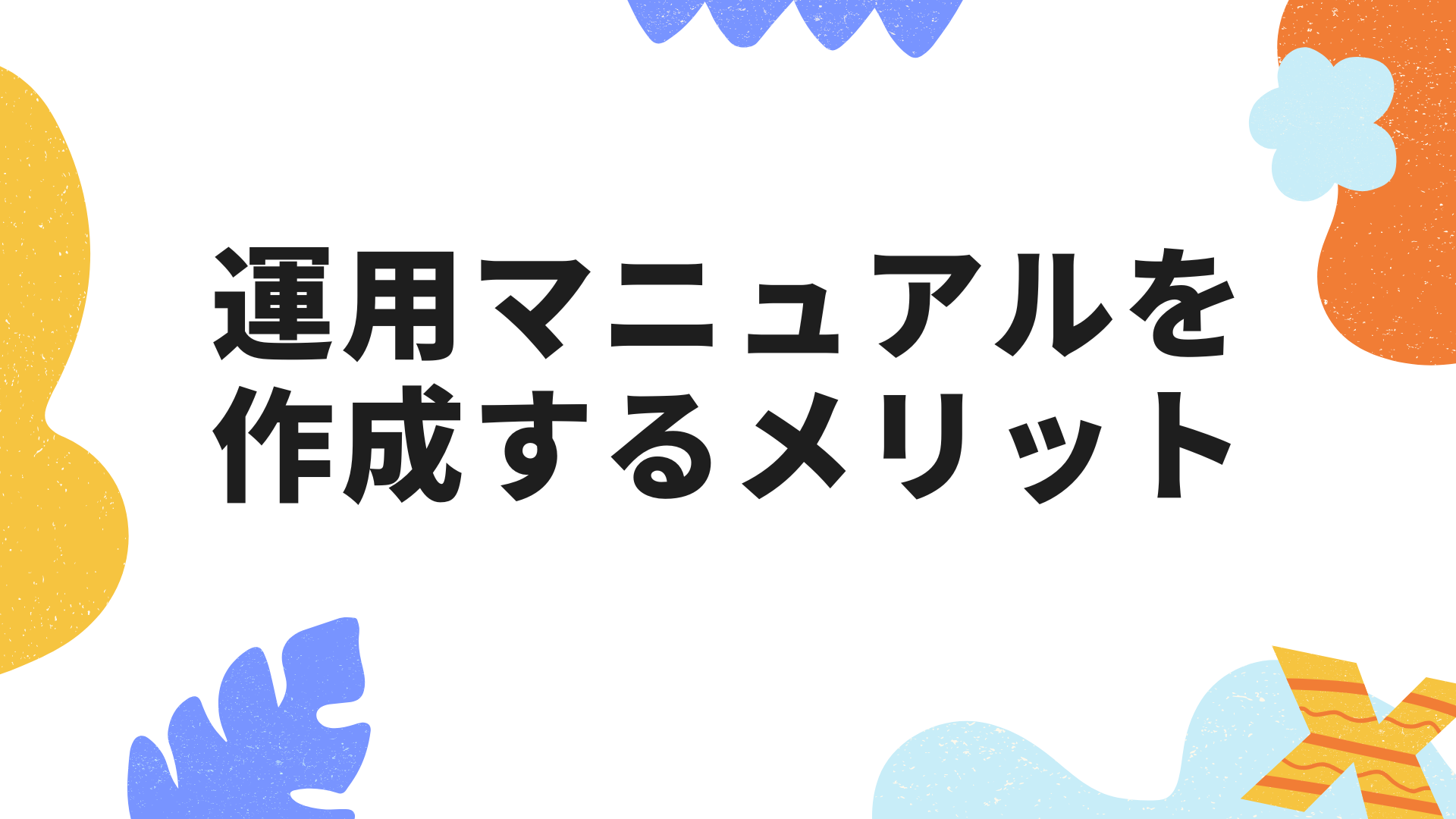
システムの複雑化やビジネス環境の急速な変化に対応するため、運用マニュアルの重要性はますます高まっています。単に業務手順を記録した文書というだけでなく、組織の知識を形式知化し、事業継続性を高めるための戦略的な資産と位置づけられます。明確で質の高い運用マニュアルを整備することで、企業は具体的にどのようなメリットを享受できるのでしょうか。本セクションでは、運用マニュアルがもたらす4つの主要なメリットについて詳しく解説します。
関連記事:業務マニュアル化するべき?マニュアル化のメリットとデメリットが丸わかり!
運用マニュアルの最大のメリットは、業務の属人化を解消し、誰が担当しても同じ品質で作業を遂行できる標準化を実現できる点にあります。「あの人でなければ分からない」「担当者が不在で対応できない」といった状況は、業務停滞のリスクに直結します。マニュアルによって業務プロセスが可視化・共有されることで、特定個人のスキルや経験への依存から脱却し、組織全体として安定した運用体制を構築できます。これは、急な退職や異動が発生した際のスムーズな引き継ぎにも大きく貢献します。
業務手順が標準化されると、作業のムラやミスが減少し、業務品質が安定します。担当者の経験年数やスキルレベルに関わらず、常に一定のクオリティを担保できるため、顧客や利用者からの信頼性向上にもつながります。また、新任の担当者であっても、マニュアルを参照することで迅速に業務を覚えることができ、独り立ちまでの期間を大幅に短縮できます。これにより、組織全体の生産性向上が期待できるのです。
新入社員や異動してきたメンバーに対する教育・研修は、多くの時間と労力を要します。しかし、整備された運用マニュアルがあれば、それを主要な教材として活用できます。OJT(On-the-Job Training)の際も、指導者が付きっきりで教える必要がなくなり、研修を受ける側も自分のペースで学習を進めることが可能です。結果として、指導者・研修者双方の負担が軽減され、教育・研修にかかるコストを大幅に削減できます。
システムの障害やセキュリティインシデントなど、予期せぬトラブルはいつ発生するか分かりません。そのような緊急時において、運用マニュアルは冷静かつ迅速な対応を可能にするための「行動指針」となります。障害の切り分け手順、復旧作業のフロー、関係各所への報告ルールなどが明確に定められていれば、パニックに陥ることなく、被害を最小限に抑えるための的確な初動対応が可能です。これは、事業継続計画(BCP)の観点からも極めて重要であり、組織的なリスク管理能力の強化に直結します。
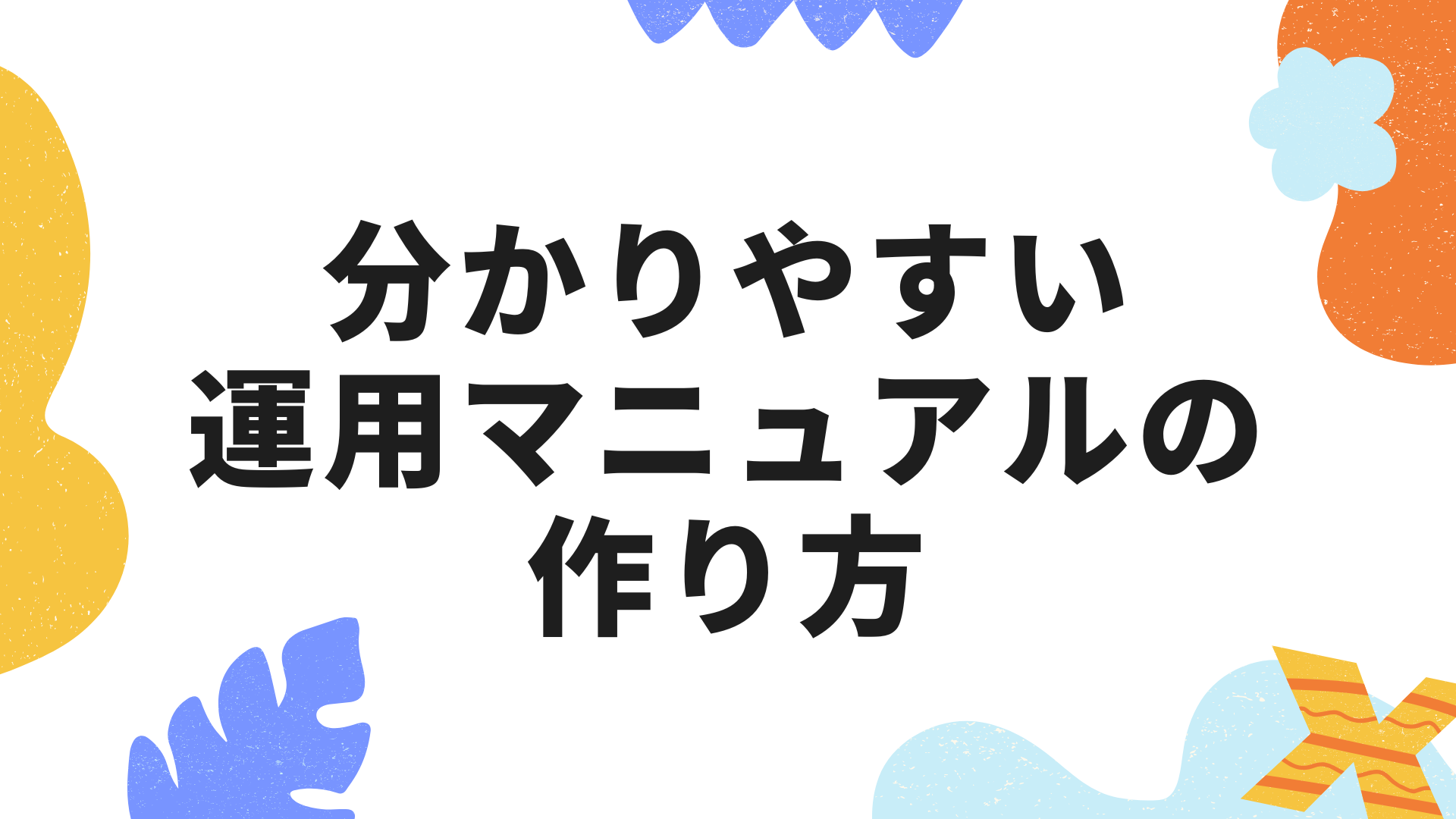
効果的な運用マニュアルは、思い付きで書き始めても完成しません。読み手の視点に立ち、情報を整理し、体系的にまとめるプロセスが不可欠です。ここでは、誰が読んでも理解しやすく、実務で本当に役立つ運用マニュアルを作成するための具体的な7つのステップを解説します。この手順に沿って進めることで、作成の抜け漏れを防ぎ、効率的に質の高いマニュアルを完成させることができます。
最初のステップは、「何のために、誰のために」このマニュアルを作るのかを定義することです。例えば、「新任の担当者が3日で基本的な監視業務を一人で遂行できるようにする」といった具体的な目的を設定します。また、読み手はシステムに関する知識が豊富なエンジニアなのか、それともITに不慣れなオペレーターなのかによって、使用する言葉の専門性や説明の詳しさが大きく変わります。この初期設定が、マニュアル全体の方向性を決定づけます。
次に、マニュアルに記載すべき業務内容をすべて洗い出します。日常的な定型業務から、月に一度のメンテナンス作業、緊急時の対応フローまで、関連するタスクを網羅的にリストアップします。このとき、あまりに範囲を広げすぎると作成が困難になるため、「今回のマニュアルではサーバーの正常性監視までを対象とし、アプリケーションの改修手順は含めない」のように、どこまでを範囲とするかを明確に定義することが重要です。
洗い出した業務内容をもとに、マニュアル全体の骨子となる構成案、つまり目次を作成します。業務の流れや論理的なつながりを意識して、章や節を組み立てていきましょう。例えば、「1. 概要」「2. 日常点検業務」「3. 定期メンテナンス」「4. 障害対応手順」といった大きな枠組みを作り、その中に具体的な作業項目を配置します。良い目次は、読者が目的の情報をすぐに見つけるための道しるべとなります。
構成案が固まったら、いよいよ本文の執筆に取り掛かります。文章は PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識し、「〜してください」という能動態で、簡潔かつ分かりやすく記述することを心がけます。特に、システムの操作画面や構成図などは、言葉だけで説明するよりもスクリーンショットや図を積極的に活用する方が、読者の理解を格段に深めることができます。このプロセスは、まさに業務標準化を文書に落とし込む作業と言えるでしょう。
初稿が完成したら、必ず複数の関係者にレビューを依頼しましょう。実際にそのマニュアルを利用する現場の担当者や、業務に詳しい上長など、異なる視点から内容をチェックしてもらうことが重要です。レビューでは、「記述内容が現状と合っているか」「専門用語が多すぎないか」「手順に分かりにくい部分はないか」といった観点でフィードバックをもらい、客観的な視点で内容を修正・改善していきます。
完成したマニュアルは、関係者全員がいつでも簡単にアクセスできる場所に保管する必要があります。ファイルサーバーの特定のフォルダや、社内のナレッジ共有ツール、イントラネットなどが一般的な保管場所です。保管したら、その場所を関係者に周知することを忘れないでください。せっかく作ったマニュアルも、どこにあるか分からなければ存在しないのと同じです。
運用マニュアルは「作って終わり」ではありません。システムの仕様変更や業務フローの見直しに伴い、情報は古くなっていきます。そのため、「半年に一度は見直しを行う」「システムのアップデート時には必ず更新する」といったメンテナンスのルールを定め、常に最新の状態を保つことが極めて重要です。担当者を決め、定期的な見直しを業務プロセスに組み込むことで、マニュアルの陳腐化を防ぎ、継続的に価値あるものとして活用できます。
関連記事:マニュアルをわかりやすくする作成ポイント5つ・デザインや書き方も解説
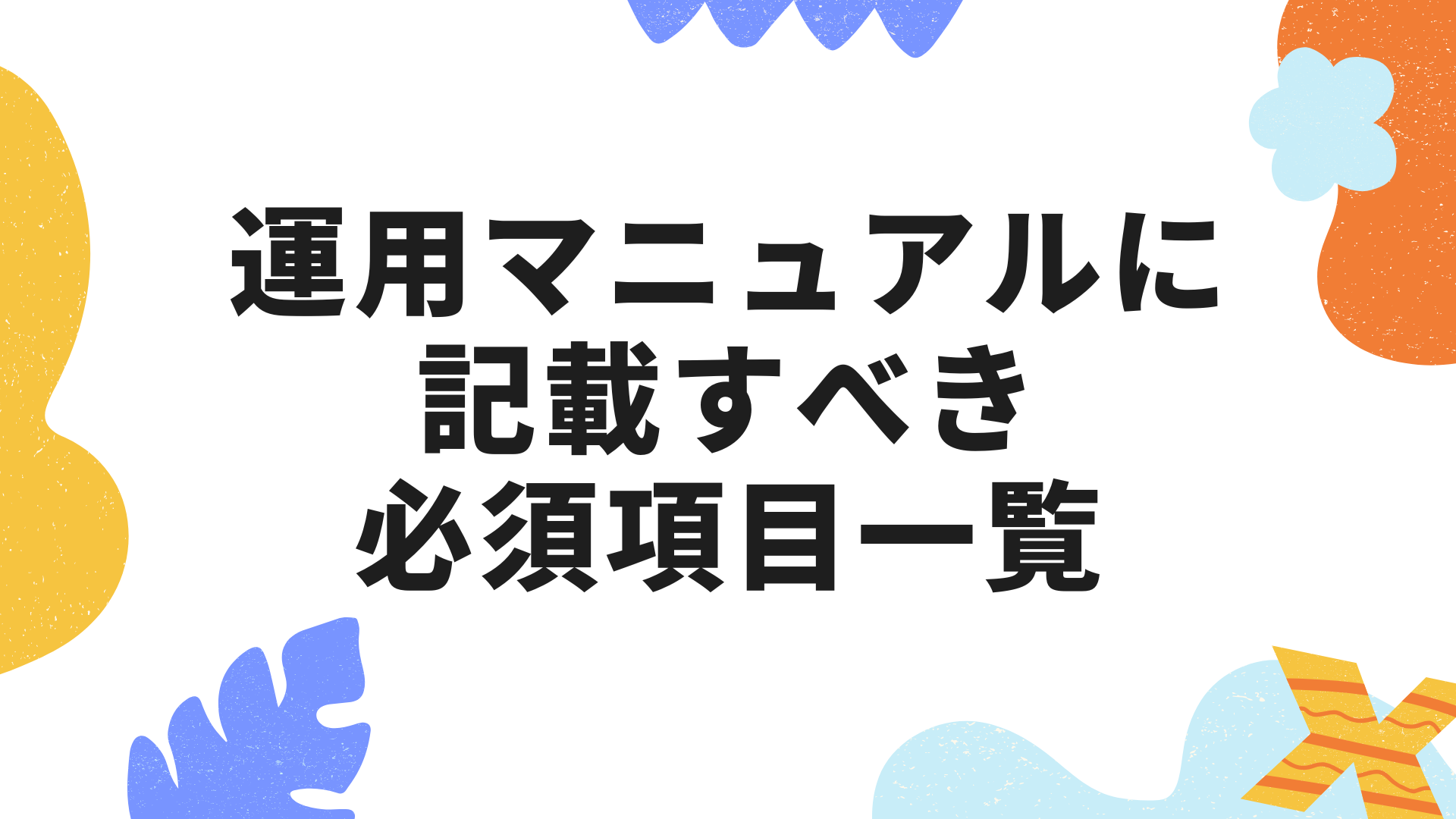
分かりやすい運用マニュアルを作成するためには、その構成要素、つまり「何を記載すべきか」を事前に把握しておくことが重要です。項目に抜け漏れがあると、いざという時に役立たないマニュアルになってしまいます。ここでは、どのようなシステムの運用マニュアルにも共通して含めるべき、6つの必須項目を解説します。これらの項目を網羅することで、マニュアルの網羅性と実用性が格段に向上します。
マニュアルの冒頭には、その文書全体の概要を記載します。具体的には、「このマニュアルの目的」「対象読者(誰向けか)」「対象システムの範囲」「マニュアルの管理者」などを明記します。これにより、読者はマニュアルを開いてすぐに、これが自分にとって必要な情報かどうか、どのような位置づけの文書なのかを正確に理解することができます。
個別の作業手順を記述する前に、まずは業務の全体像を示しましょう。フローチャートなどを用いて、業務の開始から終了までの一連の流れや、関連する部署・システムとの関係性を視覚的に示すと効果的です。この「鳥の目」の視点を提供することで、読者は各作業が全体のどの部分に位置するのかを理解しやすくなり、業務への理解が深まります。
マニュアルの中核となる部分です。一つひとつの作業について、「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行うのかを、ステップバイステップで具体的に記述します。ここでのポイントは、読者が迷わず作業できるよう、スクリーンショットや図をふんだんに用いることです。曖昧な表現は避け、クリックするボタンや入力するコマンドなどを明確に示します。こうした詳細な手順書は、OJT(On-the-Job Training)の効果を最大化する上でも欠かせません。
運用業務にはトラブルがつきものです。この項目では、過去に発生した障害や、想定されるエラーごとに、「現象」「原因」「対処法」をセットで記載します。エラーメッセージの一覧や、その意味、そして具体的な解決手順をまとめておくことで、担当者は慌てず、迅速に初期対応を行うことができます。ナレッジが蓄積されるほど、このセクションは充実し、マニュアルの価値を高めます。
重大な障害が発生した際には、迅速なエスカレーション(上長や関係部署への報告・連携)が求められます。そのため、緊急時の連絡先リスト(部署、担当者名、電話番号、メールアドレス)と、連絡する際の優先順位を明確に記載しておく必要があります。また、「どのような情報を」「誰に」「どのタイミングで」報告するのか、といったエスカレーションルールを定めておくことで、組織的な対応が可能になります。
マニュアルの信頼性を保つために、改訂履歴は必ず記載しましょう。「いつ」「誰が」「どの部分を」「なぜ」変更したのかを記録しておくことで、読者は常に最新の情報を確認できます。また、過去の経緯を遡って確認したい場合にも役立ちます。改訂履歴の存在は、そのマニュアルが適切に管理されていることの証明にもなります。
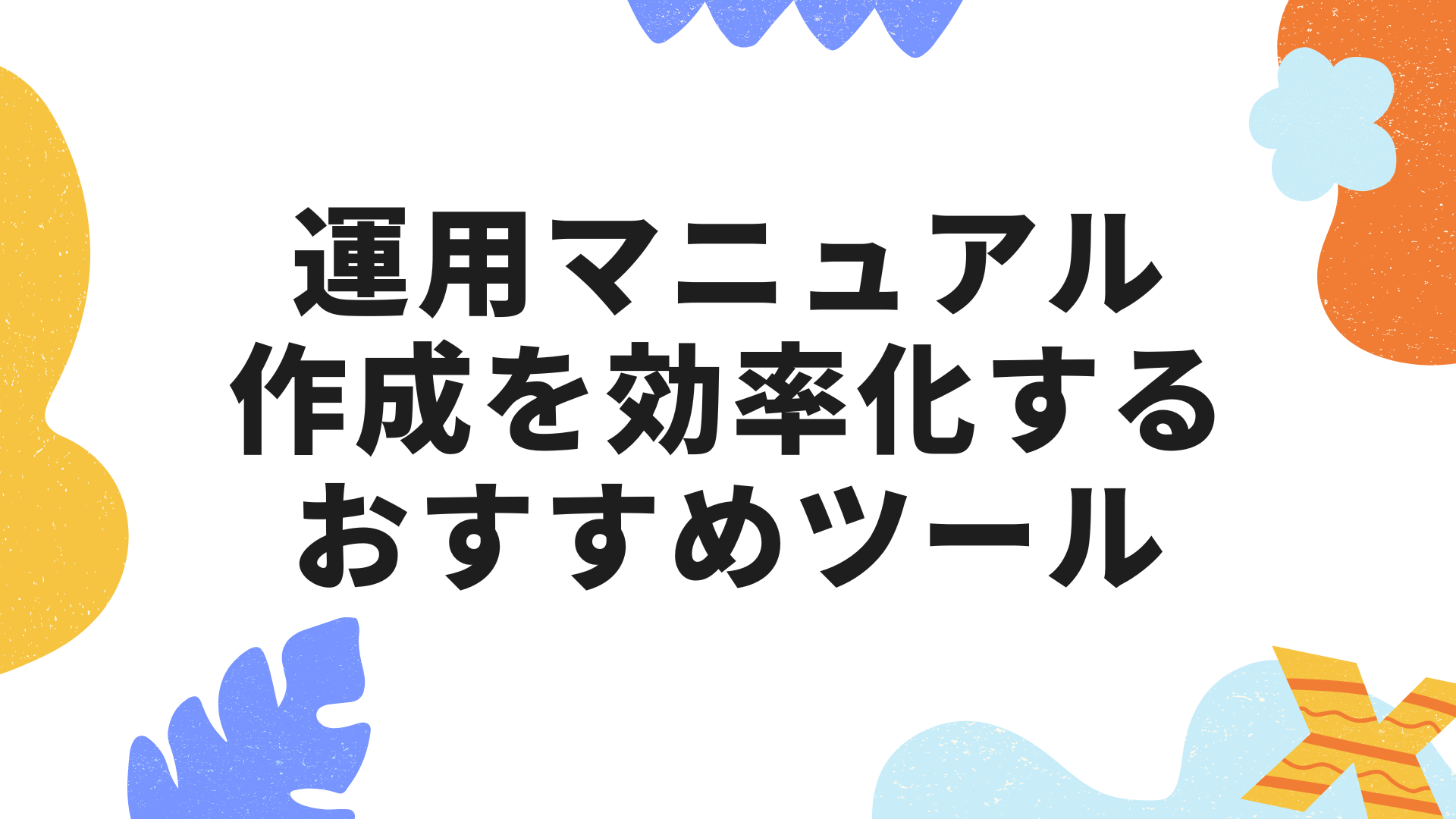
運用マニュアルの重要性を理解していても、作成に手間がかかるため、後回しになってしまうケースは少なくありません。しかし、適切なツールを活用することで、作成プロセスを大幅に効率化し、クオリティを高めることが可能です。ここでは、マニュアル作成の目的や規模に応じて選べる4つのカテゴリのツールを紹介し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
最も手軽に始められるのが、Microsoft Office製品に代表される汎用的なドキュメント作成ソフトです。ほとんどの企業で標準導入されており、多くの人が基本的な操作に慣れているため、追加のコストや学習なしに作成を開始できるのが最大のメリットです。簡単な手順書や、印刷して配布する形式のマニュアルであれば、これらのツールでも十分に役割を果たします。しかし、バージョン管理が煩雑になりがちで、動画の埋め込みなどリッチな表現には向いていません。
関連記事:【完全版】誰でも簡単にExcel(エクセル)でマニュアル作成!
関連記事:【完全版】誰でも簡単にWord(ワード)でマニュアル作成!
より本格的で分かりやすいマニュアルを目指すなら、専用ツールの導入が効果的です。これらのツールには、スクリーンショットの撮影・編集、動画キャプチャ、テンプレート機能、多言語対応など、マニュアル作成に特化した機能が豊富に搭載されています。操作手順を録画して自動でマニュアル化する機能を備えたものもあり、作成工数を劇的に削減できます。導入にはコストがかかりますが、更新のしやすさや管理の一元化といったメリットは、長期的に見てその価値を上回る可能性があります。
社内WikiやConfluence、Notionといったナレッジ共有ツールも、運用マニュアルの作成・管理プラットフォームとして非常に有効です。これらのツールは、複数人での同時編集やコメント機能に優れており、チームで協力しながらマニュアルを育てていくスタイルに適しています。強力な検索機能で目的の情報をすぐに見つけられ、常にオンラインで最新版が共有されるため、版管理の悩みから解放されます。関連情報へのリンクも容易で、マニュアルを中心とした知識ベースを構築できます。
デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)は、従来のマニュアル作成ツールとは一線を画す新しいソリューションです。DAPは、マニュアルを「読む」のではなく、システム画面上で「体験」させることを目的としています。例えば、システムの操作画面上に「次はこのボタンをクリックしてください」といった吹き出し(ツールチップ)やガイドをリアルタイムで表示し、ユーザーをゴールまで導きます。これにより、ユーザーはマニュアルと画面を見比べる必要がなくなり、迷うことなく操作を習得できます。これは、新しいシステム導入を成功させる上で、非常に強力なアプローチです。
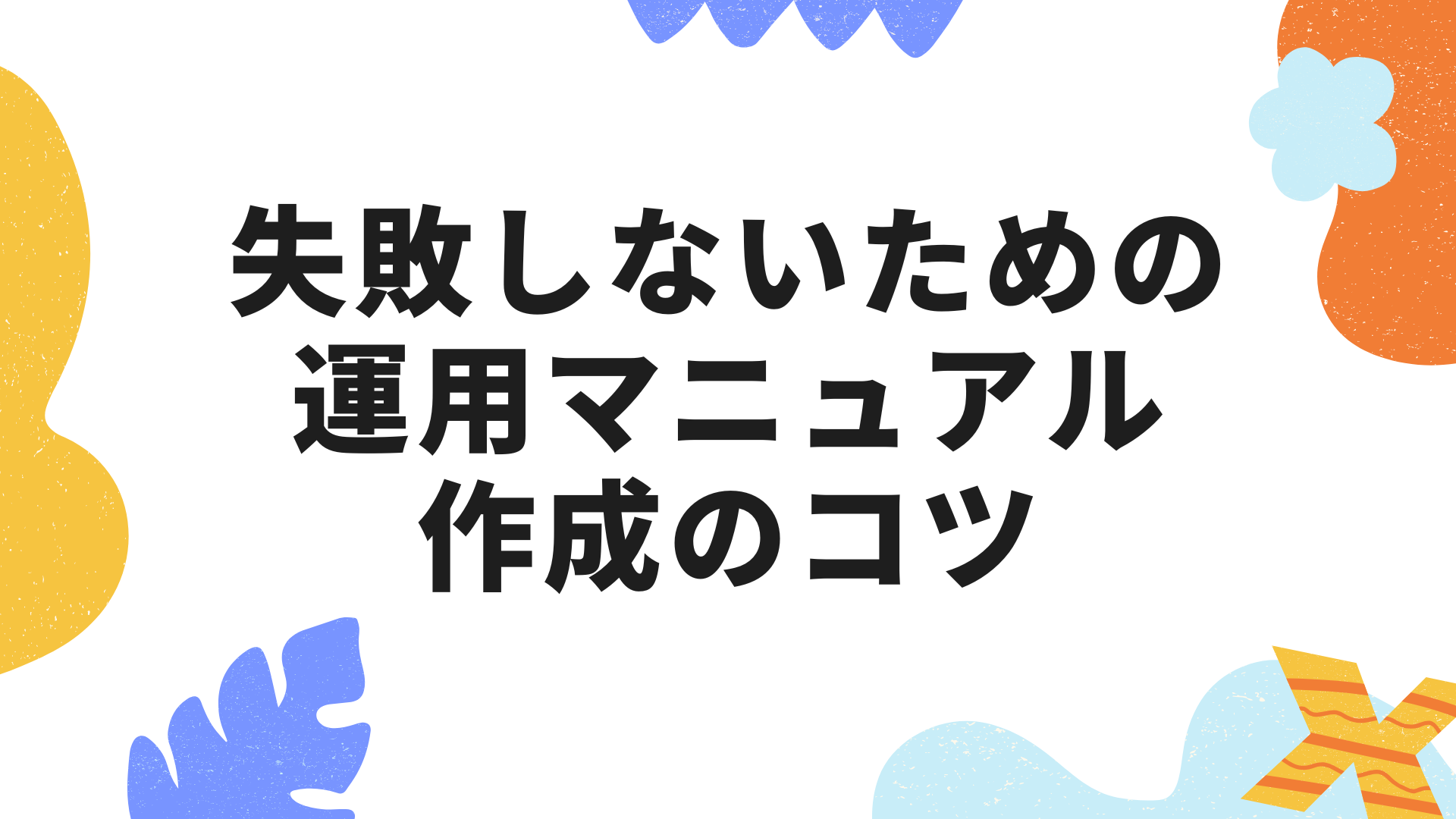
ただ手順を羅列するだけでは、本当に「使える」運用マニュアルにはなりません。読み手の立場に立ち、分かりやすさを追求するための工夫が求められます。ここでは、マニュアルの質を格段に向上させ、作成後に「誰も使ってくれない」という事態を避けるための、4つの実践的なコツを紹介します。これらのポイントを意識することで、マニュアルは現場で頼られる存在へと変わります。
文章を記述する際は、常に「5W1H」(When:いつ, Where:どこで, Who:誰が, What:何を, Why:なぜ, How:どのように)を明確にすることを心がけましょう。「サーバーを再起動する」と書くだけでなく、「毎月第一月曜日の午前3時に(When)、運用担当者が(Who)、本番環境のWebサーバーを(Where)、バックアップ取得後に(What)、設定変更を反映させるため(Why)、所定の手順書に従って再起動する(How)」のように具体的に記述することで、誤解や作業漏れのリスクを大幅に減らすことができます。
マニュアルは、必ずしも専門知識が豊富な人だけが読むとは限りません。新任の担当者や他部署のメンバーでも理解できるよう、できるだけ専門用語や社内だけで通用する略語の使用は避け、平易な言葉で説明することが重要です。やむを得ず専門用語を使う場合は、初出時に「SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)のように、カッコ書きで補足説明を加えるといった配慮が、マニュアルの分かりやすさを大きく左右します。
複雑な操作手順やシステムの構成を文章だけで説明するには限界があります。「百聞は一見に如かず」の言葉通り、図やスクリーンショットを効果的に活用しましょう。特に、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の操作を説明する際には、実際の画面キャプチャに矢印や囲み線で「どこをクリックするのか」を明示することで、読者は直感的に内容を理解できます。文章と画像を適切に組み合わせることが、分かりやすいマニュアルへの近道です。
前述の通り、運用マニュアルは一度作成したら終わりではありません。最も重要なのは、継続的に改善していく仕組みを組織内に作ることです。マニュアルの末尾にフィードバック用の連絡先を明記したり、ナレッジ共有ツール上でコメントを書き込めるようにしたりして、利用者からの意見を積極的に収集しましょう。そして、そのフィードバックを元に定期的に内容を見直し、更新する責任者を定めておくことで、マニュアルは常に「生きた情報」としてその価値を保ち続けます。
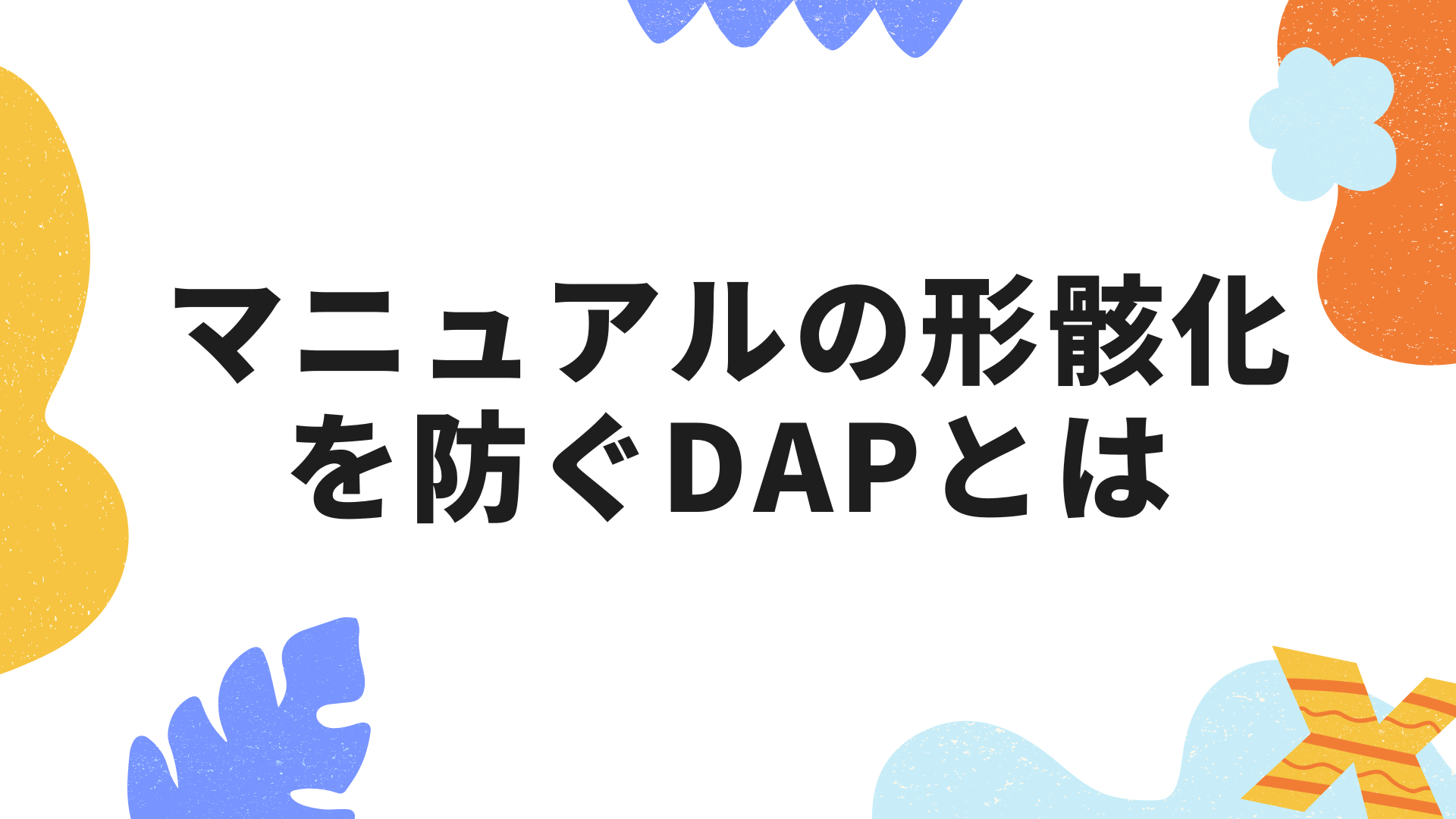
多くの企業が直面する課題が、手間をかけて作成した運用マニュアルが「形骸化」してしまう問題です。マニュアルが実際の業務フローと乖離したり、そもそも存在を忘れられて読まれなくなったりするのです。この根本的な原因は、多くの場合「マニュアルを参照する手間」にあります。そこで注目されているのが、マニュアルのあり方を根本から変える「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」という新しいテクノロジーです。
従来の運用マニュアルは、システムとは別のファイル(PDFやWebページ)として存在するため、ユーザーは操作画面とマニュアルを何度も見比べる必要がありました。この手間が、マニュアルが使われなくなる大きな要因です。
デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)は、この問題を解決します。DAPを導入すると、システムやアプリケーションの画面上に、操作をナビゲートする「吹き出し」や「ガイド」を直接表示させることができます。まるでカーナビが「50m先、右折です」とリアルタイムで案内してくれるように、ユーザーが今まさに操作している画面上で、「次にクリックすべきボタン」や「入力すべき内容」をステップバイステップで示してくれます。これにより、ユーザーはマニュアルを探したり読んだりすることなく、直感的に正しい操作を完遂できるのです。
弊社が提供するデジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar(フルスタ)」は、このリアルタイムナビゲーション機能を、プログラミングの知識がなくても(ノーコードで)簡単に設定できるツールです。
「Fullstar」を活用することで、従来のマニュアル作成・運用業務を劇的に変革できます。
「Fullstar」は、運用マニュアルを「読まれるもの」から「使われるもの」へと進化させ、システムの定着化と形骸化防止を同時に実現するソリューションです。 フォーム入力後、資料を閲覧できます。
【3分でわかる】Fullstar(フルスタ)概要資料


無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行