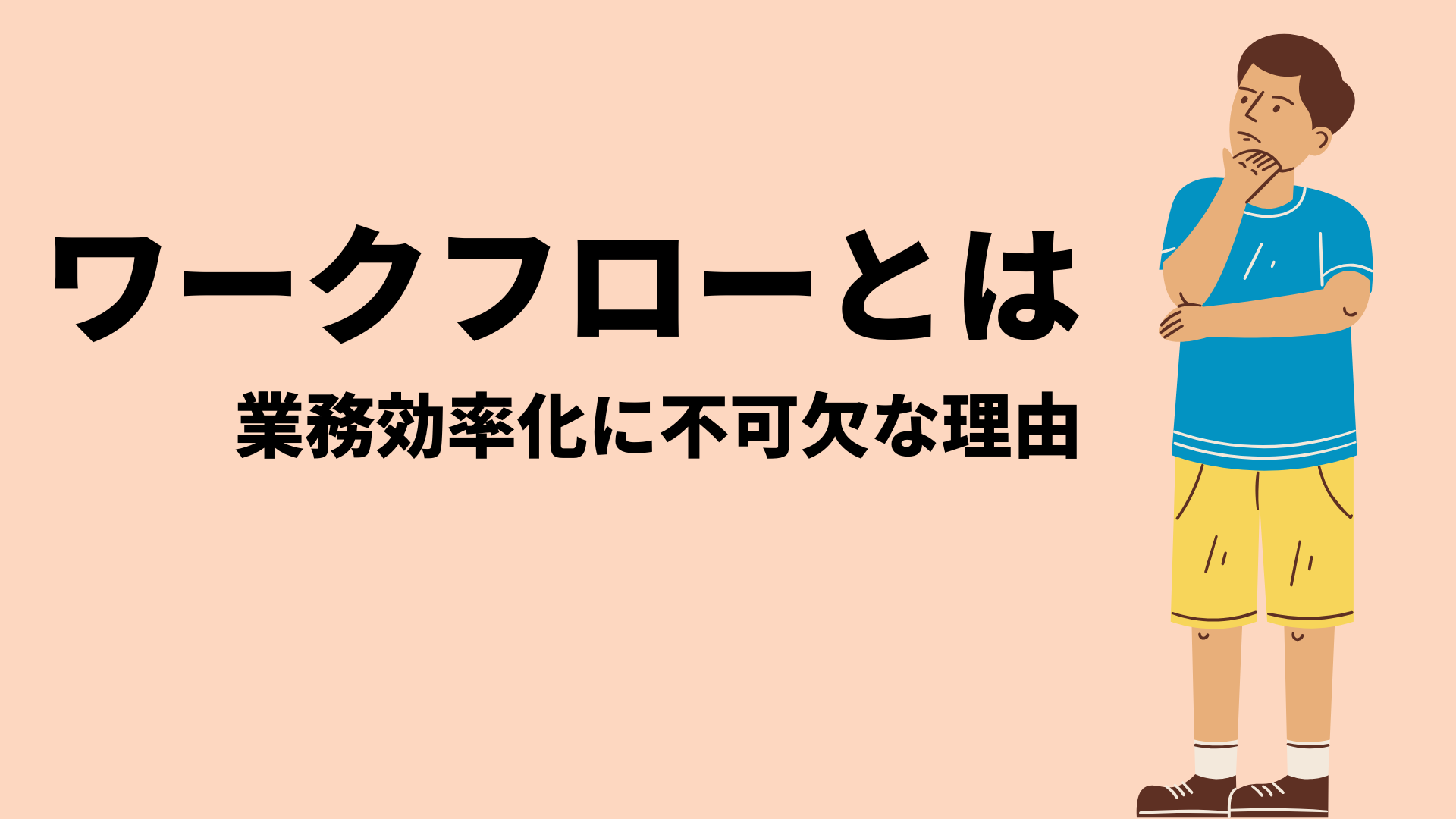

「ワークフローの作り方」を理解し実践することは、業務の属人化を防ぎ、組織の生産性を向上させるための重要な鍵となります。ワークフローとは、一連の業務における手続きや情報の流れを図式化し、誰が見ても理解できるように可視化したものです。単に業務の流れを示すだけでなく、承認ルートの明確化や内部統制の強化にも繋がり、組織全体の業務効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
本記事では、具体的なワークフローの作り方を4つのステップで解説するとともに、作成を成功させるコツや、自社に最適なツールの選び方までを網羅的にご紹介します。
この記事は、特に以下のような課題をお持ちの方におすすめです。
さらに、作成したワークフローを形骸化させず、社内に確実に定着させるための新しいアプローチも解説します。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
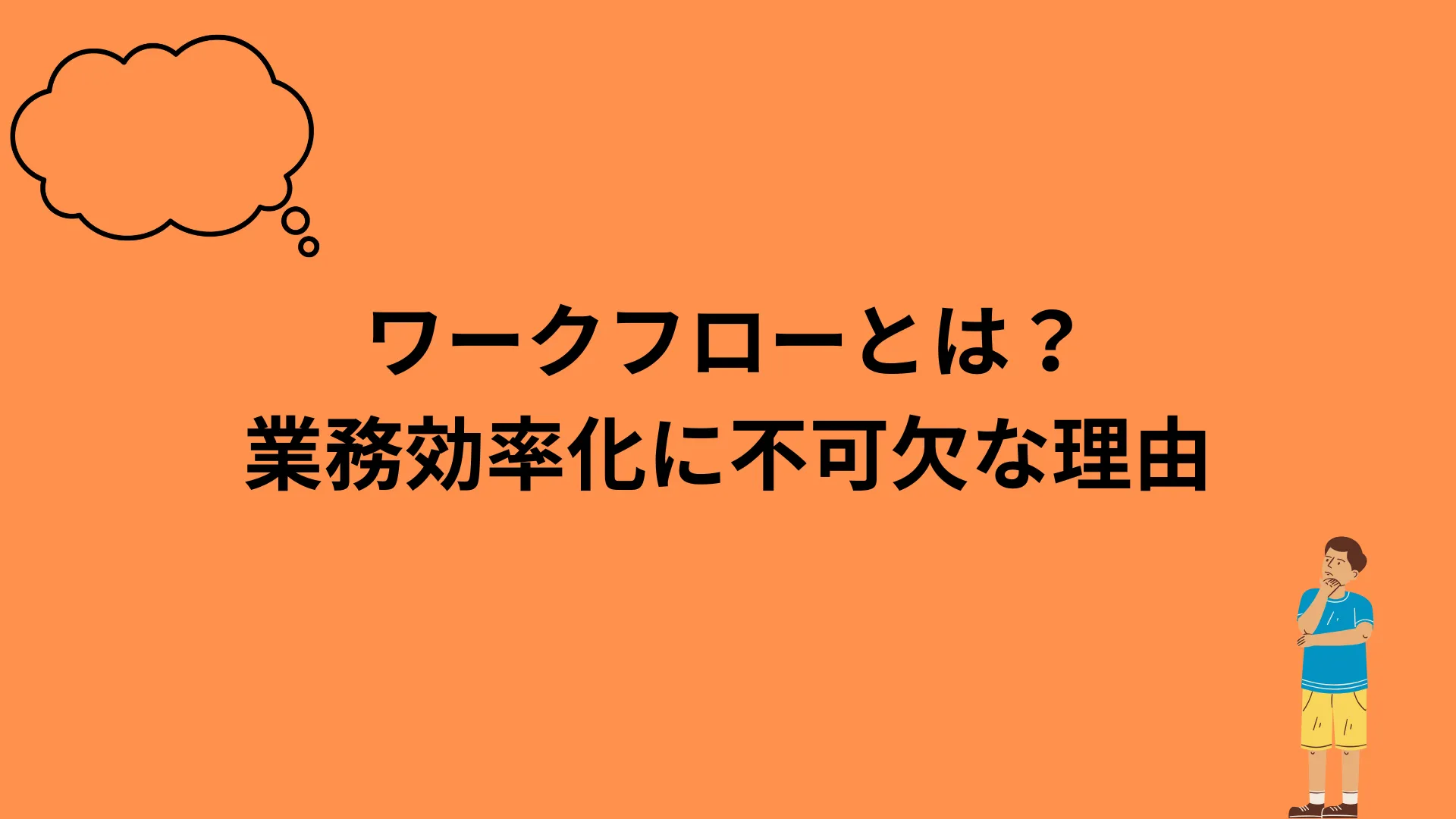
ワークフローとは、直訳すると「仕事(Work)の流れ(Flow)」であり、業務における一連の手続きや情報の流れを図式化したものを指します。具体的には、「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行うのかというルールを明確にし、業務プロセス全体を可視化します。これにより、業務の標準化を促進し、組織全体の生産性向上を実現するために不可欠な要素となっています。
関連記事:ワークフロー管理とは?重要性と業務の例、DXを加速させる管理システムの選び方まで解説
「ワークフロー」と似た言葉に「業務フロー」がありますが、両者は視点が異なります。業務フローが個々の業務手順や作業の流れそのものを示すのに対し、ワークフローは特に申請と承認のプロセスに焦点を当て、人や部門間での情報の受け渡しや意思決定の流れです。申請から決裁までの流れは、典型的なワークフローです。業務フローという大きな枠組みの中に、承認プロセスを担うワークフローが存在します。
現代のビジネス環境では、市場の変化に迅速に対応するためのスピーディーな意思決定が求められます。しかし、多くの企業では、紙媒体での申請・承認プロセスや、担当者不在による業務の停滞といった課題を抱えています。
ワークフローを作成し、最適化することは、こうしたボトルネックを解消する第一歩です。業務プロセスを可視化することで、どこに無駄があり、どこを改善すべきかが明確になります。さらに、ワークフローシステムを導入すれば、申請・承認業務の電子化が可能となり、場所や時間を選ばない柔軟な働き方にも対応できます。こうしたDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の観点からも、ワークフローの整備は企業競争力を高める上で極めて重要と言えるでしょう。
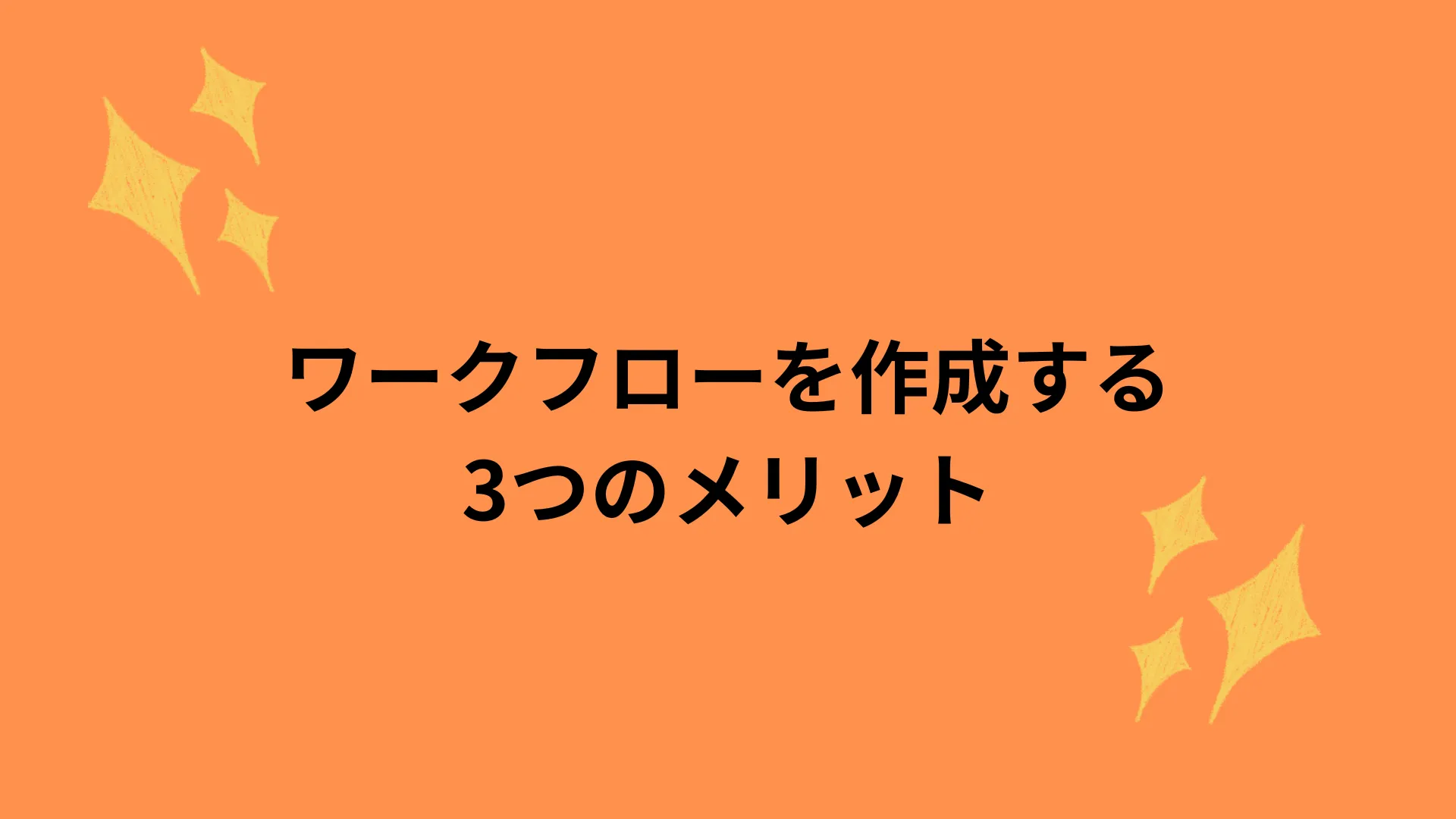
適切なワークフローを作成・運用することは、企業に多くのメリットをもたらします。主なメリットとして、「業務プロセスの可視化」「意思決定の迅速化」「内部統制の強化」の3点が挙げられます。これらは、単なる業務効率化に留まらず、組織全体の競争力向上に直結する重要な要素です。以下で、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
ワークフローを作成する最大のメリットは、業務プロセスが「見える化」されることです。誰がどのような手順で業務を進めているのか、どこで承認が必要なのかが一目瞭然になるため、業務の流れを関係者全員が正確に把握できます。
これにより、特定の人しか業務の進め方を知らない「属人化」の状態を解消できます。業務が標準化されることで、担当者の急な不在や異動、退職が発生しても、他の人がスムーズに業務を引き継ぐことが可能です。また、新人教育の際にも、可視化されたワークフローは優れたマニュアルとして機能し、教育コストの削減にも繋がります。
ワークフローによって申請から承認・決裁までのルートが明確に定められると、書類の回付や確認作業がスムーズに進みます。特に、紙の書類を回覧する場合に起こりがちな「書類がどこで止まっているか分からない」「承認者が不在で先に進めない」といった問題を解消できます。
ワークフローシステムを導入すれば、申請や承認をオンライン上で行えるため、承認者は外出先やテレワーク中でも対応可能です。これにより、承認プロセスの停滞がなくなり、意思決定のスピードが大幅に向上します。結果として、ビジネスチャンスを逃すことなく、迅速な経営判断を下せるようになり、組織全体の生産性向上に大きく貢献します。
内部統制とは、企業の事業活動を健全かつ効率的に運営するための社内ルールや仕組みのことです。ワークフローは、この内部統制を強化する上で非常に有効な手段となります。
あらかじめ定められたルールと承認ルートに基づいて業務が実行されるため、担当者の独断による不正やミスの発生を未然に防ぎます。例えば、一定金額以上の取引には必ず部長承認を必要とするといったルールをワークフローに組み込むことで、不正な支出を抑制できます。また、すべての申請・承認プロセスが記録として残るため、監査対応の際にも迅速かつ正確な証跡を提示でき、コンプライアンス(法令遵守)体制の強化に繋がります。
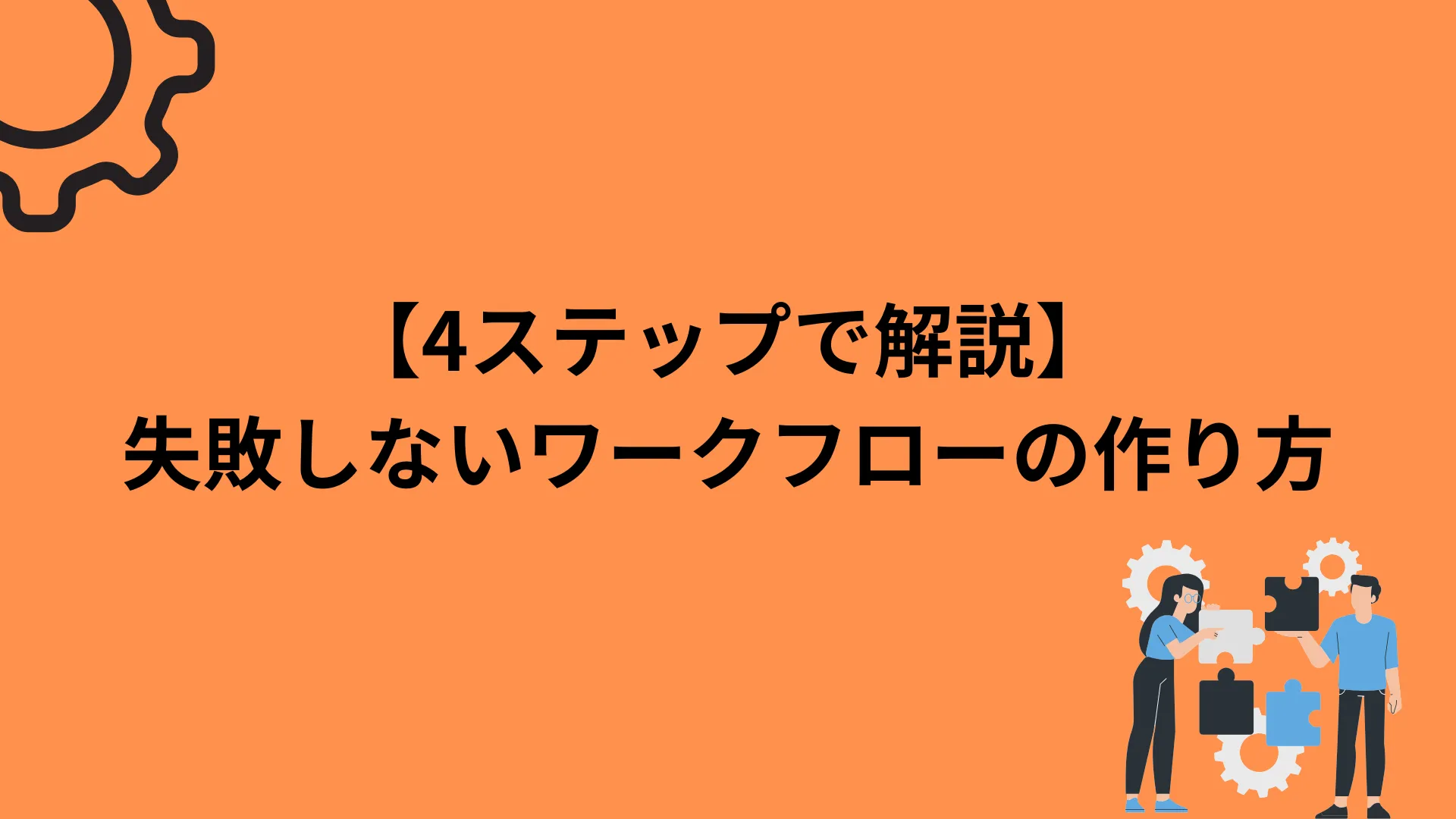
ここからは、実際にワークフローを作成するための具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。いきなりツールを導入したり、複雑なフローチャートを描き始めたりするのではなく、現状の業務を正しく理解し、段階的に進めることが成功の鍵です。各ステップのポイントを押さえ、着実に進めていきましょう。
最初のステップは、ワークフロー化の対象となる業務を洗い出し、その目的を明確にすることです。
業務の洗い出し: まず、社内に存在する申請・承認業務をリストアップします。例えば、「経費精算」「稟議申請」「備品購入申請」「休暇申請」など、定型的なプロセスを持つ業務が対象となります。全ての業務を一度に進めるのは困難なため、特に課題が大きい業務や、導入効果が高いと思われる業務から優先順位をつけましょう。
目的の明確化: 次に、なぜその業務をワークフロー化するのか、目的を具体的に定義します。「承認時間を50%削減する」「書類の紛失リスクをゼロにする」など、定量的な目標を設定することが重要です。この目的が、後のステップでの判断基準となります。
次に、対象業務の現在のプロセスを詳細に整理し、関係者を特定します。
業務プロセスの整理: 業務の開始から完了までの一連の流れを書き出します。具体的には、「誰が申請し(申請者)」「どのような情報を入力し」「誰に提出し(一次承認者)」「誰が最終的に決裁するのか(決裁者)」といった要素を時系列で整理します。この段階では、現場の担当者にヒアリングを行い、実際の業務内容との乖離がないかを確認することが不可欠です。
関係者の特定: 申請者、承認者、決裁者、そして業務内容によって必要となる経理部や情報システム部などの関連部署をすべてリストアップします。それぞれの役割と責任範囲を明確にしておくことで、後の承認ルート設計がスムーズになります。
整理した業務プロセスを基に、誰が見ても理解できるフローチャートを作成し、承認ルートを設計します。
フローチャートの作成: 「開始/終了」「処理」「判断」といった標準的な記号を用いて、業務の流れを図式化します。条件分岐(例:申請金額が10万円以上か否か)がある場合は、それも明確に図に落とし込みます。フローチャートを作成することで、プロセスのボトルネックや非効率な部分を発見しやすくなります。
承認ルートの設計: 特定した関係者を基に、申請から決裁までの承認ルートを設計します。直列承認(課長→部長の順)や並列承認(関係部署が同時に承認)、条件分岐によるルート変更など、業務内容に合った最適なルートを定義します。この際、無駄な承認ステップがないか、役職や権限規程と矛盾しないかを慎重に検討します。
最後に、作成したワークフローを関係者に共有し、フィードバックを求めます。
関係者への共有: 作成したフローチャートや新しい業務ルールを、実際にその業務に携わるすべての関係者に説明します。説明会などを開催し、変更の背景や目的、具体的な操作方法などを丁寧に伝え、理解を促します。
フィードバックの収集と反映: 新しいワークフローが実際の業務内容に即しているか、非効率な点はないかなど、現場の担当者から意見を募ります。机上で設計したフローが、必ずしも現場で最適とは限りません。収集したフィードバックを基にワークフローを修正・改善し、実用性を高めていくことが重要です。
関連記事:差し戻しの原因と対策を徹底解説!業務効率化を進める実践的ステップ
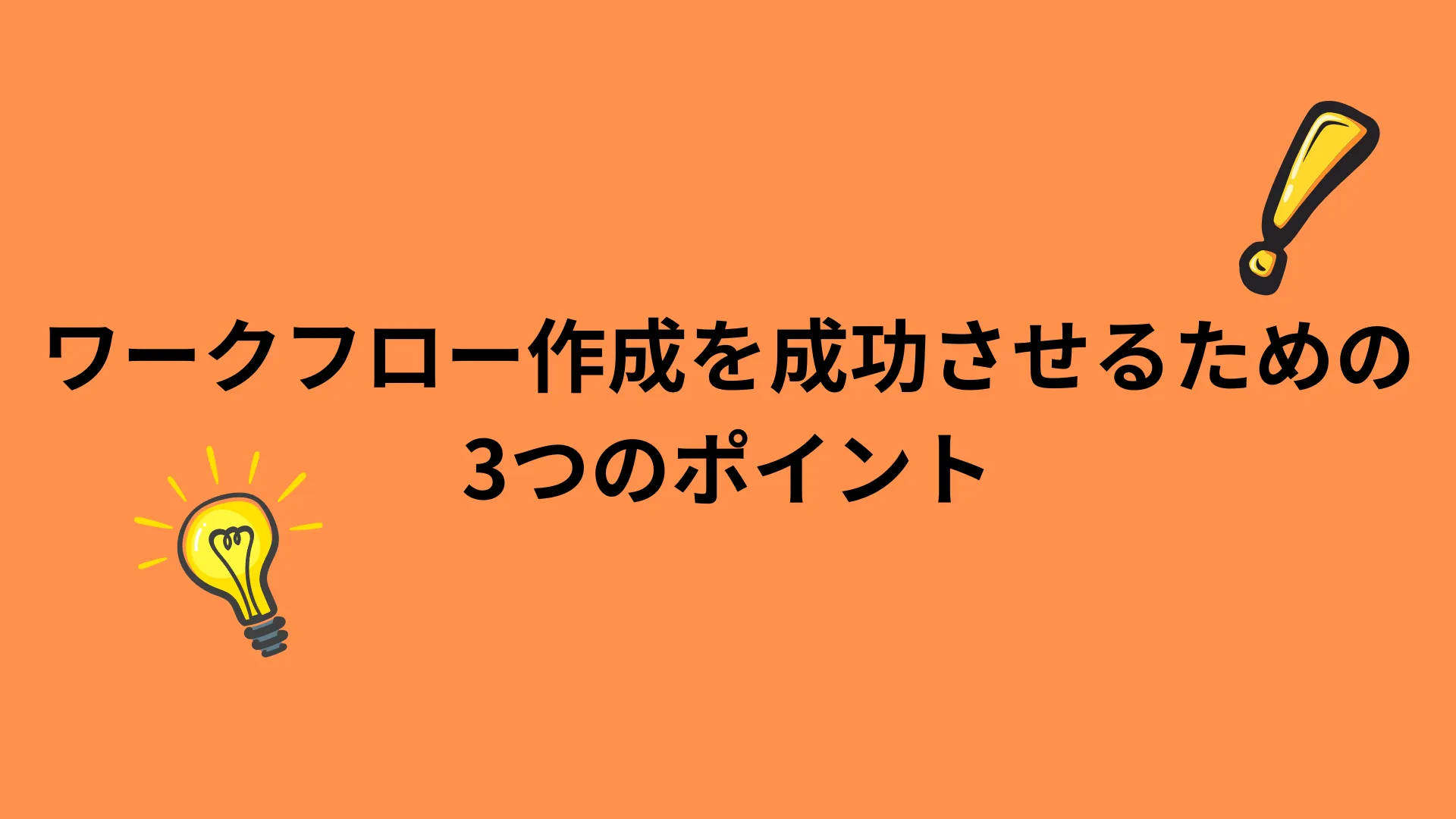
ワークフローは、一度作成して終わりではありません。業務内容の変化に対応し、継続的に改善していくことが重要です。ここでは、作成したワークフローを形骸化させず、効果的に運用していくための3つのコツを紹介します。これらのポイントを意識することで、ワークフロー導入の効果を最大化できるでしょう。
全社的な業務改革を目指す場合でも、最初からすべての業務をワークフロー化しようとすると、現場の混乱を招き、失敗するリスクが高まります。まずは、特定の部署や限定的な業務(例:交通費精算のみ)からスモールスタートし、導入効果を検証することをおすすめします。
小さな成功体験を積み重ねることで、他部署の協力を得やすくなるだけでなく、導入過程で見つかった課題を次の展開に活かすことができます。効果測定を行いながら段階的に対象範囲を拡大していくアプローチが、結果的に確実な全社展開へと繋がります。
ワークフローを設計するのは管理部門やDX推進部門かもしれませんが、実際にそれを利用するのは現場の従業員です。そのため、現場の意見を無視してトップダウンで導入を進めると、「使いにくい」「かえって手間が増えた」といった不満が噴出し、利用されなくなる可能性があります。
設計段階から現場の担当者を巻き込み、ヒアリングを重ねることが重要です。また、導入後も定期的に利用者からフィードバックを収集し、業務内容や組織変更に合わせてワークフローを柔軟に見直す運用体制を整えましょう。
ワークフローは、誰が見ても直感的に理解できるシンプルさが求められます。フローチャートで使用する記号や用語、申請フォームの項目名などを全社で統一し、分かりやすいルールブックを作成しましょう。
例えば、「承認」「決裁」「確認」といった言葉の定義を明確にしたり、フローチャートの書き方を標準化したりすることで、部署ごとの解釈の違いによる混乱を防ぎます。ルールを統一することで、従業員は新しいワークフローにもスムーズに対応できるようになり、組織全体の業務効率が向上します。
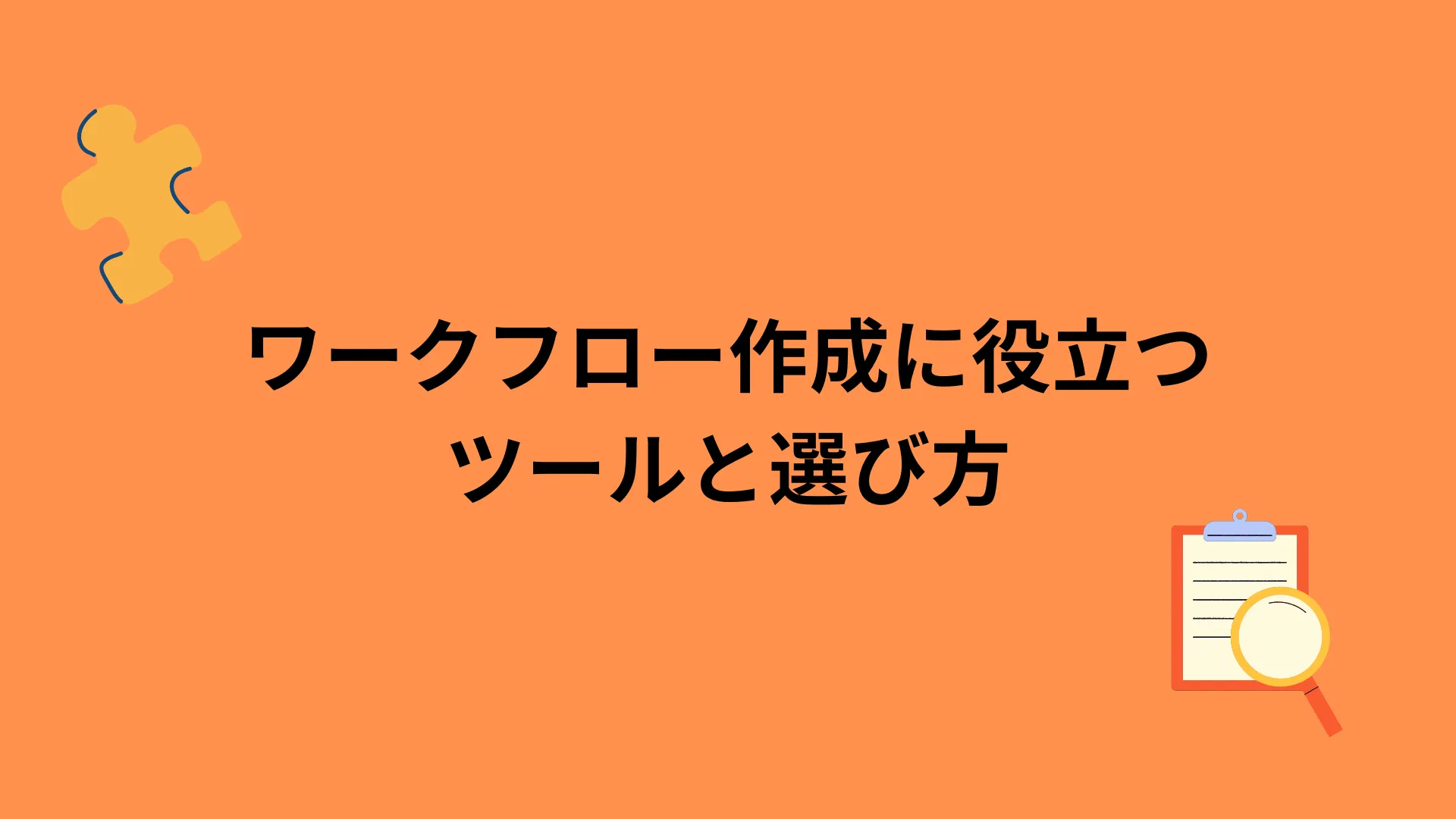
手書きや表計算ソフトでもワークフローを作成することは可能ですが、作成後の運用や管理、業務効率を飛躍的に向上させるためには、専用の「ワークフローシステム」の導入が極めて有効です。ここでは、ツールを導入するメリットや、自社に合ったシステムの選び方について解説します。
ワークフローシステムの導入には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
デメリット
多種多様なワークフローシステムの中から自社に最適なものを選ぶためには、以下のポイントを比較検討することが重要です。
機能の網羅性と拡張性
自社の業務に必要な機能(複雑な承認ルート設定、外部システム連携など)が備わっているかを確認します。将来的な事業拡大や組織変更にも対応できる拡張性があるかも重要な選定基準です。
操作性(UI/UX)
ITに不慣れな従業員でも直感的に操作できるか、デモやトライアルで確認しましょう。使いやすいインターフェースは、社内への浸透をスムーズにします。
提供形態(クラウド型かオンプレミス型か)
サーバー管理が不要で手軽に始められるクラウド型か、自社サーバーで構築し、柔軟なカスタマイズが可能なオンプレミス型か、自社のセキュリティポリシーやIT部門のリソースを考慮して選びます。
サポート体制
導入時の設定支援や、運用開始後の問い合わせ対応など、ベンダーのサポート体制が充実しているかを確認します。
せっかく優れたワークフローを作成し、高機能なシステムを導入しても、従業員に使われなければ意味がありません。導入後に「前のやり方の方が楽だった」という声が上がり、形骸化してしまうケースは少なくありません。そうした事態を防ぎ、新しい業務プロセスを社内にスムーズに定着させるためには、ツールの「使いやすさ」が決定的な鍵を握ります。
従業員が新しいシステムを利用する際、最も大きな障壁となるのが「操作が分からない」というストレスです。マニュアルを読み込まないと使えないような複雑なシステムは、敬遠されがちです。
そのため、ワークフローシステムを選定する際には、機能の豊富さだけでなく、ITリテラシーの高低にかかわらず、誰でも直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI)を備えているかを重視すべきです。シンプルな画面構成、分かりやすいボタン配置など、ユーザー目線で設計されているツールは、教育コストを削減し、導入後の定着率を大きく向上させます。
しかし、どんなに優れたUIのシステムでも、全従業員がすぐに使いこなせるとは限りません。そこで注目されているのが、デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)です。DAPは、既存のシステム上に操作ガイドや入力ルールを直接表示させることで、ユーザーの「分からない」をリアルタイムで解決するツールです。
例えば、ワークフローシステムの申請画面で、「この項目には何を入力すればいいのか?」と迷った際に、システムの画面上にヒントや入力例をポップアップで表示させることができます。これにより、従業員はマニュアルを探したり、問い合わせをしたりすることなく、自己解決しながら作業を進められます。
弊社が提供するDAPツール「Fullstar」は、あらゆるWebシステムに後付けでナビゲーションを追加し、ユーザーが迷わず操作できるよう支援します。ワークフローシステムの導入と合わせて「Fullstar」を活用することで、システムの定着を強力に促進し、導入効果を最大化することが可能です。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行