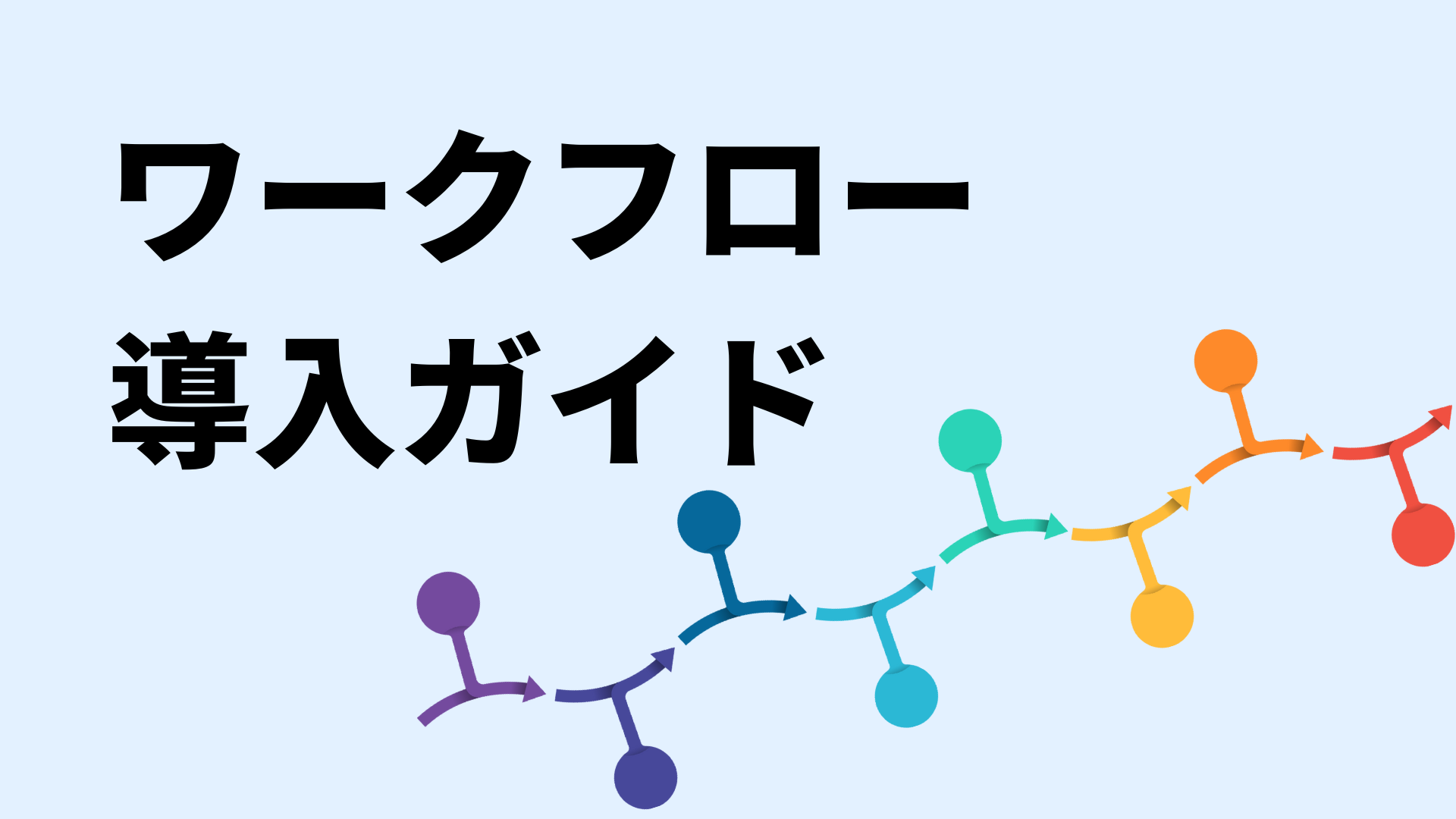

ワークフローの導入とは、企業活動における各種申請・承認・決裁といった一連の手続きを、専用のシステムを用いて電子化・自動化することです。従来、紙やメールで行われていた業務プロセスをデジタル化することで、意思決定の迅速化やペーパーレス化によるコスト削減、内部統制の強化を目指します。しかし、その効果を最大化するには、自社の課題に合ったシステムの選び方や、導入のメリット・注意点を正しく理解することが不可欠です。
本記事では、ワークフロー導入を成功させるための選定ポイントから、具体的な導入手順、そして導入後の定着までを網羅的に解説します。
この記事は、特に以下のような課題やお考えをお持ちの方におすすめです。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
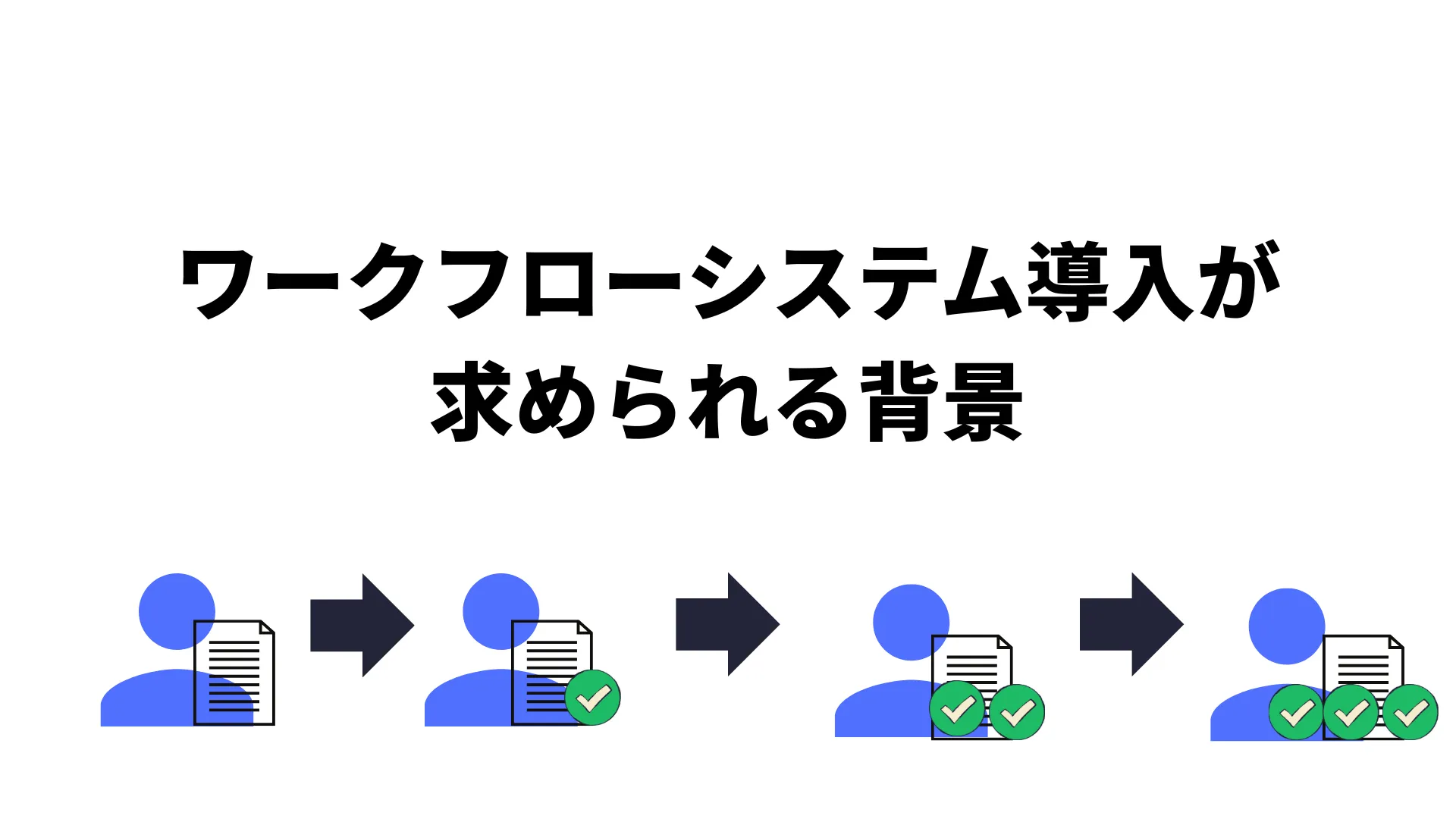
多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が経営課題となる中、なぜ今「ワークフローシステム」の導入が重要視されているのでしょうか。その背景には、従来の紙やメールを主体とした業務プロセスが持つ、構造的な課題が存在します。本セクションでは、具体的な課題を明らかにするとともに、今まさにシステム化が急務とされる理由について解説します。
紙とハンコで行われる従来の申請・承認業務。多くの方が、その非効率さに一度は頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。
例えば、ようやく作り上げた稟議書も、承認者の出張一つでデスクの上に滞留してしまいます。複数の部署を回るうちに、一体今どこで止まっているのか分からなくなり、関係部署への確認に追われることもしばしばです。このように、プロセス全体がブラックボックス化しやすく、本来進むべき業務が「待ち時間」によって停滞してしまうのが、紙ならではの大きな課題と言えるでしょう。
さらに、物理的な書類である以上、紛失や盗難、改ざんといったセキュリティリスクも常に付きまといます。厳密なルールがなければ、本来通すべき承認ルートが飛ばされてしまうといった、内部統制上の問題にも繋がりかねません。加えて、過去の書類を探し出すためにキャビネットの奥から古いファイルを探し出す時間、そして印刷や保管にかかるコストも、日々の業務の中では見過ごされがちですが、企業全体で見れば決して小さくない負担となっているのです。
従来の課題に加え、近年のビジネス環境の変化がワークフローシステムの導入をさらに後押ししています。単なる業務効率化に留まらない、企業経営における重要な一手として位置づけられるようになりました。
働き方の多様化への対応
テレワークやリモートワークは、今や多くの企業で標準的な働き方となりました。しかし、承認のために出社が必要な「ハンコ出社」という言葉が生まれたように、従来のワークフローは場所の制約を受けます。システムを導入し、どこからでも申請・承認ができる環境を整えることは、多様な働き方を支えるための必須条件と言えるでしょう。
全社的なDX推進の加速
ワークフローの電子化は、ペーパーレス化という目に見える効果だけでなく、全社的なDXを推進する上での重要な第一歩です。申請・承認という定型業務をデジタル化することで、従業員のITリテラシー向上に繋がります。また、蓄積された申請・決裁データを分析し、業務プロセスのさらなる改善や経営判断に活用することも可能になります。
関連記事:ワークフロー管理とは?重要性と業務の例、DXを加速させる管理システムの選び方まで解説
内部統制とコンプライアンス強化の要請
企業の社会的責任や透明性が厳しく問われる現代において、内部統制の強化は極めて重要な経営課題です。ワークフローシステムは、あらかじめ設定されたルートに基づき承認プロセスを自動化するため、規程違反や不正のリスクを大幅に低減します。誰が・いつ・何を承認したかの記録が自動的に保存されるため、監査対応の効率化にも大きく貢献します。
労働人口減少と生産性向上への貢献
少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの企業にとって深刻な問題です。限られた人的リソースでこれまで以上の成果を上げるためには、徹底的な生産性向上が求められます。ワークフローシステムによって定型的な申請・承認業務を自動化・効率化することで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。
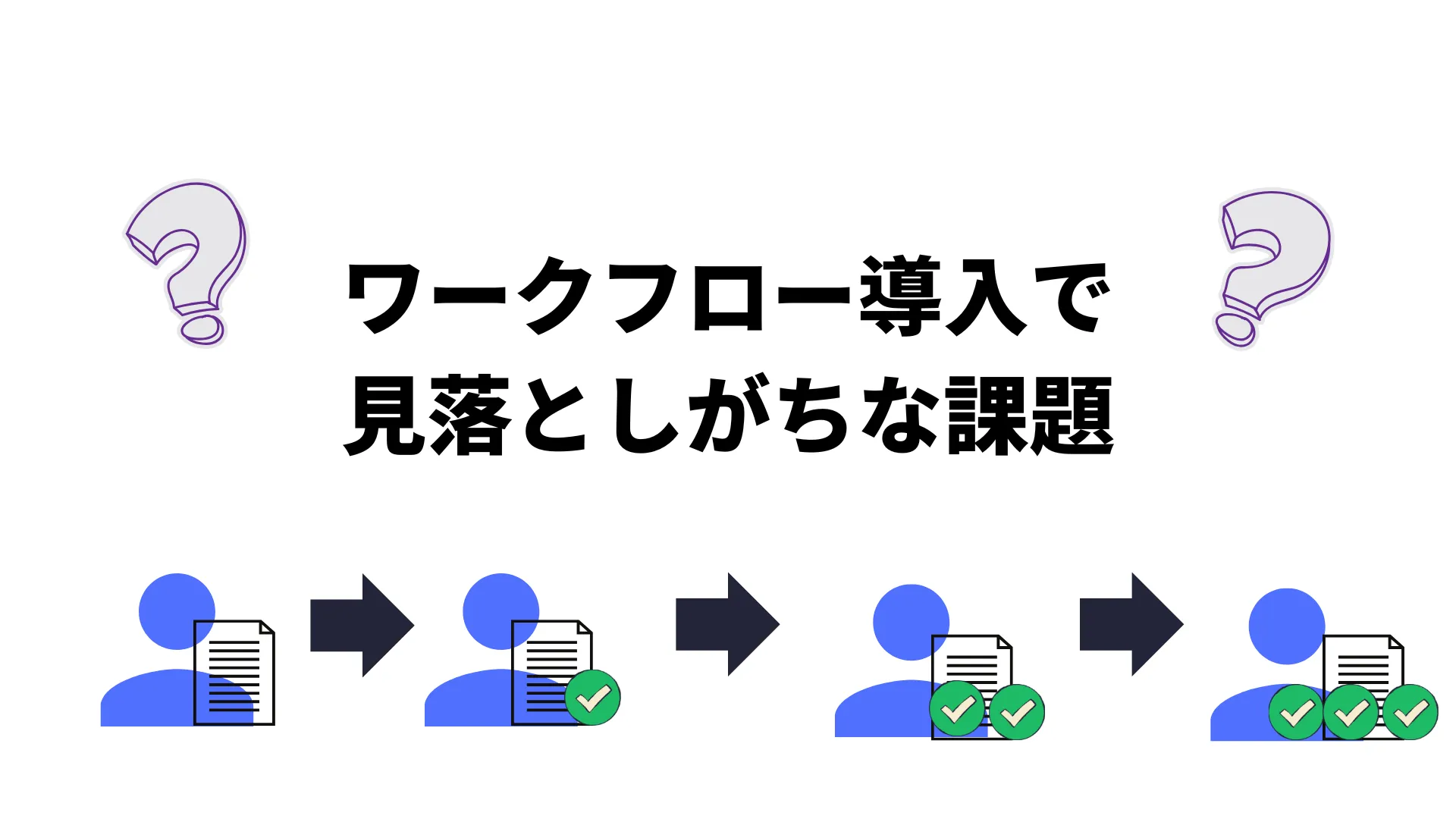
満を持してワークフローシステムを導入したにも関わらず、「以前より手間が増えた」「結局、あまり使われていない」といった声が聞かれることがあります。それは、ツールの機能や価格だけで製品を選んでしまい、多くの企業が見落としがちな、ある共通の課題に直面しているからです。本章では、その課題の本質を深掘りします。
最もよくある失敗は、これまで紙で行っていた申請・承認のプロセスを、そのままシステムに置き換えてしまうことです。例えば、紙の申請書と同じレイアウトの入力フォームを作り、紙で回していた通りの承認ルートをシステム上で再現するだけ、といったケースです。
これでは、単に媒体が「紙」から「画面」に変わっただけで、業務のボトルネックは解消されません。むしろ、これまでになかったシステムへの入力や操作という新たな手間が増え、「かえって面倒になった」と感じさせてしまう危険性さえあります。本質的な課題は、紙やハンコそのものではなく、その背景にある非効率な業務プロセスにあるのです。
さらに深刻なのは、承認プロセスそのものが意味をなさなくなる、という問題です。これは、多くの担当者が実感するところではないでしょうか。
実際の業務では、システムで申請を上げる前に、チャットやメール、あるいは口頭での「根回し」や「事前合意」が済んでいることが少なくありません。その結果、システム上での承認行為は、本来の「内容を精査し、意思決定する」という目的を失い、すでに決まったことに対してボタンを押すだけの「事後報告」や「形式的な作業」となってしまいます。
この二度手間は、従業員のモチベーションを下げ、システムの利用を敬遠させる大きな原因となります。これでは、何のために高いコストをかけてシステムを導入したのか分かりません。
https://x.com/kotakurihara/status/1956136252203557356
こうした課題を避けるためには、システム導入の前に、まず「何のために、誰の承認が必要なのか」という業務プロセスの根本的な目的に立ち返ることが不可欠です。すべての業務に、多段階の承認が本当に必要でしょうか。承認の目的を再定義することで、導入すべきシステムの姿も明確になります。
ガバナンス強化が目的の場合
企業の重要事項(高額な稟議、重要な契約締結など)が対象です。この場合、厳格な承認プロセスは必須であり、誰がいつ承認したかという証跡管理機能や、規程に基づいたルートの自動設定機能などが重要になります。
情報共有や記録保全が目的の場合
例えば、日常的な経費精算や備品購入申請などが挙げられます。この場合、本来の目的は「不正なく処理し、記録を残す」ことです。であれば、承認プロセスは大幅に簡略化するか、あるいは不要かもしれません。申請内容の自動チェック機能や、関係者への自動通知機能、後から検索しやすい記録・保管機能などが充実していることが重要になります。
このように、承認の目的を明確にすることで、不要なプロセスを削ぎ落とし、本当に価値のある業務改革へと繋げることができるのです。
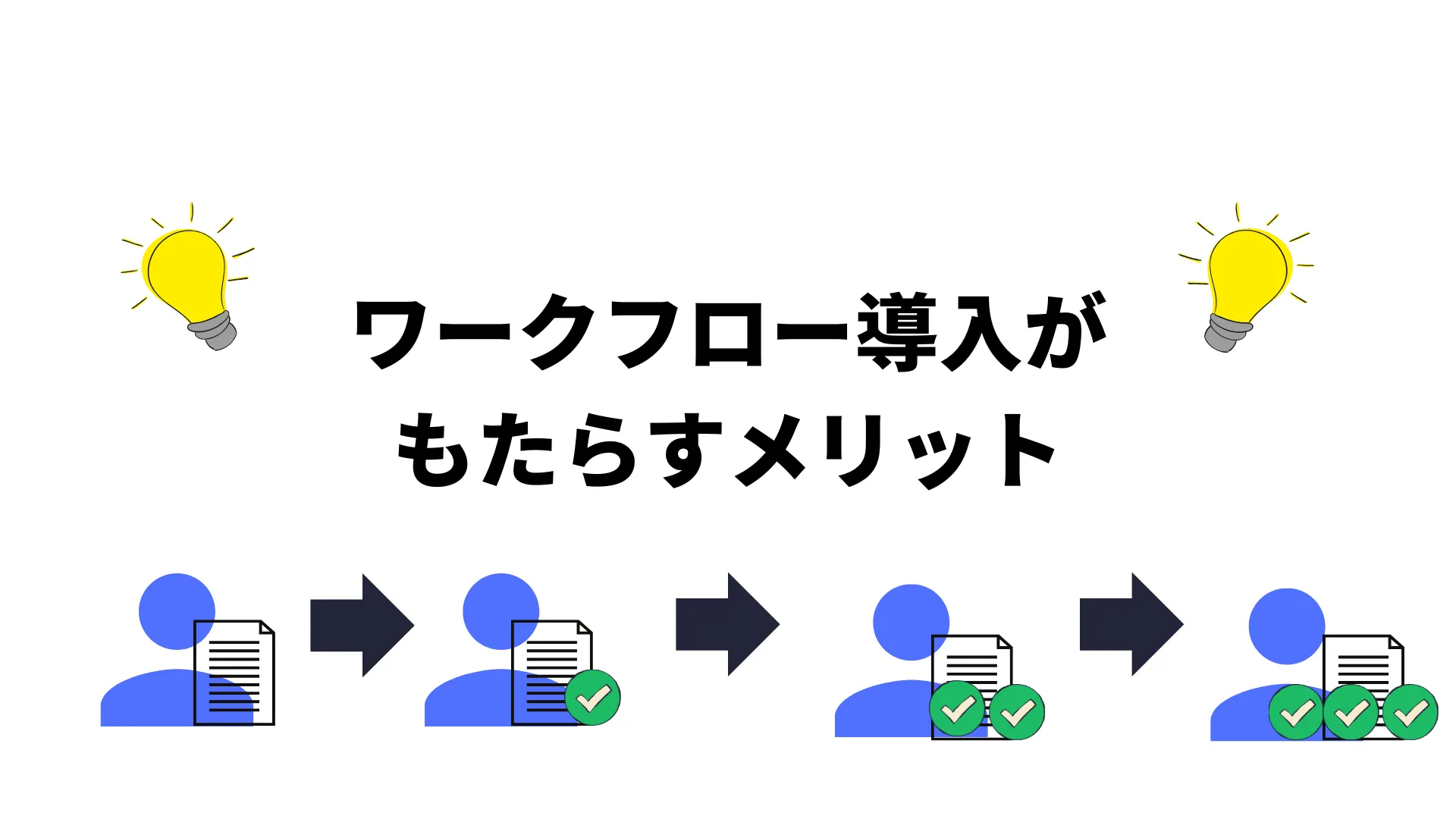
前章で触れた課題は、目的を明確にし、適切なプロセス見直しを行うことで乗り越えられます。ここでは、ワークフローシステムを正しく導入・活用することで企業が享受できる、具体的なメリットを5つ紹介します。
メリット1:意思決定の迅速化
申請から承認までのプロセスがオンラインで完結するため、物理的な書類の移動時間がゼロになります。承認者は場所を問わずスマートフォンなどから承認でき、進捗状況もリアルタイムで可視化されるため、プロセス全体のスピードが飛躍的に向上します。
メリット2:業務プロセスの可視化と標準化
これまで属人的になりがちだった申請・承認ルートがシステム上で明確に定義されるため、誰でも同じプロセスで業務を進められるようになります。業務が標準化されることで、担当者の異動や退職時の引き継ぎもスムーズになります。
メリット3:内部統制とセキュリティの強化
役職や規程に応じた承認ルートをシステムで制御することで、不正な承認やプロセスの逸脱を防ぎます。また、誰が・いつ・何を承認したかという操作ログ(監査証跡)が自動で記録されるため、コンプライアンス強化や監査対応の効率化に繋がります。
メリット4:多様な働き方への対応
時間や場所を問わずに申請・承認業務が行える環境は、テレワークや時差出勤といった柔軟な働き方を強力にサポートします。育児や介護といった事情を抱える従業員も働きやすくなり、人材の定着や多様性の確保に貢献します。
メリット5:ペーパーレス化によるコスト削減
紙での運用が不要になることで、用紙代、印刷代、郵送費、書類の保管スペースといった物理的なコストを大幅に削減できます。また、書類の検索や管理にかかっていた人件費という見えにくいコストの削減効果も期待できます。
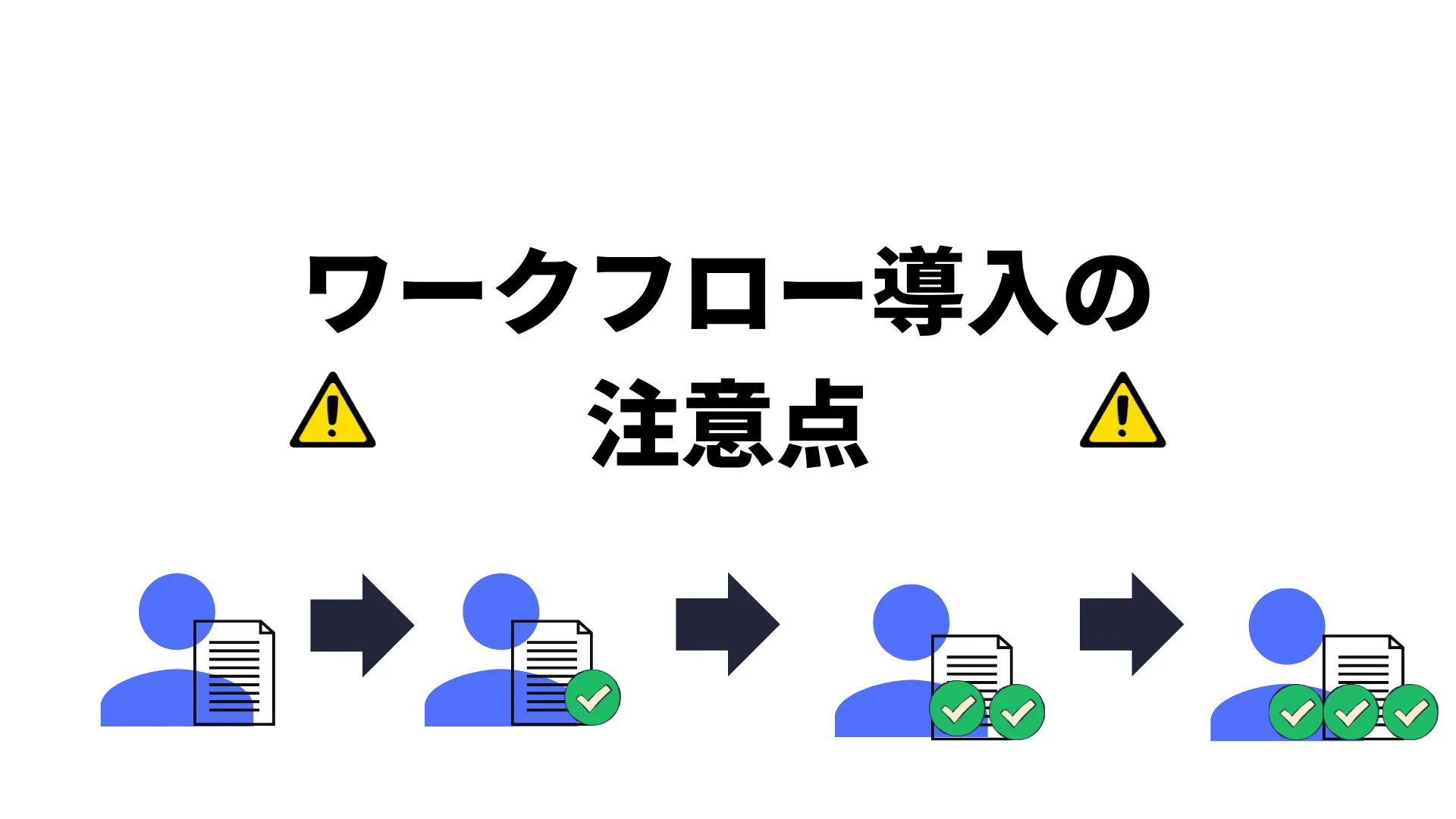
メリットを最大化するためには、導入に伴う課題や注意点を事前に理解し、対策を講じることが重要です。ここでは、特に確認しておくべき3つの注意点を解説します。
注意点1:導入・運用コストの発生
システムの導入には、初期費用や月額利用料といったコストが発生します。多機能なシステムほど高額になる傾向があるため、自社の課題解決に必要な機能を見極め、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
対策: スモールスタートを検討する、複数社の料金体系を比較する、クラウド型のサービスを選び初期費用を抑える、といった方法が考えられます。
注意点2:業務プロセスの見直し
前章で述べた通り、既存の業務プロセスをそのままシステム化するだけでは、十分な効果は得られません。導入を機に、不要な承認ステップはないか、より効率的なルートはないか、といった業務プロセスの見直しが不可欠です。これには相応の労力がかかります。
対策: 導入プロジェクトに各部署の業務を熟知したメンバーを加え、全部署を巻き込みながら見直しを進めることが成功の鍵です。
注意点3:従業員への定着
新しいシステムの導入は、従業員にとって一時的な負担増や操作への戸惑いを生む可能性があります。十分な説明やトレーニングがないと、システムが使われなくなり、結局は以前のやり方に戻ってしまうという失敗に繋がりかねません。
対策: 操作が直感的なシステムを選ぶ、導入目的やメリットを丁寧に説明する、分かりやすいマニュアルや研修会を用意する、といった丁寧なフォローが求められます。
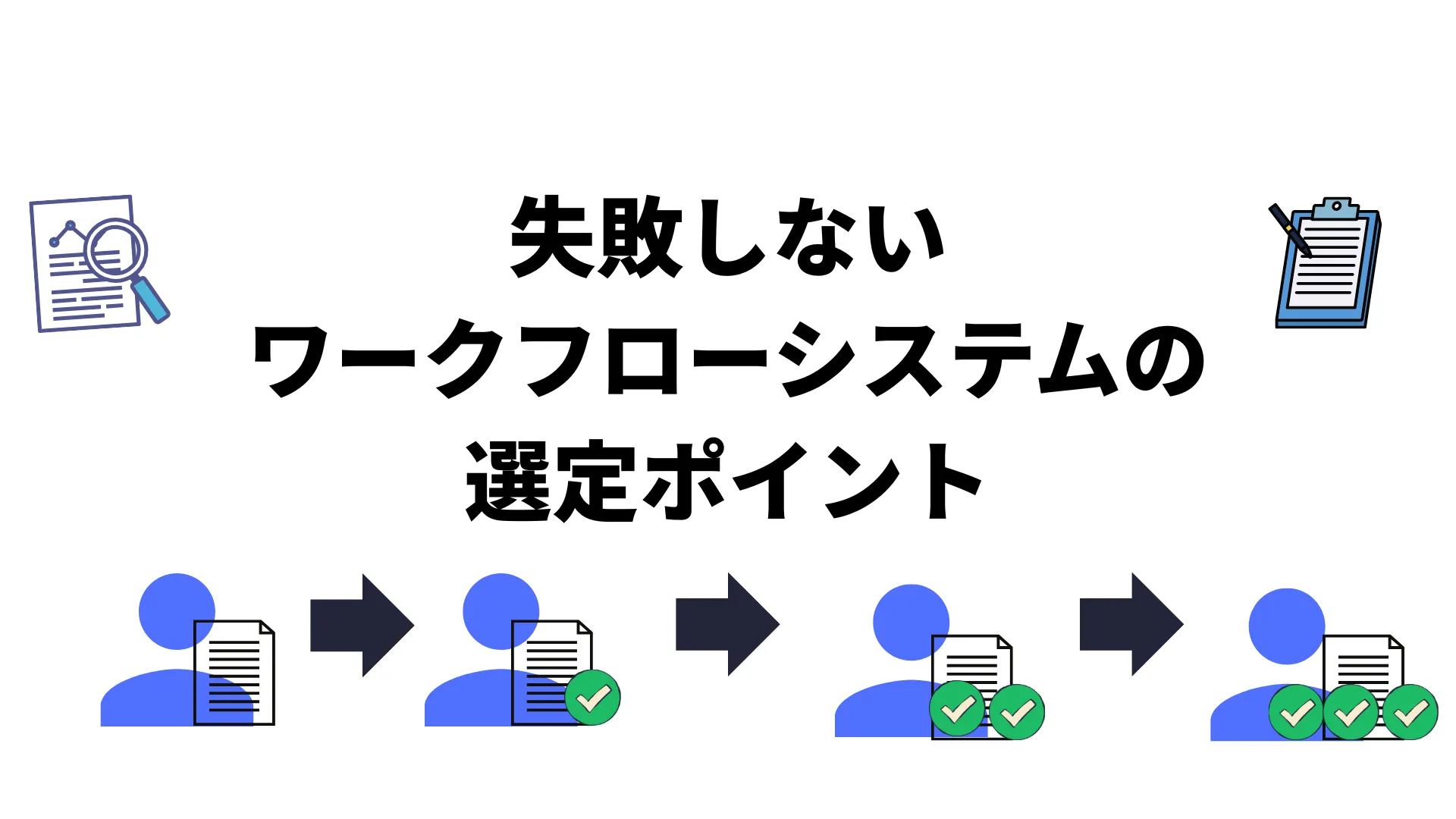
自社に合ったシステムを選定する上で、失敗を避けるために確認すべき重要なポイントを解説します。多機能さや価格だけで判断するのではなく、自社の目的や業務に合っているかという視点で、以下の8つのポイントを確認しましょう。
Point 1. 承認すべき業務範囲を明確にする
最も重要な最初のステップは、システムで扱う業務範囲、つまり「何を承認の対象とするか」を明確にすることです。前述の通り、ガバナンス強化が目的なのか、情報共有が目的なのかによって、必要な機能は全く異なります。まずは目的を定め、それに合致した業務範囲に絞ってシステム化を検討することが、成功への最短距離です。
Point 2. 複雑な承認フローにも対応できるか
企業の承認プロセスは、単純な直線型のものばかりではありません。「申請金額によって承認者が変わる」「特定の品目であれば経理部を経由する」といった条件分岐や、複数の承認者が同時に承認する並列承認など、複雑なフローが求められることも多々あります。自社の承認フローを洗い出し、システムが柔軟に対応できるかを確認しましょう。
Point 3. 既存システムとの連携性を評価する
ワークフローシステムは、単体で完結するよりも、他のシステムと連携することでさらに価値が高まります。例えば、会計システムと連携して経費精算の仕訳を自動化したり、人事システムと連携して異動時の承認ルートを自動更新したりすることが考えられます。API連携やCSV連携など、どのような連携方法が可能かを確認しましょう。
Point 4. 高度なセキュリティと権限管理機能を求める
申請・承認データには、企業の機密情報や個人情報が含まれることもあります。そのため、堅牢なセキュリティは必須要件です。通信の暗号化、IPアドレス制限、二要素認証といったセキュリティ機能に加え、役職や所属部署に応じてアクセスできる情報や操作できる機能を細かく制御できる、柔軟な権限管理機能があるかを確認しましょう。
Point 5. 全従業員が直感的に使える操作性か見極める
ワークフローシステムは、一部の専門家だけでなく、全従業員が利用するツールです。ITリテラシーに関わらず、誰でもマニュアルを見なくても直感的に操作できるシンプルなインターフェースであることが、利用定着の鍵を握ります。無料トライアルなどを活用し、複数の部署の従業員に実際に触ってもらい、操作性を評価することをおすすめします。
Point 6. 自社に合う提供形態(クラウドかオンプレミスか)を選択する
ワークフローシステムには、主にクラウド型とオンプレミス型の2つの提供形態があります。
現在では、多くの企業で導入のしやすさからクラウド型が主流となっています。
Point 7. 組織の成長や変化に対応できるか
企業は常に成長し、変化します。組織改編や人事異動が頻繁に発生しても、承認ルートの変更やユーザー情報の更新が簡単に行えるかは重要なポイントです。また、将来的にシステム化したい業務が増えた際に対応できる拡張性があるかどうかも、長期的な視点で確認しておきましょう。
Point 8. 導入から定着までのサポート体制を重視する
システムの導入時だけでなく、運用を開始してから発生する疑問やトラブルに対応してくれるサポート体制も重要です。電話やメールでの問い合わせ窓口の有無、対応時間、FAQサイトの充実度などを確認しましょう。特に、導入後の利用定着を支援してくれる専任の担当者がつくようなサービスは、心強いパートナーとなります。
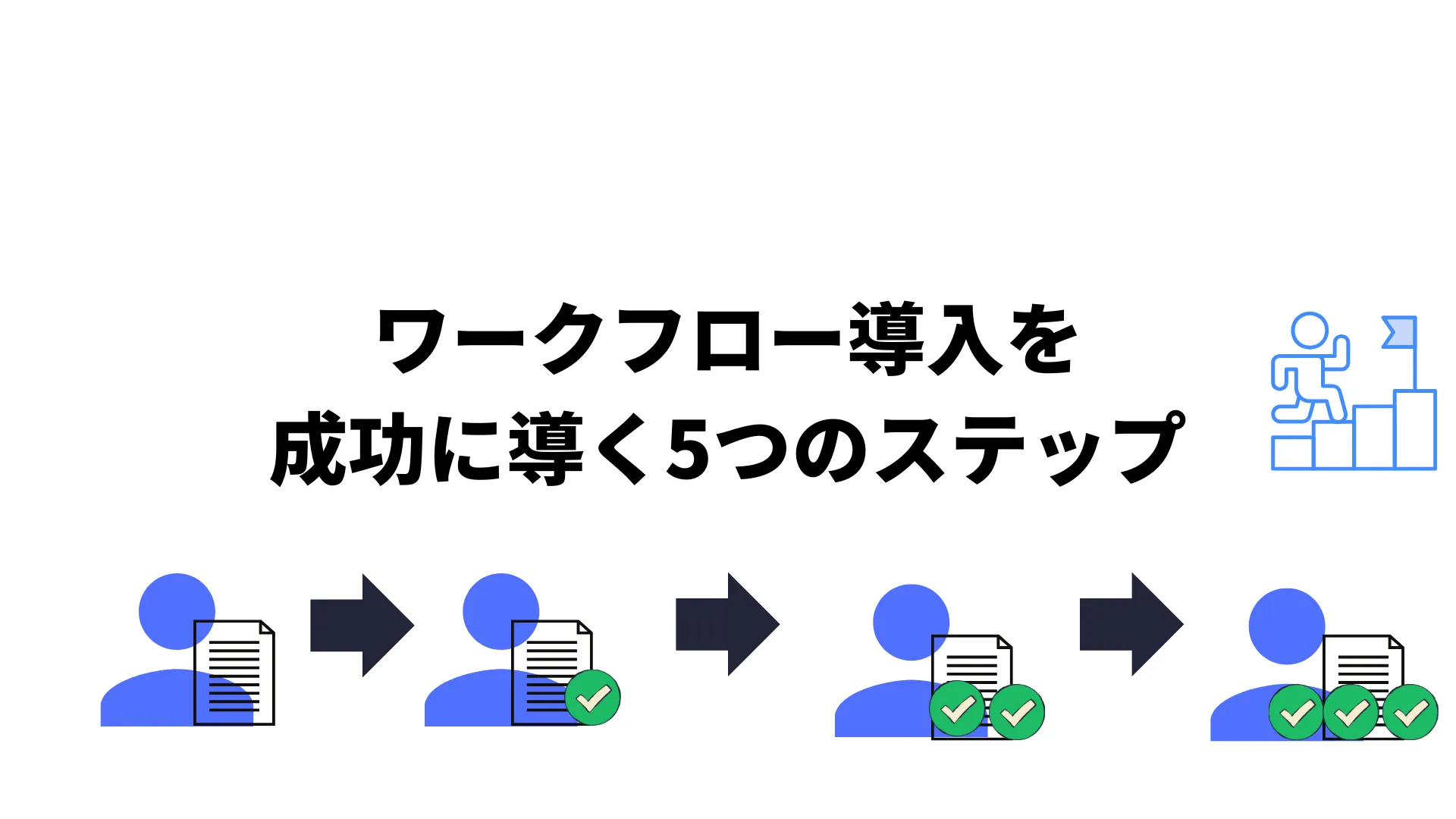
適切なシステムを選定できたら、次はいよいよ導入プロジェクトを進めていきます。ここでは、導入を成功させるための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。
関連記事:システム導入の進め方完全マニュアル|失敗しないためのポイント
Step 1. 現状の業務フローと「承認の目的」を明らかにする
まず、対象とする業務の現状を徹底的に可視化します。誰が、どのような手順で、どれくらいの時間をかけて申請・承認を行っているのかを洗い出します。そして最も重要なのが、その承認が「何のために」行われているのか、その目的を関係者全員で再確認・定義することです。
Step 2. 導入目的と新しい業務プロセスを決める
Step 1で見えた課題と目的を基に、「システム導入によって何を実現したいのか」というゴールを具体的に設定します(例:「稟議の承認時間を平均3日から1日に短縮する」など)。そして、そのゴールを達成するための新しい業務プロセスを設計します。この段階で、不要な承認ステップの廃止やルートの簡略化を大胆に行うことが重要です。
Step 3. 複数のシステムを比較し、実際に試してみる
Step 2で定めた要件を基に、複数のシステムをピックアップし、前の章で解説した選定ポイントに沿って比較検討します。資料やWebサイトの情報だけでなく、必ず無料トライアルやデモンストレーションを依頼し、実際の操作性を確認しましょう。現場の担当者にも試してもらい、フィードバックを得ることが、導入後のミスマッチを防ぎます。
Step 4. 導入チームを作り、社内に知らせる
システム導入を推進する専任のチームを編成します。情報システム部門だけでなく、実際にシステムを利用する業務部門のメンバーにも参加してもらうことが不可欠です。また、導入の目的やスケジュール、従業員にとってのメリットなどを、経営層から全社に向けて発信し、協力体制を築きます。
Step 5. 段階的に導入し、利用状況を見ながら改善する
最初から全社・全部署で一斉に導入するのではなく、特定の部署や業務に絞って試験的に導入する「スモールスタート」が有効です。まずは小さな成功体験を作り、そこで得られた課題や改善点を反映させながら、徐々に対象範囲を拡大していきます。導入後も、定期的に利用状況を分析し、より使いやすい設定や運用ルールへと改善を続けることが定着の鍵です。
こうした改善のサイクルを回し続けることは、システムの定着だけでなく、従業員が日々の業務で感じる小さなストレスを解消していくことにも繋がります。「この申請、もう少し入力項目が少なければ楽なのに」「このルート、いつもここで止まるな」といった現場の声を吸い上げ、設定に反映させていくことで、システムはより業務にフィットし、誰もが気持ちよく使えるツールへと進化していくのです。
素晴らしいシステムを導入し、業務プロセスも見直した。しかし、最後の壁として「従業員がシステムをなかなか使いこなしてくれない」という問題が立ちはだかります。この「定着化」の課題を解決するソリューションとして、今注目されているのが「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」です。
多くの企業では、新システムの導入後に研修会を実施したり、分厚いマニュアルを配布したりしますが、それだけでは不十分な場合が少なくありません。いざ使おうとした時に操作方法が分からず、結局、情報システム部門への問い合わせが殺到したり、詳しい同僚に聞いたりすることで、業務が非効率になるケースが見られます。これが、システムの利用が定着しない大きな原因です。
デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは、さまざまなWebシステムやアプリケーションの利用定着を支援するためのツールです。(より詳しくは、デジタルアダプションとは?の記事もご覧ください)。既存のシステムに後から追加する形で導入でき、ユーザーが操作に迷わないように支援する機能を画面上に表示させます。
当社の提供するDAP「Fullstar(フルスタ)」は、導入したワークフローシステムの上に、操作ガイドや入力ルールをリアルタイムで表示させることができます。
これにより、従業員はマニュアルを読んだり誰かに質問したりすることなく、自己解決しながらシステムを使いこなせるようになります。結果として、問い合わせ対応の工数を削減し、システム導入の効果を最大化することができるのです。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行