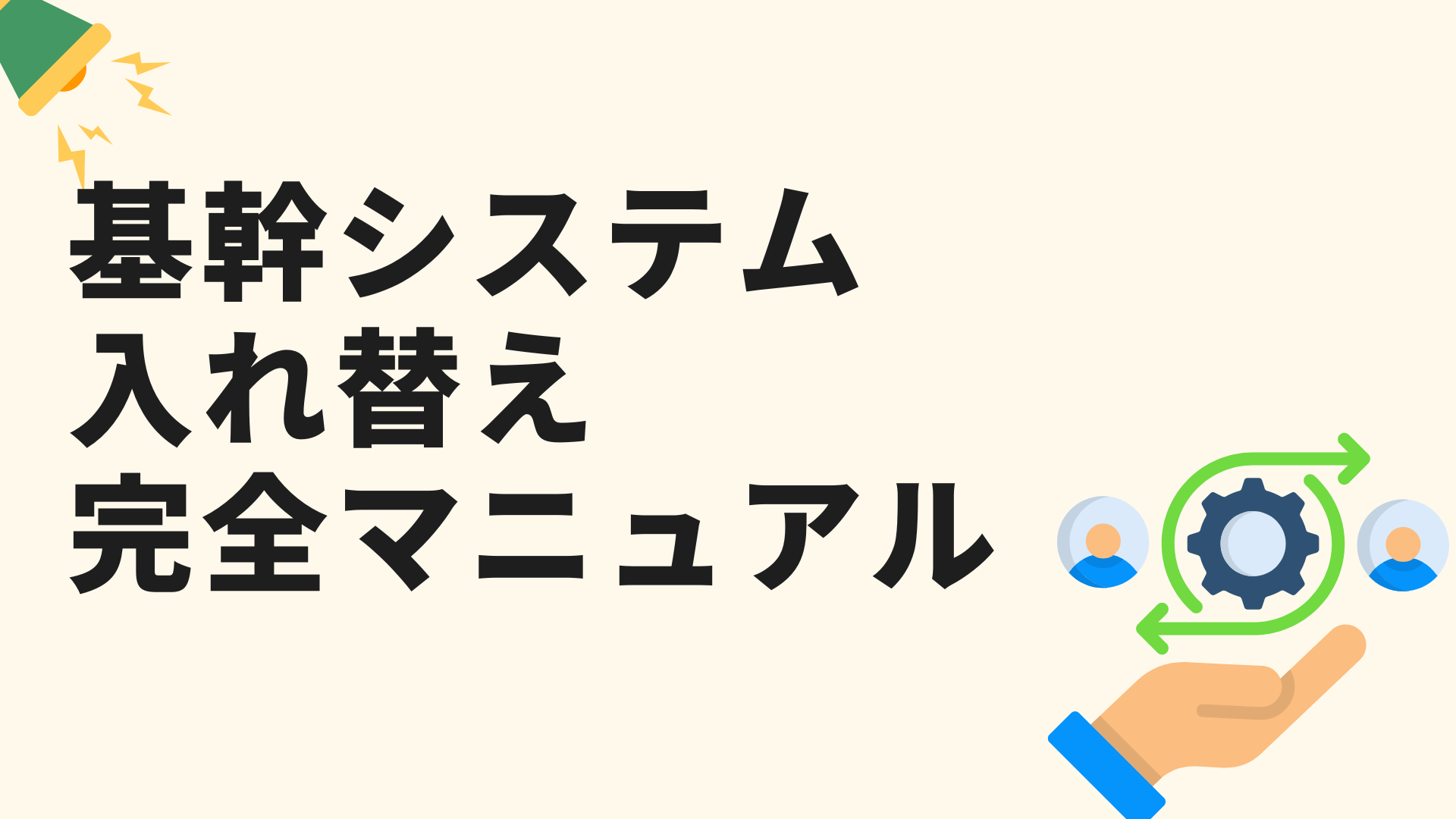

企業の心臓部ともいえる基幹システムは、販売・会計・人事などあらゆる業務を支える存在です。しかし、導入から時間が経過するにつれて老朽化やサポート切れが進み、現場業務との乖離やセキュリティリスクが顕在化してきます。その解決策となるのが「基幹システムの入れ替え」です。とはいえ、システム入れ替えは投資規模も大きく、進め方を誤ると業務停止や現場の混乱を招きかねません。本記事では、基幹システム入れ替えのメリットから注意点、さらに定着化までを徹底的に解説し、成功に導くためのポイントをまとめました。
関連記事:基幹システムとERPの違いとは?導入のポイントと選び方を徹底解説
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
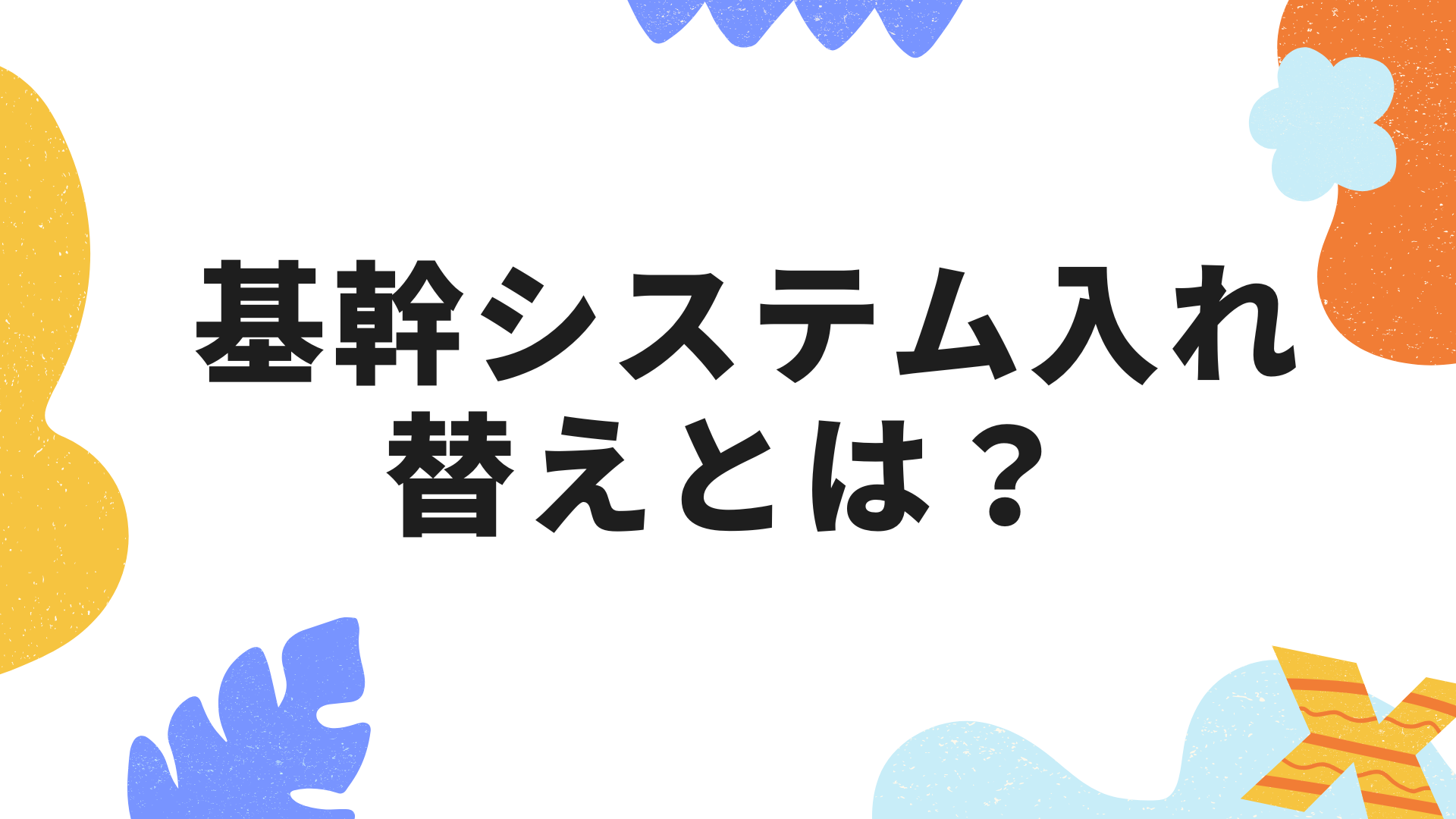
基幹システムの入れ替えとは、長年利用してきた会計、人事、販売、生産管理などの中核業務を支えるシステムを、新しいソフトウェアやインフラに置き換えることを指します。単なるプログラム更新に留まらず、サーバ・ネットワークなどのハードウェア刷新、業務フローや運用ルールの見直しも含まれる大規模な取り組みです。近年では、クラウド化やERP統合、データ分析基盤の強化、セキュリティレベルの向上などを目的とするケースが増加しています。現行システムが古く、他システム連携やモバイル対応が難しい状況では、市場の変化に追随できず競争力低下の原因になります。入れ替えは単なる延命措置ではなく、DX推進と企業価値向上のための重要な経営判断といえます。
関連記事:基幹システムとは?役割・種類などをわかりやすく解説
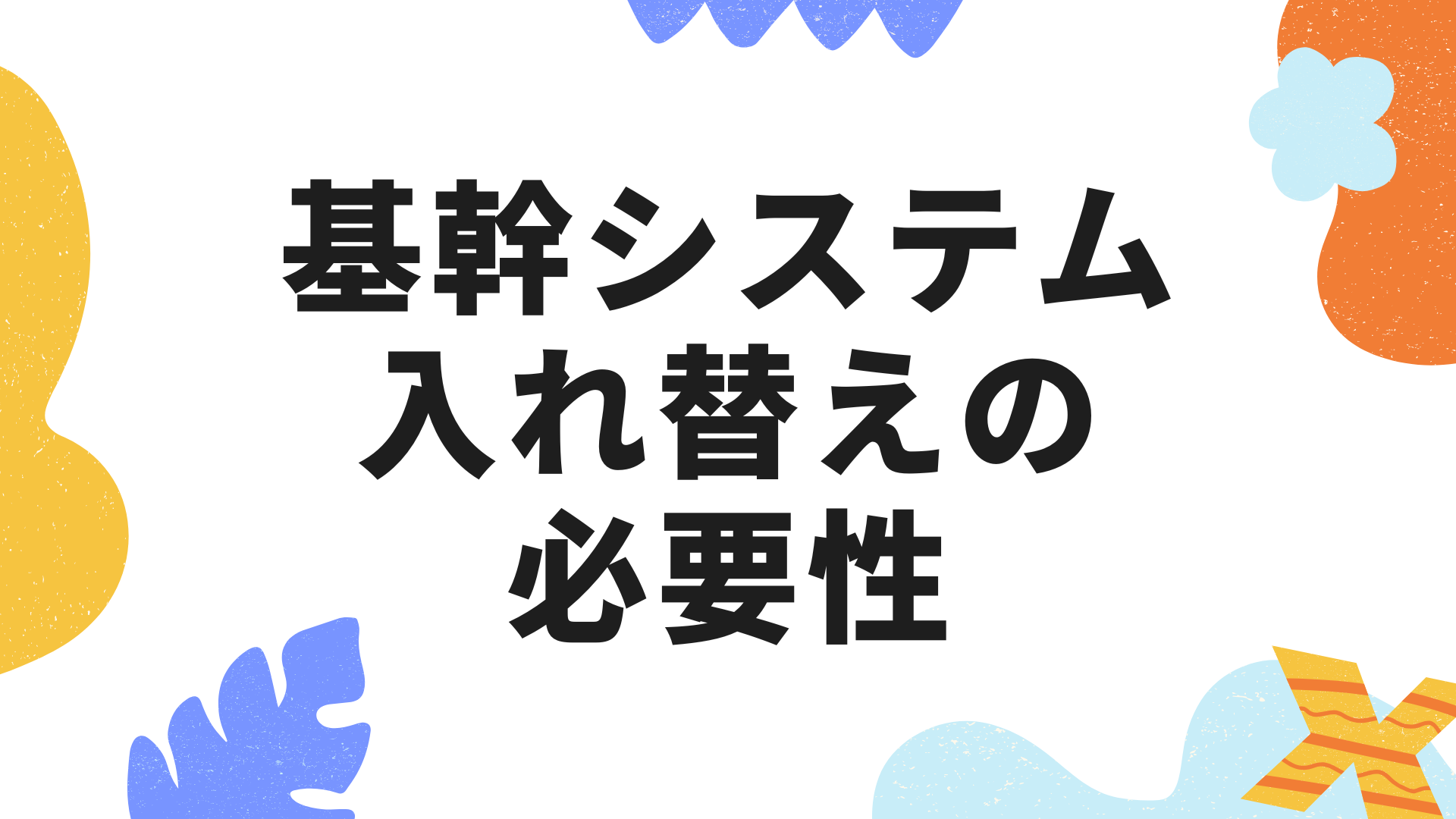
システムは稼働年数が長くなるほど、ハードウェアの故障リスクやパフォーマンス低下が顕著になります。また、古いソフトウェアは最新OSやブラウザへの対応が難しく、互換性トラブルが頻発します。その結果、日常業務に支障をきたし、メンテナンスのための人的・金銭的コストが増加します。これらの状態を放置すると、突発的な障害や長時間の業務停止といった重大なリスクにつながります。
ソフトウェアやミドルウェア、ハードウェアにはサポート期限があります。期限を過ぎると、セキュリティパッチの提供が止まり、技術的な不具合にも対応できなくなります。この状態で運用を続けることは、情報漏洩やシステム停止といった深刻なトラブルの温床となります。特に金融や製造などセキュリティ要件の厳しい業界では、サポート切れは直ちに入れ替えを検討すべき重要なサインです。
企業が成長し事業領域を拡大すると、業務プロセスは必然的に複雑化します。しかし、旧来のシステムは柔軟性が低く、新しい業務フローや取引形態に対応できない場合があります。結果として、手作業や二重入力が増え、業務効率が低下します。この状況を是正しない限り、生産性向上やDX推進は難しくなります。
現代の企業活動では、他システムとのデータ連携やリアルタイム分析が当たり前になっています。しかし、オンプレミス中心の古い基幹システムでは、クラウドサービスとの連携やAPI活用が困難で、ビジネススピードに遅れが生じます。これにより、競合に対する優位性を失いかねません。
旧システムは最新の暗号化技術や多要素認証などのセキュリティ対策が不十分であることが多く、サイバー攻撃の標的になりやすい傾向があります。特にランサムウェアやゼロデイ攻撃に対しては脆弱で、被害を受けた場合の損失は莫大です。
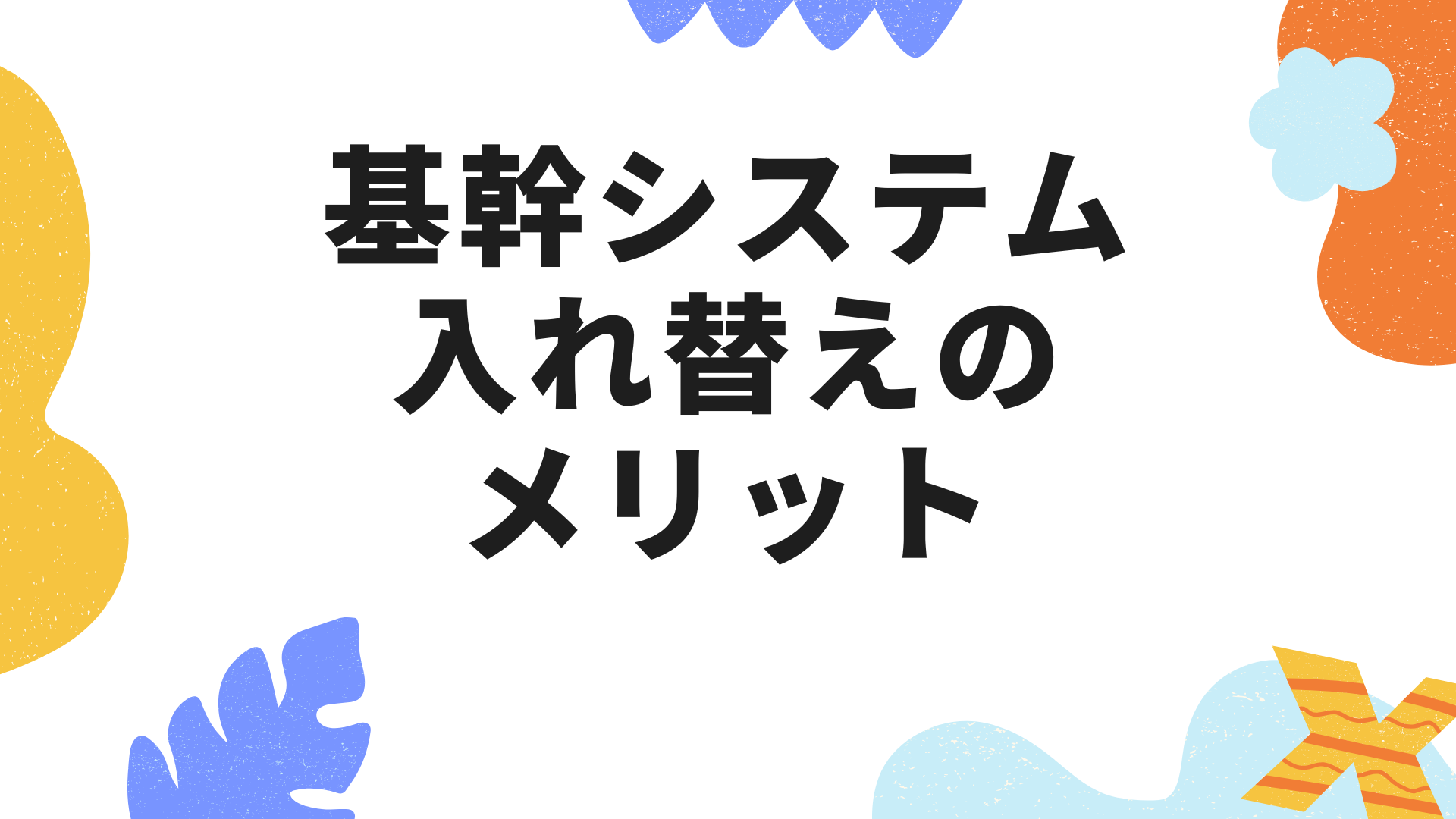
最新の基幹システムは、入力作業や承認プロセスを自動化し、人的ミスや作業時間を大幅に削減できます。たとえば請求書発行や在庫管理など、従来は複数のシステムや紙ベースで行っていた業務を一元管理できるため、二重入力や情報の不整合がなくなります。これにより、現場担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。
新しい基幹システムはリアルタイムでデータを集約・分析できるため、経営層やマネージャーは即座に現状を把握し、根拠ある意思決定が可能になります。BIツールやダッシュボード機能と連携すれば、販売状況、在庫水準、利益率などを瞬時に可視化できます。これにより、従来は月単位だった集計や分析を日単位、場合によってはリアルタイムで行えるようになり、機会損失の防止や戦略のスピーディな修正が可能です。
最新のシステムは、多要素認証や暗号化通信、アクセス権限の細分化など、セキュリティ面で大幅な強化が施されています。これにより、情報漏洩や不正アクセスのリスクを軽減できます。また、個人情報保護法や業界固有の規制に合わせた監査ログや証跡管理も容易になり、コンプライアンス面の安心感も高まります。
クラウド型の基幹システムに移行すれば、社内ネットワークに依存せず、場所やデバイスを問わず安全にアクセスできます。これにより、在宅勤務や海外拠点からの利用、モバイル端末による業務遂行がスムーズになり、業務のスピードと柔軟性が向上します。また、災害や障害時にもクラウドの冗長化機能を活用して事業継続性(BCP)を確保できます。
旧システムは保守要員やパーツの確保が難しくなる一方で、最新システムは自動アップデートやクラウドベースの運用により、保守負担を軽減できます。さらに、API連携やモジュール追加によって、将来の事業拡大や新サービス展開にも柔軟に対応できる拡張性があります。これにより、中長期的な投資効果を最大化できます。
まず、現在稼働している基幹システムの利用状況や課題を可視化します。システム処理の遅延や入力作業の煩雑さ、データの分断、セキュリティリスクなど、現場で発生している問題を明確にすることが重要です。この段階では、経営層だけでなく現場担当者からのヒアリングやアンケートを実施し、実務上の不便さや改善要望を収集します。こうした情報は後の要件定義や機能選定に直結するため、最初の分析が不十分だと後工程で大きな手戻りが発生するリスクがあります。
次に、新システムに求める理想の状態を描きます。単なる機能置き換えではなく、業務プロセスそのものを見直す視点が重要です。たとえば、紙ベースの承認フローを電子化する、在庫管理と販売管理を統合するなど、業務全体の最適化を目指します。このフェーズでは、業務効率化やコスト削減だけでなく、将来の事業戦略や働き方改革、法規制への適応も視野に入れた要件を検討します。
クラウド型かオンプレミス型か、またはハイブリッド型かを決定します。クラウドは初期投資を抑えられ、柔軟性や拡張性に優れますが、カスタマイズ性やセキュリティ要件によってはオンプレミスが有利な場合もあります。方式が決まったら、複数のベンダーから提案を受け、価格だけでなく提案内容やサポート体制、将来的なアップデート方針まで総合的に比較検討します。
基幹システム入れ替えでは、データ移行が最大のハードルの一つです。既存データのクリーニング(重複・不整合の解消)、フォーマット変換、移行手順の検証などを事前に行い、移行後にデータ欠落や整合性問題が発生しないようにします。また、切替のタイミングを繁忙期と重ならないよう調整し、必要に応じて段階的な移行(モジュールごとの移行や並行稼働)を計画します。
新システムを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。操作説明会やマニュアル整備に加え、最近ではデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を活用して、画面上でリアルタイムに操作をガイドする取り組みが増えています。これにより、利用者は迷わず業務を進められ、早期定着が可能になります。定着フェーズでは運用状況のモニタリングや改善提案も重要です。
関連記事:デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは?dap導入のメリットや機能を紹介!
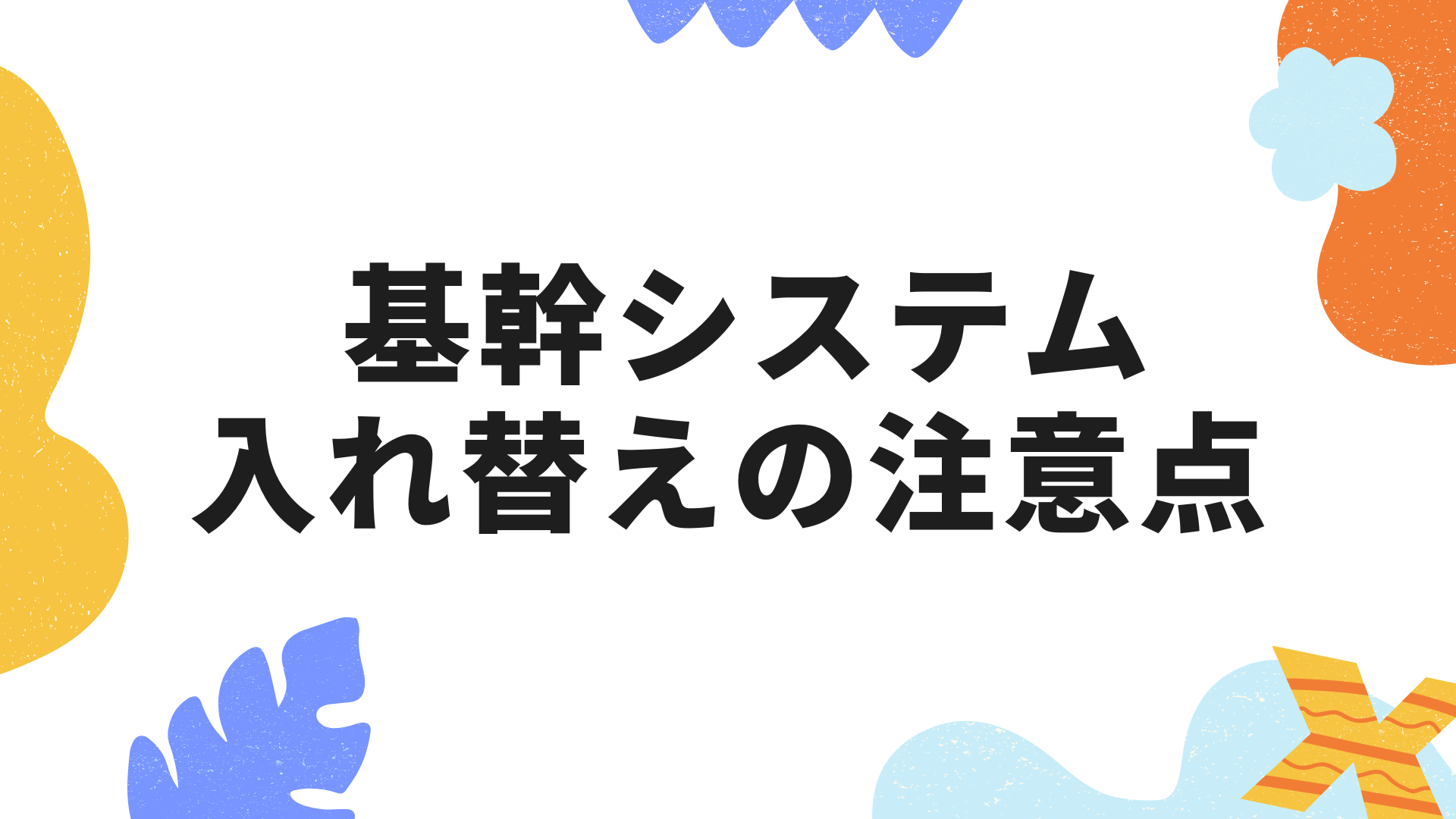
基幹システムの入れ替えで最も多い失敗の一つが、要件定義の不足です。現行業務の分析や改善ポイントが不十分なまま導入を進めると、新システムで必要な機能が不足し、業務がかえって非効率になることがあります。これを防ぐためには、現場担当者の意見を反映しながら、優先度をつけた要件一覧を作成することが欠かせません。また、機能面だけでなく、運用ルールや承認フローといった業務プロセスの整合性も事前に確認する必要があります。
データ移行は単なるコピー作業ではなく、品質管理や整合性チェックが重要です。古いシステムでは長年の運用で不整合や重複データが蓄積している場合が多く、それらを整理しないまま移行すると、新システムで不具合やエラーが発生する原因になります。移行前にはデータのクリーニングを行い、テスト環境での移行検証を繰り返すことで、本番移行のリスクを最小限に抑えることが可能です。
新しいシステムへの切り替えは、多くの従業員にとって大きな負担です。周知や教育が不十分だと、現場からの抵抗感や利用率の低下につながり、定着が進まないことがあります。特に長年同じシステムを使ってきた組織では、操作習慣や業務フローが固まっているため、変化への心理的ハードルが高くなります。この課題を解消するには、導入前から説明会や操作体験会を実施し、従業員が新システムに触れる機会を増やすことが効果的です。
システム切り替え直後は、操作ミスや設定トラブルが頻発するものです。にもかかわらず、ベンダーや社内のサポート体制が整っていない場合、現場の混乱が長期化します。導入後数カ月は、問い合わせ対応や追加研修を迅速に行える仕組みを確保しておくことが重要です。また、サポートを効率化する手段として、デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)の導入も有効で、画面上のガイドやチュートリアルによって現場の自走を促せます。
基幹システムの入れ替えは、計画・実行・移行の各フェーズで慎重な対応が求められますが、真の成功は「現場で確実に使われ続けること」です。導入直後に操作の戸惑いや業務停滞が起きれば、せっかくの投資も効果を発揮できません。そこで有効なのが、デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「Fullstar」です。操作中の画面に直接ガイドやチュートリアルを表示し、利用者が迷わず業務を遂行できる環境を整えます。結果として、教育コストを抑えながら短期間での定着化を実現し、入れ替えによる業務改善効果を最大限引き出すことが可能になります。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行