

「障害対応に追われて、改善に手が回らない」
「管理ツールがバラバラで、状況把握に時間がかかる」
毎日のシステム運用業務、こんな悩みはありませんか?
こうした小さな“非効率”は積み重なると、業務スピードの低下だけでなく、障害時の対応遅れやコスト増にも直結します。さらに近年は、クラウドやリモート環境の普及で管理対象は広がり、従来の運用体制では限界を感じる企業も少なくありません。
この記事では、「運用」と「保守」の違いを整理しながら、現場で実践できる効率化のステップを解説します。IT資産の一元管理から自動化、アウトソーシングの活用まで、明日から取り入れられるヒントを具体的にご紹介します。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
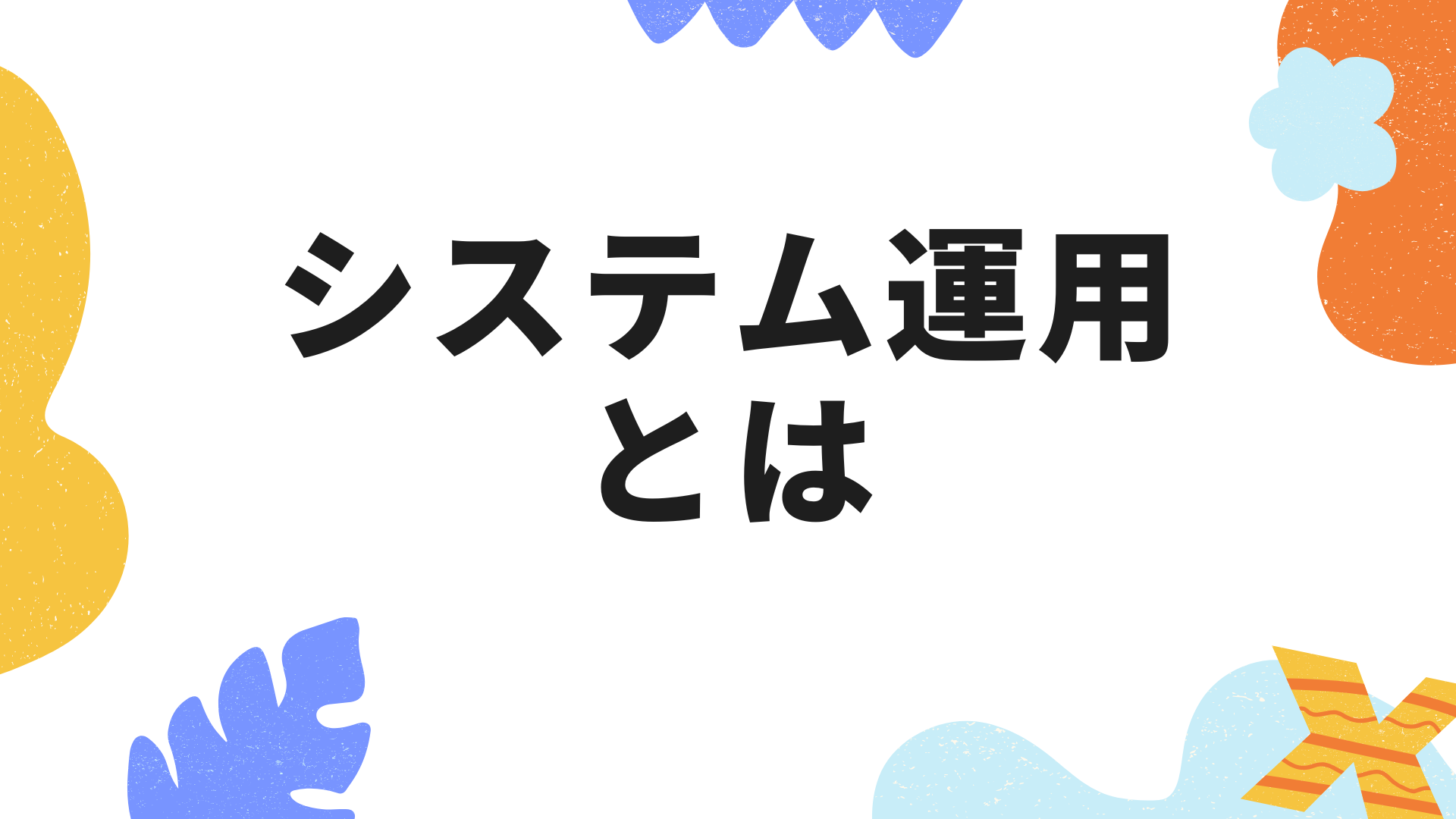
システム運用とは、企業や組織が利用しているITシステムを、安定的かつ安全に稼働させるための継続的な活動のことです。
サーバやネットワーク、アプリケーション、クラウドサービスなど、システム全体を対象に、日々の監視や管理、トラブル対応を行います。
主な業務内容には以下が含まれます。
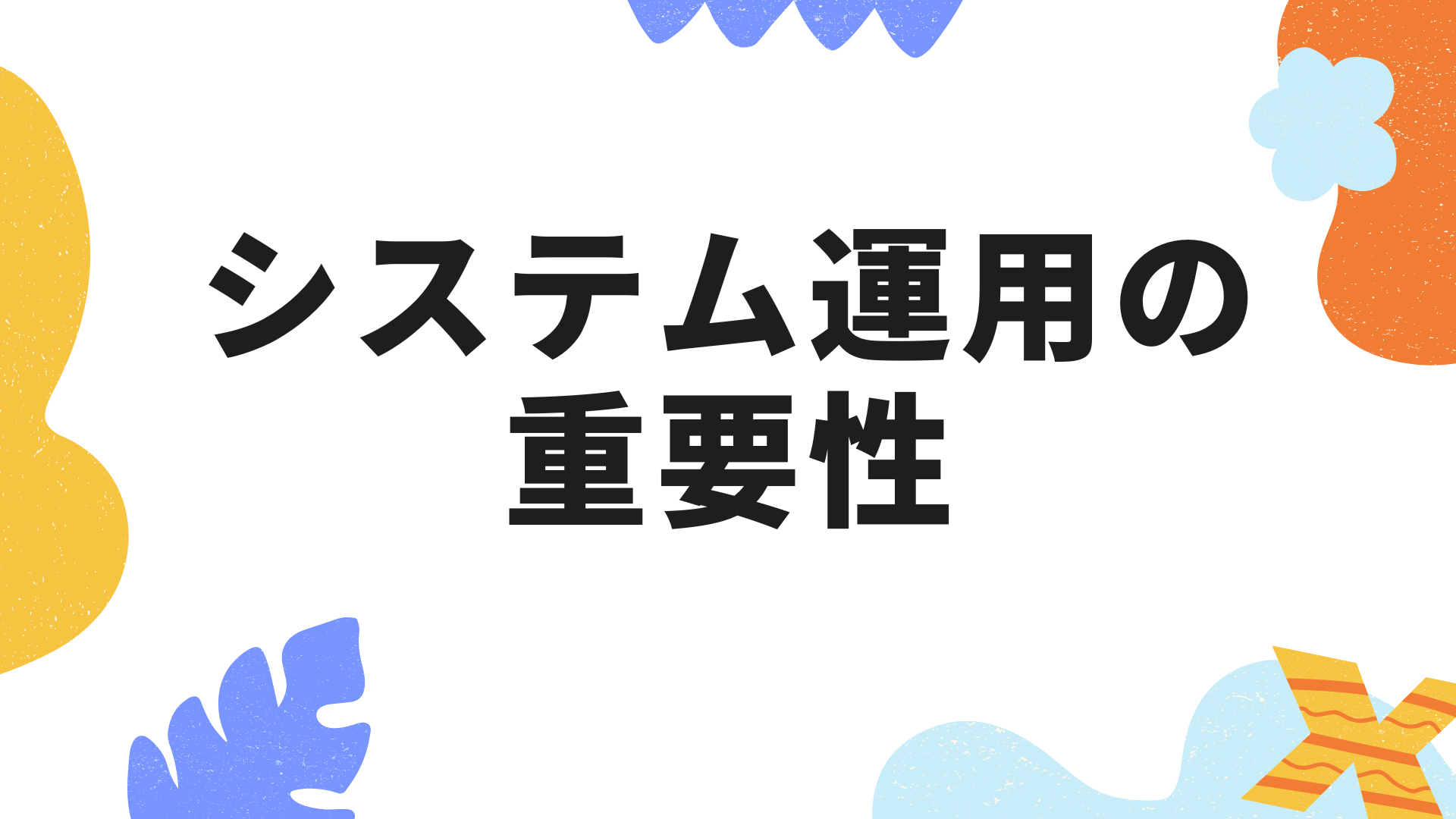
システム運用が適切に行われていないと、業務停止や情報漏えい、顧客へのサービス提供中断といった重大なリスクが発生します。
特に近年は、クラウドやリモートワークの普及により、管理対象は社内ネットワークだけでなく外部サービスにも広がり、運用業務の重要性はさらに増しています。
システム運用とは、企業や組織のITシステムを安定的かつ安全に稼働させるために、日々継続して行われる管理・監視・調整の活動を指します。対象はサーバやネットワーク機器、アプリケーション、クラウドサービスなど多岐にわたり、業務内容は非常に広範です。例えば、システムの稼働状況を常時監視し、異常があれば迅速に原因を特定し対処すること。ユーザーアカウントの登録や権限設定を正確に行い、不正アクセスや操作ミスを防ぐこと。さらには、万が一の障害や災害に備えてデータや設定のバックアップを定期的に取得することも欠かせません。
これらの作業は一見地味ですが、企業活動の根幹を支える極めて重要な役割を担っています。もし運用が滞れば、業務停止や顧客へのサービス提供中断、さらには情報漏えいなどの重大なリスクが発生します。特に現在のようにIT環境が複雑化している状況では、運用業務の正確さと効率性が企業競争力を左右するといっても過言ではありません。
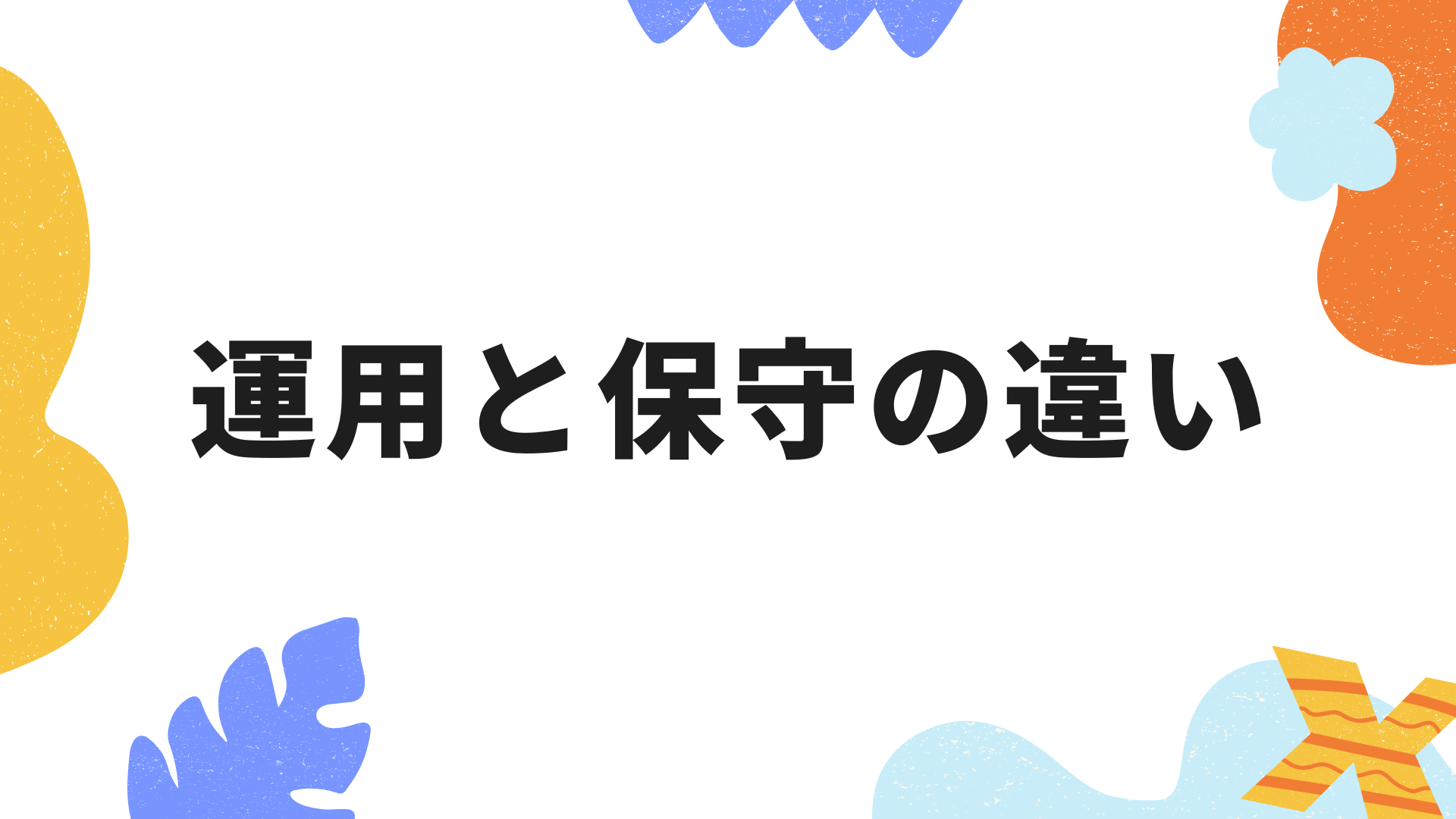
「運用」と「保守」という言葉は混同されがちですが、その役割は異なります。運用は日々の監視や管理、障害発生時の一次対応といった、システムを稼働させ続けるための継続的な業務を意味します。一方、保守はハードウェアの部品交換やソフトウェアのバージョンアップ、不具合修正といった、システムの性能維持や改善のための作業を指します。
たとえば、サーバの状態を常にチェックして異常がないか確認するのは運用ですが、部品が故障して交換する作業は保守にあたります。このように役割分担を明確にすることで、トラブル対応の責任範囲が整理され、効率的かつ迅速な対応が可能になります。
効率化の第一歩は、自社の運用業務のどこに非効率が潜んでいるかを明確にすることです。障害対応の遅延、監視作業の属人化、ツールの乱立など、現状を細かく洗い出すことで改善の方向性が見えてきます。
サーバやネットワーク機器、クラウドサービスなどの資産情報が部門ごとに分散していると、障害発生時に迅速な対応ができません。統合管理ツールを用いてIT資産を一元化することで、情報の検索や更新が容易になり、運用負荷を大幅に削減できます。
定期的なログ収集やバックアップ作業、アカウント管理などは自動化の対象に適しています。スクリプトやRPA、クラウドベースの自動化機能を活用すれば、人為的なミスの防止と作業時間の短縮が同時に実現します。
属人化を防ぐには、運用マニュアルや手順書、障害対応記録を共有し、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できる体制を作ることが重要です。情報共有の仕組みが整っていれば、新任担当者の教育コストも下がります。
自社での対応が難しい領域や、夜間・休日の監視などは専門業者へのアウトソーシングも有効です。外部リソースを適切に活用することで、限られた人員をより戦略的な業務に振り向けられます。
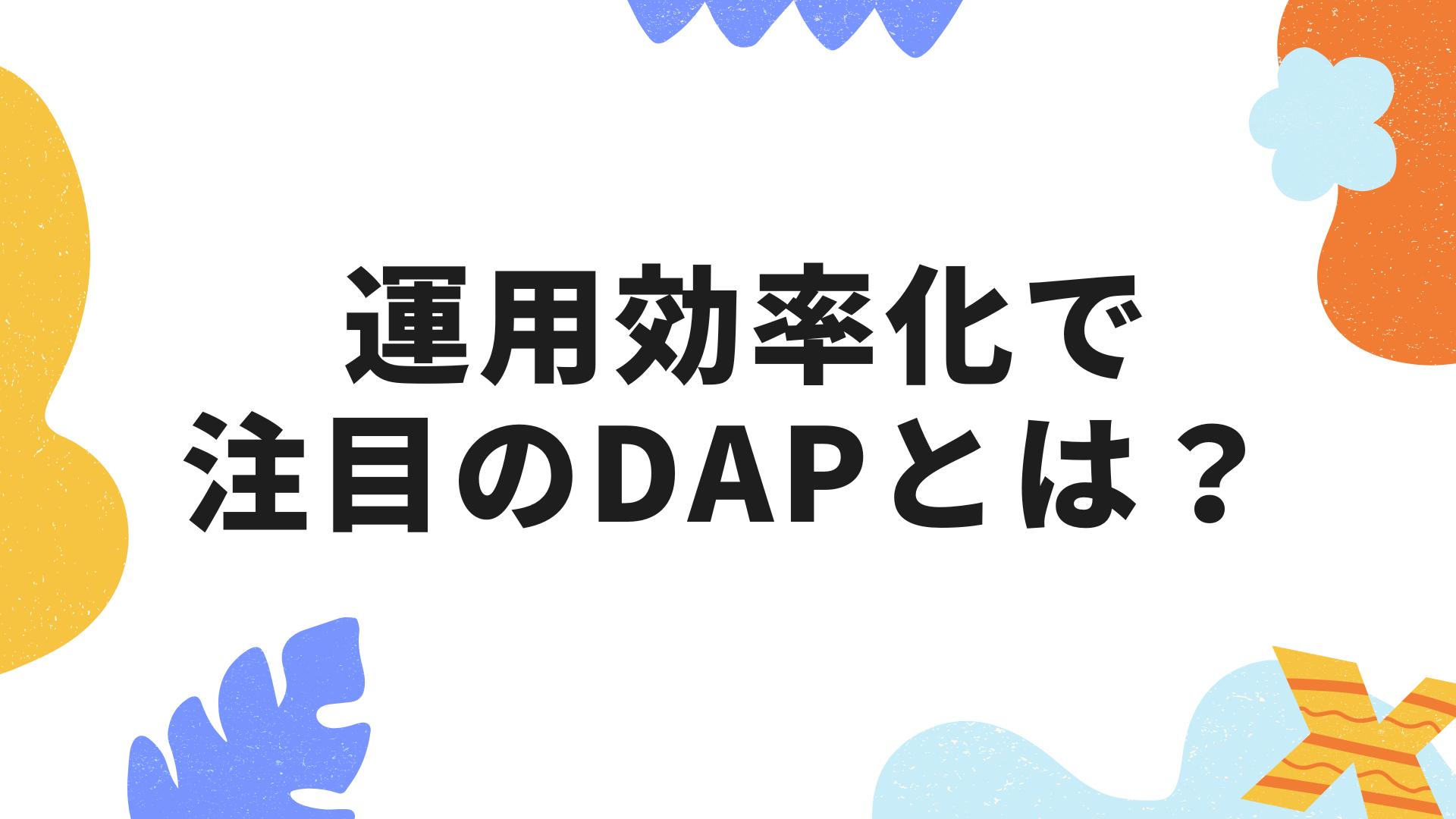
システム運用の効率化は、もはや一部のIT部門だけの課題ではなく、企業全体の業務品質やスピードを左右する経営テーマです。特に監視や管理、障害対応などの現場業務は属人化しやすく、ツールの使い方やシステムの操作手順が担当者ごとに異なる状況では、どれだけ優れた仕組みを導入しても本来の効果を発揮できません。
こうした課題を解消する手段のひとつが、デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)の活用です。DAPは、利用者がシステムやツールを迷わず使いこなせるよう、画面上で操作ガイドや手順を提示し、必要な情報を必要なタイミングで届けます。これにより、新任担当者でも短期間で業務に慣れ、作業品質を均一化できます。また、頻繁に更新されるクラウドサービスや業務アプリの新機能も、現場に負担をかけずに展開できるため、継続的な効率化が可能です。
複雑化するIT環境で安定稼働と迅速な対応を両立させるには、単なるツール導入や作業自動化だけでなく、現場の“使いこなし”を支える仕組みが不可欠です。システム運用の効率化を次のステージへ進めるためにも、DAPの導入を検討することは、非常に有効な一手となるでしょう。
参考:デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とは?dap導入のメリットや機能を紹介!
Fullstarは、システム運用における課題を解消するために設計されたデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)です。
利用者がシステムや業務ツールを操作する際、画面上にわかりやすいガイドや操作手順を表示し、迷いなく作業を進められるよう支援します。これにより、新任スタッフでも短期間で業務に適応でき、作業品質を均一化できます。また、システムやクラウドアプリの更新時も、マニュアル改訂や大規模研修を必要とせず、現場にスムーズに新機能を浸透させられます。
さらに、Fullstarは利用状況のデータを可視化し、どの機能が活用されているか、どこでつまずきが発生しているかを把握できます。この分析結果をもとに、教育や運用フローを改善し、業務全体の効率を継続的に高めることが可能です。
安定稼働と迅速な対応、そして現場の生産性向上を同時に実現したい企業にとって、Fullstarは有力な選択肢となるでしょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行