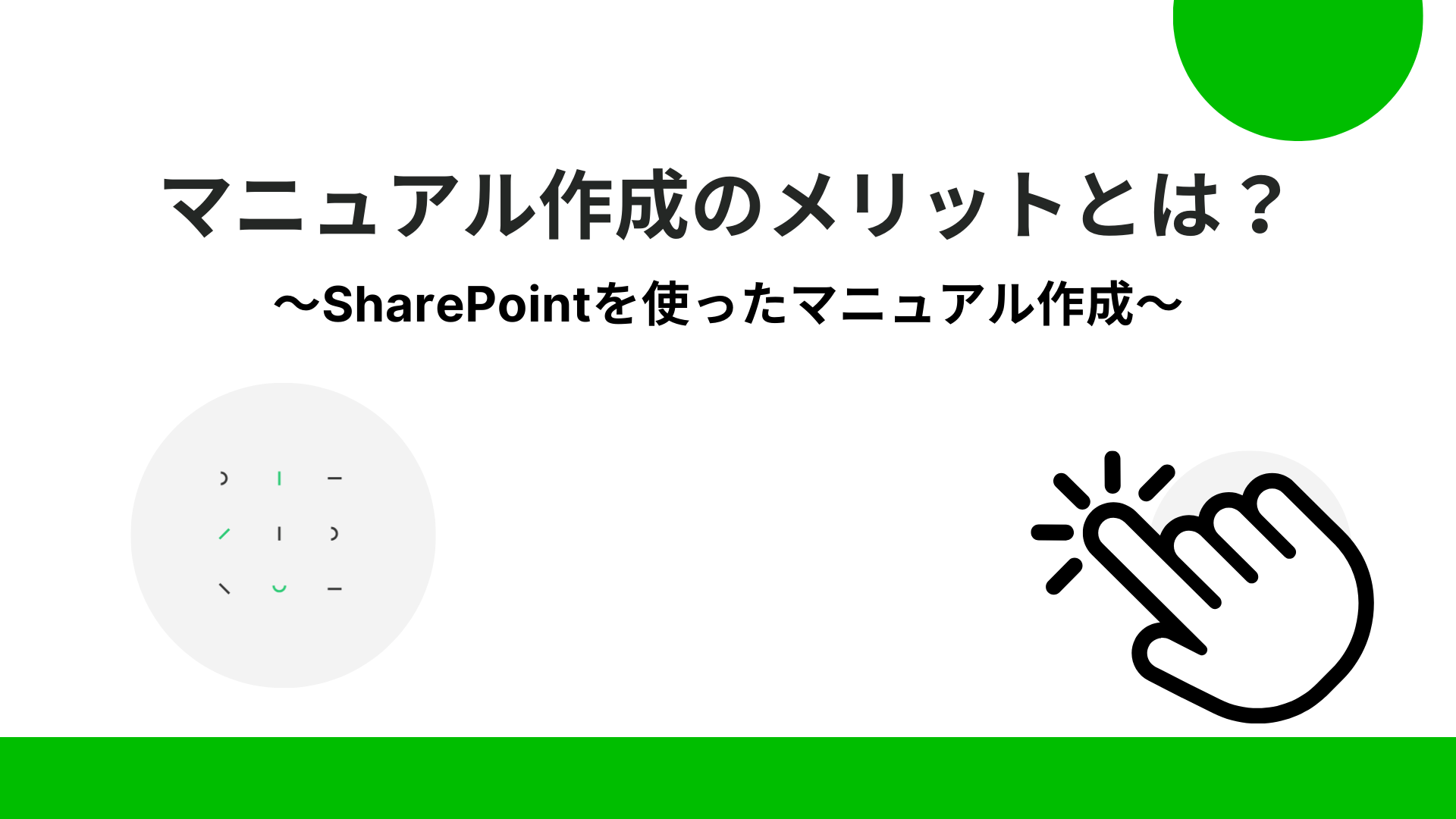

働き方の多様化やテレワークの普及を背景に、社内マニュアルのデジタル化が加速しています。中でも注目されているのが、Microsoftの「SharePoint」です。本記事では、SharePointを活用した社内マニュアルの作成方法と、その活用事例・メリット・運用のポイントまでを徹底解説します。働き方の多様化やテレワークの普及を背景に、社内マニュアルのデジタル化が加速しています。中でも注目されているのが、Microsoftの「SharePoint」です。本記事では、SharePointを活用した社内マニュアルの作成方法と、その活用事例・メリット・運用のポイントまでを徹底解説します。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次
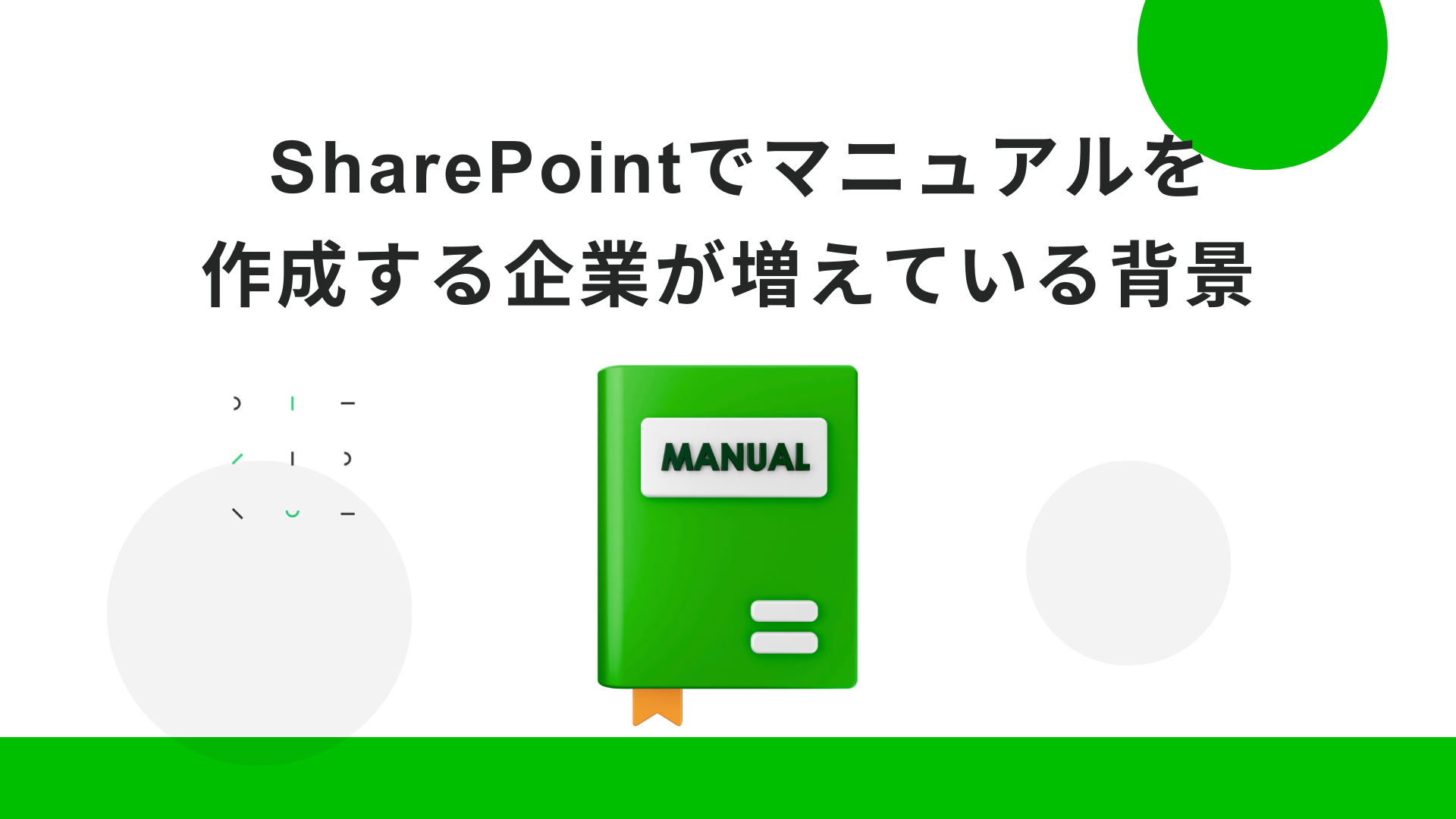
昨今、多くの企業でデジタル化や業務効率化の流れが加速し、社内に蓄積されたノウハウや情報の管理方法が見直されつつあります。特にマニュアル類については、従来のような紙やPDFファイルによる管理から、より柔軟で更新しやすい仕組みへの移行が求められるようになっています。その背景には、働き方の多様化やテレワークの定着といった環境の変化があり、従業員が「いつでも・どこでも・すぐに」必要な情報にアクセスできる環境の整備が急務となっているからです。
こうした中で注目されているのが、Microsoft社が提供する情報共有プラットフォーム「SharePoint」です。SharePointは、社内の情報を一元管理できるだけでなく、閲覧権限や編集履歴の管理、他のMicrosoft365製品との連携がスムーズに行える点が高く評価されています。特に、情報システム部門や業務改善を担う部署、社内DXを推進するチームにとっては、単なるドキュメント共有にとどまらず、業務知識の蓄積・共有を行う基盤として活用できる点が大きな魅力となっています。
企業によっては、これまで部署ごとに個別に作成・保存されていたマニュアルを、SharePointに集約することで、属人化の解消や情報の重複・散逸を防ぐ体制を整えています。また、組織内でルールや手順が変更された際にも、リアルタイムで修正・周知が可能なため、情報鮮度を保ちつつ業務の正確性を担保する仕組みとして機能しています。このように、企業のナレッジマネジメントを支えるツールとして、SharePointは確かな地位を築きつつあるのです。
SharePointを使って社内マニュアルを作成・管理する最大のメリットは、「情報が一元化されることで、必要な人が、必要なときに、正確な情報にアクセスできる」環境が整う点にあります。これは従業員の日々の業務を支えるだけでなく、問い合わせ対応や教育の工数削減にも直結する効果があるため、多くの企業で実感されている利点です。
SharePointはMicrosoft 365の一部として提供されているため、WordやExcel、PowerPointといったビジネスで日常的に使われているツールとの親和性が非常に高く、既存資料をそのまま活用しながらコンテンツを構築できるという使いやすさも大きな魅力です。新たなツール導入のために特別な教育を行う必要が少ない点も、現場へのスムーズな浸透を後押ししています。
SharePointではページ形式でマニュアルを作成できるため、単なる文書の羅列ではなく、画像・動画・リンクなどを含んだ視覚的に分かりやすい構成が可能です。これにより、ITに詳しくない一般社員でも直感的に操作を理解しやすく、特に社内システムや業務フローの説明において効果を発揮します。
加えて、SharePointの持つ履歴管理機能により、いつ・誰が・どこを編集したかという情報が自動で記録されるため、マニュアルの内容が不意に変更された際もすぐに把握することができます。この仕組みは、マニュアルの信頼性を保つうえで非常に有効です。
このように、SharePointはただのファイル保管ツールではなく、組織全体で業務知識を継続的に共有・改善していくための「ナレッジのハブ」として機能します。情報の更新性や管理性、そして視認性に優れたこのツールを活用することで、企業はマニュアルという資産を、より活きたものとして運用することができるのです。
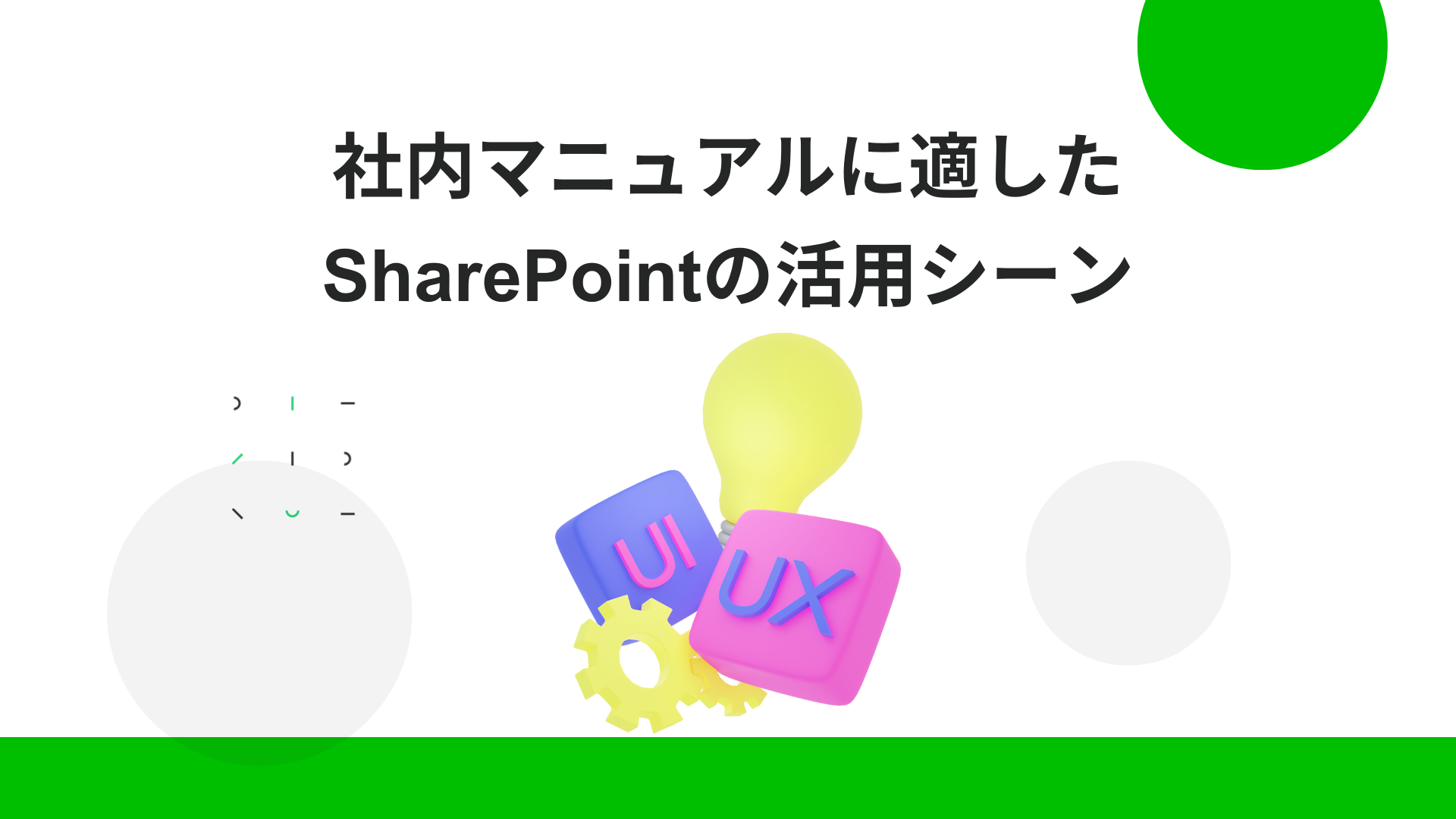
SharePointは、社内に蓄積された知識や業務ノウハウを整理・共有し、組織全体の生産性を高めたい企業にとって、非常に柔軟で実用的なプラットフォームです。特に、業務の標準化や属人化の解消を目指す情報システム部門やDX推進チームにおいて、多くの導入実績があります。
代表的な活用事例として挙げられるのが、社内システムの操作マニュアルの整備です。経費精算や勤怠管理、業務アプリの利用方法など、日々の業務に関わる操作手順をSharePoint上にまとめておくことで、社員が自己解決しやすい環境を構築できます。その結果、問い合わせ件数が減り、操作ミスやトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
SharePointは新入社員のオンボーディングにも有効です。入社直後に必要な情報を一元化しておくことで、「どこに何があるのか分からない」といった不安を軽減し、スムーズな業務立ち上げを支援できます。業務の流れや社内用語、ITツールの使い方など、部署を問わず確認が必要な情報をポータルに集約しておくことで、部門間の情報格差も解消されます。
部署ごとの業務ルールや業務フローを明文化し、組織全体で共通の理解を持つことも可能です。部門ごとに異なっていた手順や対応方針を標準化し、マニュアルとして社内に共有することで、業務のバラつきや属人化を抑える効果が期待できます。また、過去の質問対応やトラブル事例をFAQとして蓄積しておけば、社内全体のナレッジとして活用され、自己解決を促す仕組みにもつながります。
このように、SharePointは単なるドキュメントの保管場所にとどまらず、社内マニュアルを軸に「使われる情報」を整備することで、知識の共有と活用を促進する“組織の知識基盤”として活躍します。
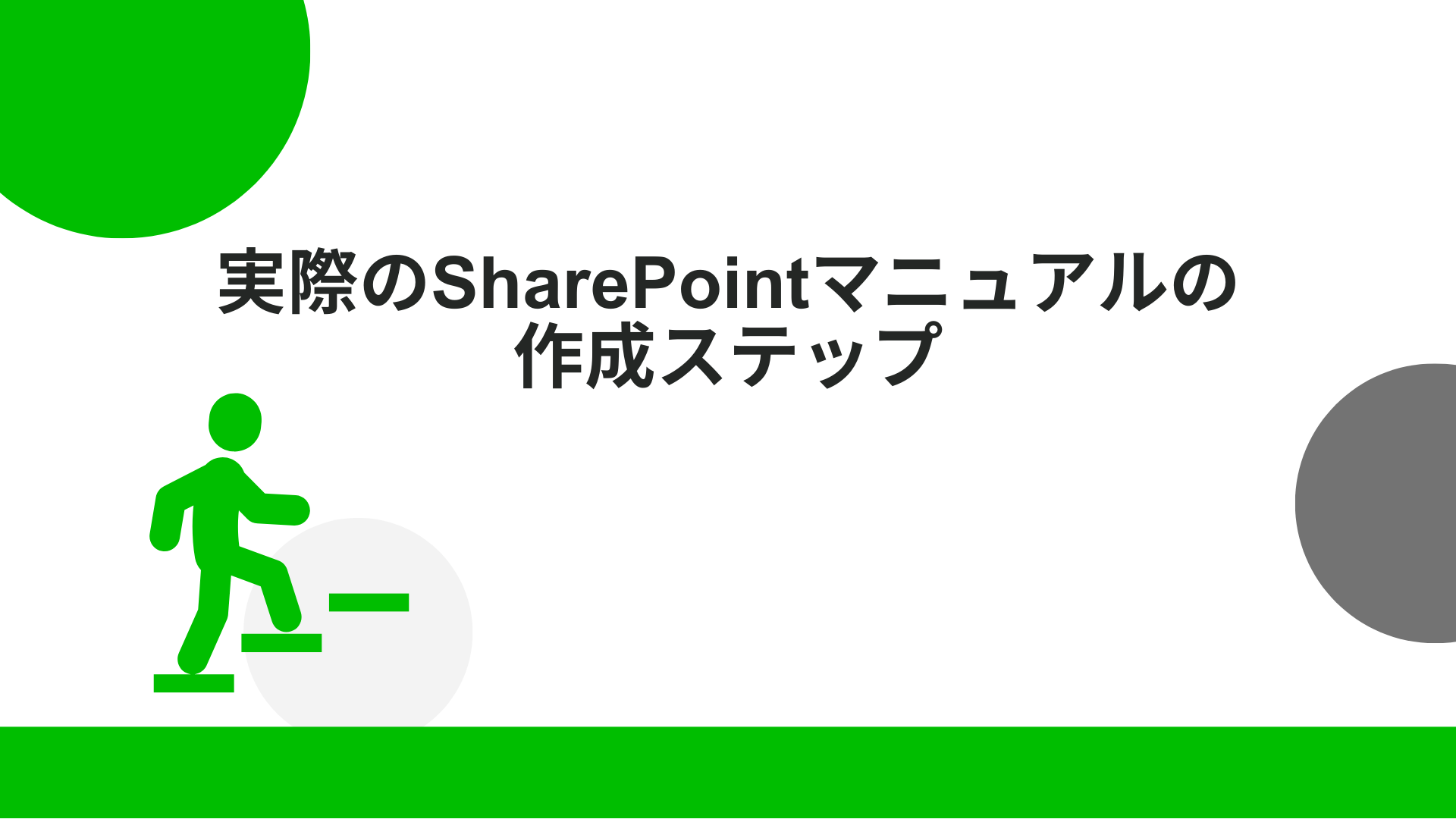
SharePointで社内マニュアルを作成する際は、いくつかのステップに沿って進めることで、構造的で運用しやすいコンテンツを構築できます。
SharePointでマニュアルを構築する際は、まず「サイトの作成」からスタートします。用途に応じて、部門間の共同作業に適した「チームサイト」や、全社向けの情報配信に適した「コミュニケーションサイト」を選ぶことができます。目的を明確にし、最適なテンプレートを選定することで、運用の土台が整います。
サイトを構築したら、次に行うのが情報構造の設計です。マニュアルの内容を業務カテゴリや部署別に分類し、フォルダやライブラリの配置を工夫することで、誰が見ても迷わず情報にたどり着けるレイアウトを整えます。初期段階で命名ルールや分類基準をしっかりと定めておくことで、運用フェーズでもスムーズな更新・追加が可能になります。
その上で、実際のマニュアルコンテンツを作成していきます。既存のWordやPDFファイルをアップロードして使う方法も一般的ですが、SharePointのページ作成機能を活用すれば、画像や動画、リンクなどを埋め込んだ視覚的にわかりやすいマニュアルも作成できます。特に操作手順を説明する際には、スクリーンショットを使ったステップ解説が効果的です。コンテンツの量が増えてきた段階では、ナビゲーション設計にも配慮する必要があります。トップページやサイドメニューを整備し、「よく使う業務」や「部署別マニュアル」といったカテゴリごとの導線を設けることで、ユーザーが目的の情報にすばやくアクセスできるようになります。また、サイト内検索の使いやすさも意識し、キーワードやページタイトルの付け方にも工夫が求められます。
最後に重要なステップが「アクセス権限の設定」です。SharePointでは、ユーザー単位・グループ単位で細かな閲覧・編集権限を設定できるため、例えば、編集は情報システム部門に限定し、閲覧は全社員に許可する、といったセキュリティポリシーを反映させることが可能です。これにより、情報の正確性と安全性を担保しながら、社内全体への展開が実現できます。
このような一連の構築作業は、すべてノーコードで完結するのがSharePointの大きな強みです。専門的な開発スキルがなくても、現場の担当者が自ら設計・編集・改善を行えるため、導入後も柔軟に運用しながら、継続的な改善を重ねていくことができます。
SharePointで社内マニュアルを構築・運用する際、多くの企業が同じような課題に直面します。下記に代表的な課題とその解決策をまとめました。
| よくある課題 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| 情報が探しにくい | フォルダ構成が不明確、命名がバラバラ | 業務・部署ごとの分類設計と命名ルールの統一 |
| 情報が更新されない | 担当が不明確、更新ルールがない | 更新担当の明確化と定期的な見直しのスケジュール化 |
| 書き方がバラバラで読みにくい | テンプレートやガイドラインがない | コンテンツ作成テンプレートを用意し、統一感を出す |
| マニュアルの存在が知られていない | 社内周知が不十分 | サイト内で目立つ導線を設置し、周知メールや説明会を実施 |
特に初期段階では、設計とルールづくりが鍵です。どれだけ優れたツールでも、「誰が、どうやって使うか」が曖昧なままでは活用されません。運用体制と見直しの仕組みをあらかじめ整備することで、長く使われるマニュアルに育てていくことが可能になります。

情報システム部門やDX推進担当者は、SharePointの導入・運用において中心的な役割を果たします。特に重要なのは、システムの構築にとどまらず、「現場にいかに使ってもらうか」を見据えた設計・運用を行うことです。マニュアルを作るのも使うのも現場の社員たちであるため、「使いやすさ」や「わかりやすさ」は定着の大前提となります。
最初から全社展開を狙うのではなく、まずは一部門や限られた業務から導入し、成果を確認しながら少しずつ拡張していく“スモールスタート”が効果的です。現場の声を拾いながら改善を繰り返すことで、自然な定着と活用の広がりが期待できます。
また、運用面では「誰が更新するのか」「どの頻度で見直すのか」といったルールを明文化し、属人化を防ぐ仕組みを整えることも不可欠です。特にSharePointは自由度が高いがゆえに、放置すると情報が散乱しやすいため、継続的なメンテナンス体制が求められます。
導入初期には、操作ガイドやFAQ、動画マニュアルなどを活用し、現場社員が自信を持ってツールを使える状態を整えることが大切です。
どれだけマニュアルや運用ルールを整備しても、「実際の画面上で何をすればいいのか分からない」といった声は少なからず発生します。特に導入初期は、現場の戸惑いを減らす工夫が欠かせません。そのため、簡単な操作ガイドや動画チュートリアルを用意し、誰でも迷わず使える状態を整えておくことが重要です。
こうした課題を解決する手段として、デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」の導入が非常に効果的です。SharePointの画面上に「次はこちらをクリック」といった操作ナビゲーションをリアルタイムで表示できるため、マニュアルを読まずとも直感的に操作を進められます。
その結果、習熟スピードが大幅に向上し、問い合わせ件数の削減や現場の負担軽減にも直結します。短期間での定着を目指す企業にとって、Fullstarは現場の生産性を高める強力な補完ツールとなるでしょう。
マニュアルは単なる「説明書」ではなく、組織のノウハウや業務の知恵が詰まった貴重なナレッジ資産です。そしてそれを社内で活かすためには、「誰でも迷わずアクセスできる」「常に最新状態が保たれている」「わかりやすく構成されている」ことが不可欠です。SharePointは、こうした条件を満たすマニュアルのプラットフォームとして非常に優れており、Microsoft 365との連携性や柔軟な構成管理機能を活かすことで、業務効率化とナレッジ共有の両立を実現できます。特に、情報システム部門やDX推進チームが主導して構築と運用のルールを整えることで、マニュアルの属人化を防ぎ、組織全体で知識を活かす文化づくりが可能になります。今後は、「作ること」だけでなく、「継続的に使われる仕組み」に目を向け、ナレッジを“活きた資産”へと育てていくことが求められます。SharePointを起点に、業務の標準化と情報共有の未来を、一歩ずつ確実に進めていきましょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行