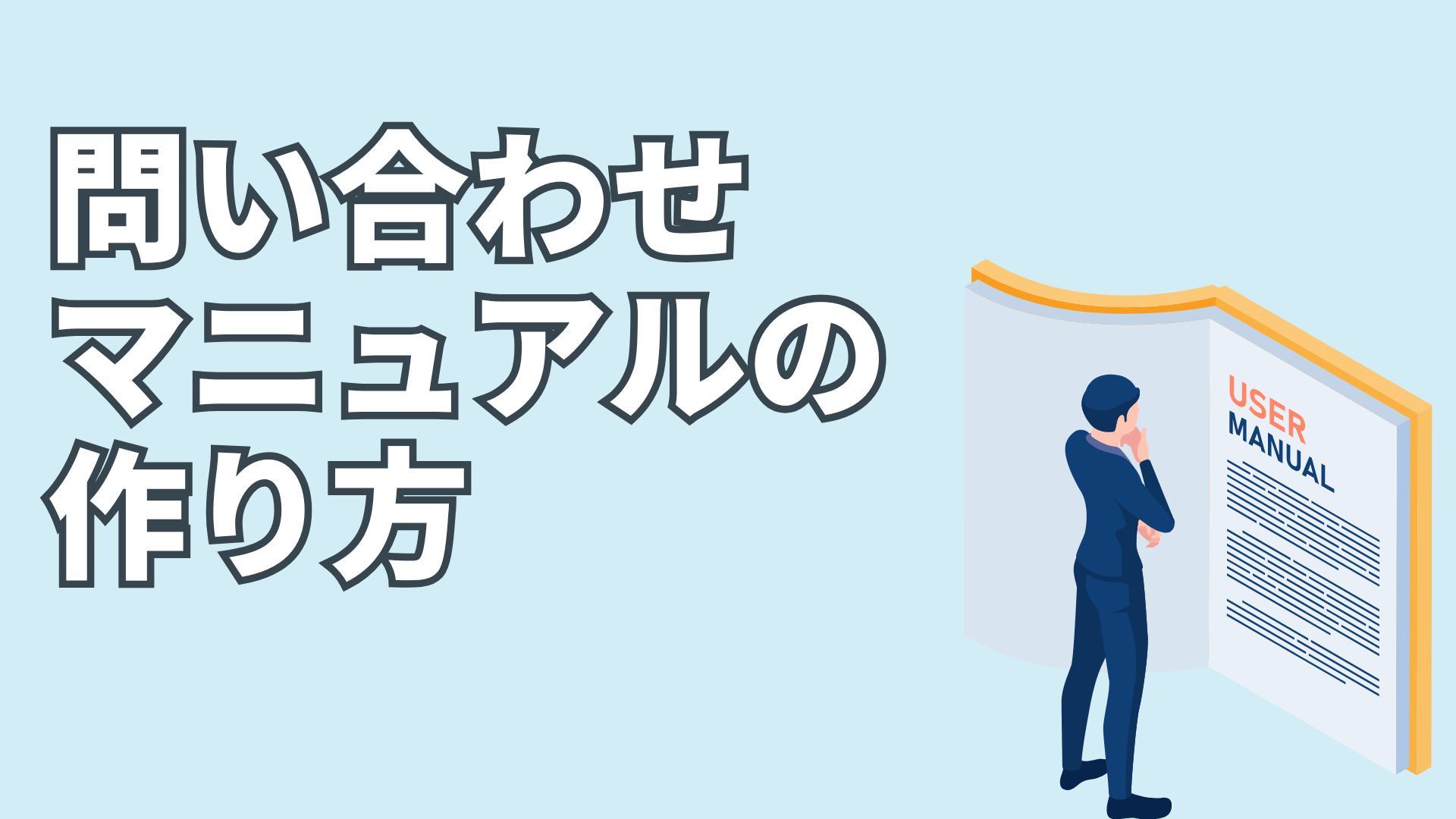

日々多くの問い合わせに対応する中で、「同じような質問に何度も答えている」「担当者によって案内の品質にバラつきがある」といった課題を感じてはいないでしょうか。これらの課題解決に有効なのが問い合わせマニュアルです。質の高いマニュアルは、業務の属人化を防ぎ、対応品質を安定させるための重要な資産となります。
マニュアルの作り方一つで、その効果は大きく変わります。作成のメリットを最大化し、現場で本当に使われるマニュアルにするためには、押さえるべきポイントがあります。また、作成したマニュアルを作っただけにさせず、継続的に活用を促すツールの導入も欠かせません。
本記事では、問い合わせ対応マニュアルの基本的な作り方から、実用性を高めるポイント、そして作成したマニュアルの価値を最大化する活用術までを網羅的に解説します。
この記事は、特に以下のような課題をお持ちの方におすすめです。
このような課題をお持ちの社内DX推進・管理部門のご担当者様に特におすすめの内容となっています。
マニュアルの有効活用・社内問い合わせ削減をしたい方へ
ワークフロー・経費精算・CRM・ERPなど様々な業務システムを「操作に迷わなくする」仕組みで、社内問い合わせを90%削減・マニュアル閲覧率向上!
目次

問い合わせ対応マニュアルとは、顧客や社内からの質問に対して、対応手順や回答内容、関連知識などを体系的にまとめた文書のことです。単なるFAQ(よくある質問)のリストに留まらず、対応時の心構えや言葉遣い、システム操作の手順といった、品質を担保するためのあらゆる情報が含まれます。
ビジネス環境が複雑化し、顧客ニーズも多様化する現代において、問い合わせ対応の品質は企業全体の評価に直結します。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により新しいツールやシステムが次々と導入される中、従業員が迷わず業務を遂行できる環境を整えることは急務です。
しっかりとしたマニュアルがあれば、経験の浅い担当者でもベテランと同様の質の高い対応が可能になります。これにより、顧客満足度の向上はもちろん、対応のばらつきによるトラブルを未然に防ぐリスクマネジメントの観点からも、その重要性はますます高まっています。
質の高い問い合わせマニュアルは、現場レベルの課題解決だけでなく、経営視点からも大きなメリットをもたらします。
特定の担当者しか対応できない業務は、その担当者が不在の際に業務が滞るリスクを抱えています。マニュアルによって業務知識を形式知化し、組織全体で共有することで、業務の属人化を防ぎ、事業の継続性を高めます。
従業員が日々の業務で発生する疑問点を自己解決できず、その都度、上司や同僚に質問していては、組織全体の生産性が低下します。検索性の高いマニュアルを整備することで、従業員一人ひとりの自己解決能力を高め、問い合わせ対応にかかる工数を削減します。これは、「社内問い合わせ業務の効率化・削減」にも繋がる重要な取り組みです。
問い合わせに対して「回答が遅い」「担当者によって言うことが違う」といった状況は、顧客の不満に直結します。社内においても、必要な情報がすぐに見つからない環境は従業員のストレス要因となり、エンゲージメントの低下を招きかねません。整備されたマニュアルは、迅速で一貫性のある対応を可能にし、顧客と従業員双方の満足度を向上させます。
参考:【最新】問い合わせ対応を効率化する5つの方法。問題と解決のコツ、問合せ効率化事例も解説
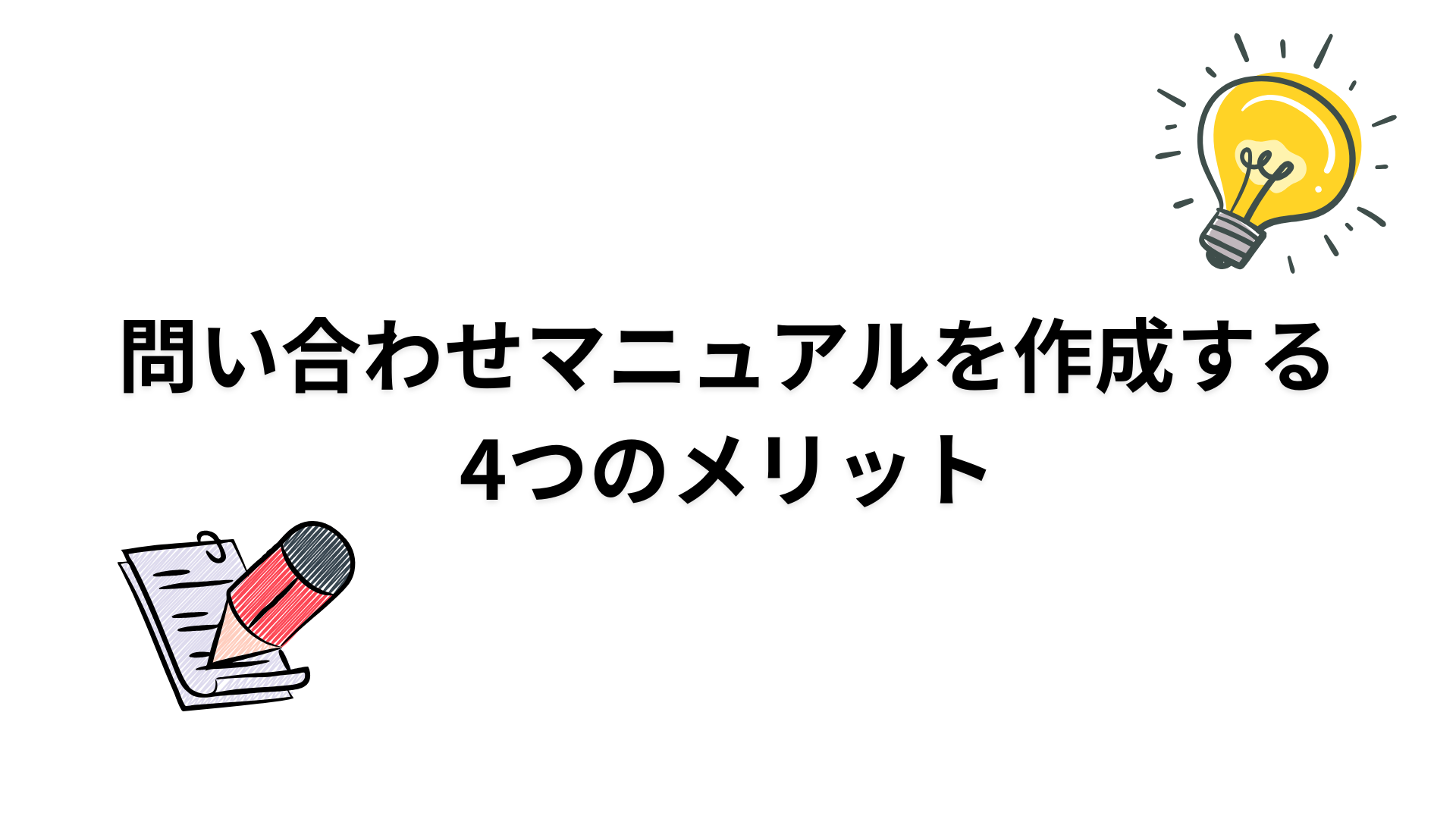
問い合わせマニュアルを整備することは、単に日々の業務を楽にするだけでなく、組織全体に多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットについて詳しく解説します。
問い合わせマニュアルを作成する最大のメリットは、業務品質を一定のレベルに標準化できることです。マニュアルがあれば、誰が対応しても同じ手順・同じ品質で業務を遂行できるため、担当者ごとのスキルの差や知識のばらつきをなくすことができます。これにより、ベテラン頼りの状況から脱却し、業務の属人化を解消できます。特定の担当者が急に休んだり、退職したりしても、業務が滞るリスクを大幅に軽減できるでしょう。
新しいスタッフが入社したり、担当者が異動してきたりした際の教育は、多くの時間と労力を要します。マニュアルが整備されていれば、指導役がつきっきりで教える必要がなくなり、新任者は自分のペースで業務内容を学習できます。基本的な知識や手順はマニュアルで習得してもらうことで、指導役はより実践的で高度な内容に集中して教えることができ、教育全体の効率が飛躍的に向上します。結果として、教育にかかる時間と人件費、いわゆる教育コストを大幅に削減することが可能です。
問い合わせに対する「迅速」で「正確」な回答は、顧客満足度に直接的な影響を与えます。マニュアルによって回答内容や手順が標準化されていれば、担当者が迷う時間が減り、よりスピーディーな対応が実現します。また、「担当によって言うことが違う」といった事態を防ぎ、一貫性のあるサポートを提供できるため、顧客は企業に対して安心感と信頼感を抱くようになります。こうした一つ一つの丁寧な対応の積み重ねが、結果として顧客満足度の向上、ひいては企業のブランドイメージ向上に繋がるのです。
マニュアルは、一度作って終わりではありません。日々の問い合わせ対応で得られた新たな知見や、発生したイレギュラーな事象とその解決策などを追記していくことで、組織にとって貴重なナレッジ(知識)が蓄積されていきます。この蓄積されたナレッジは、単なる対応履歴ではなく、業務プロセスそのものを見直すための重要なデータとなります。例えば、「同様の問い合わせが頻繁に発生している」という事実が分かれば、それは製品やサービスの改善、あるいは情報提供のあり方を見直すきっかけになるかもしれません。マニュアルを「生きたドキュメント」として運用することで、継続的な業務改善のサイクルを生み出すことができるのです。

実際に現場で役立つ問い合わせマニュアルを作成するには、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。ここでは、誰でも分かりやすいマニュアルを作るための具体的な5つのステップを解説します。このステップに沿って進めることで、網羅的で実用的なマニュアルを効率的に作成できます。
マニュアル作成の第一歩は、土台となる情報を集めることから始まります。まずは、過去にどのような問い合わせがあったのかを徹底的に洗い出しましょう。メールやチャットの履歴、電話の応対記録、担当者の記憶など、あらゆるソースから情報を収集します。
収集した情報は、ただリストアップするだけでは不十分です。次に、これらの問い合わせを「種類」や「頻度」で分類・分析します。
この分析を通じて、マニュアルに盛り込むべき情報の優先順位が明確になり、利用者のニーズに即した内容にすることができます。
集めた情報を元に、マニュアルの全体像、つまり「目次」となる構成案を作成します。利用者が目的の情報をすぐに見つけられるよう、論理的で分かりやすい構成にすることが重要です。
例えば、以下のような構成が考えられます。
構成が決まったら、各項目にどのような内容を記述するか、箇条書きで骨組み(アウトライン)を作成します。この段階で内容の過不足や重複をチェックしておくことで、手戻りを防ぎ、効率的に執筆作業を進められます。
骨組みができたら、いよいよ本文の執筆です。マニュアルは、新人や知識のない人でも理解できることが大前提です。以下の点を意識しましょう。
誰が読んでも同じように理解・実行できる表現を徹底することが、マニュアルの品質を左右します。
文字だけの説明では、どうしても伝わりにくい内容があります。特にシステム操作の手順などは、実際の画面キャプチャや図を挿入することで、理解度が飛躍的に向上します。
ただし、画像を多用しすぎるとページの表示が重くなったり、かえって見づらくなったりすることもあるため、あくまで文章を補完する目的で、効果的な箇所に絞って使用しましょう。
マニュアルは「作って終わり」ではありません。製品の仕様変更や新サービスの開始、業務プロセスの見直しなど、マニュアルの情報は時間とともに古くなっていきます。
情報が古いまま放置されたマニュアルは、誤った対応を誘発する原因となり、やがて誰にも使われなくなってしまいます。「いつ」「誰が」「どのように」マニュアルを更新するのか、具体的なルールを定めておくことが不可欠です。
常に最新の状態に保ち続けることで、マニュアルは信頼性の高い「生きた情報源」として機能し続けます。

手順通りにマニュアルを作成しても、細かな配慮が欠けていると「使いにくい」マニュアルになってしまうことがあります。ここでは、マニュアルの実用性をさらに高めるための3つの重要なポイントを紹介します。
マニュアルの利用者は、常に時間があるわけではありません。多くの場合、顧客を待たせていたり、緊急のトラブルに対応していたりする状況でマニュアルを開きます。そのため、「いかに早く目的の情報にたどり着けるか」という視点が非常に重要です。
例えば、「エラーメッセージから逆引きできる索引を作る」「問い合わせ電話でよく使われるキーワードで検索できるようにする」など、実際の利用シーンを具体的に想像しながら構成や見出しを工夫することで、現場での利便性が格段に向上します。
前述の通り、マニュアルは誰が読んでも理解できる必要があります。IT部門の担当者が作ったマニュアルが、営業部門の担当者には全く理解できない、といった事態は避けなければなりません。
作成者が「当たり前」だと思っている言葉でも、部署や経験が違えば通用しない可能性があります。マニュアルを書き終えたら、必ずマニュアルの利用者(特に新人や他部署の担当者)に読んでもらい、分かりにくい点がないかレビューしてもらうプロセスを挟むと良いでしょう。
マニュアルをゼロから作成するのは大変な作業ですが、テンプレートを活用することで、その負担を大幅に軽減できます。テンプレートを使えば、フォーマットが統一されるため、誰が作成しても見やすく、品質のばらつきを防ぐことができます。
社内で標準のテンプレートを一つ用意しておけば、更新や追加作業もスムーズに進みます。Web上には無料でダウンロードできる様々なマニュアルテンプレートも存在するため、それらを自社の業務に合わせてカスタマイズして利用するのも有効な手段です。

せっかく時間と労力をかけて作成したマニュアルも、社員に使われなければ意味がありません。ここでは、マニュアルが「作っただけ」で終わってしまうのを防ぎ、組織全体で活用するための具体的な方法論を紹介します。
多くの企業で、導入当初は活用されていたマニュアルが、次第に使われなくなり「形骸化」してしまう問題が発生します。その主な原因は以下の通りです。
特に「探すのが面倒」という課題は深刻です。人は、たとえそこに答えがあると分かっていても、探す手間が心理的な負担となり、「詳しい人に直接聞いた方が早い」という行動を選択しがちです。これが、マニュアルが使われなくなる最大の原因の一つと言えるでしょう。
この「探しにくさ」を解決する第一歩が、FAQシステムやナレッジベースといった専用ツールの導入です。これらのツールは、ファイルサーバーにWordやExcelのファイルを置くだけの管理方法とは異なり、強力な検索機能を備えています。
キーワード検索はもちろん、カテゴリ分類やタグ付けによって、利用者は目的の情報に素早くアクセスできるようになります。また、閲覧数が多いページを分析して利用者のニーズを把握したり、利用者からのフィードバック機能で内容の陳腐化を防いだりすることも可能です。まずはマニュアルを「見つけやすい」状態にすることが、活用促進の基本となります。
FAQシステムで検索性を高めても、まだ根本的な課題が残ります。それは、利用者が「疑問を感じてから、FAQシステムを開いて、キーワードを入力して検索する」という行動自体が必要な点です。
この最後のひと手間をなくし、活用を次のレベルに引き上げるのが、「デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)」という新しいソリューションです。
DAPは、業務で利用するシステムやアプリケーションの画面上に、操作ガイドや説明を直接表示させることができるツールです。例えば、システムの特定のボタンの上に「?」アイコンを設置し、クリックすると関連マニュアルの該当箇所がポップアップで表示される、といったことが可能になります。
これにより、利用者は「マニュアルを探す」必要がなくなります。 業務の流れの中で、疑問に思ったその場で、必要な情報がシステム側から提示されるため、自己解決が劇的に促進されます。
このアプローチは、マニュアルの活用を促すだけでなく、そもそも問い合わせの発生自体を未然に防ぐ効果もあります。結果として、サポート部門の負担軽減や、複雑なマニュアル作成にかかる工数の削減にも繋がるのです。弊社が提供するDAPツール「Fullstar」は、このような課題を解決し、システムの定着化と問い合わせ業務のDXを強力に支援します。
本記事では、問い合わせ対応マニュアルの重要性から、具体的な作り方、そして作成したマニュアルを形骸化させずに活用するための先進的なアプローチまでを解説しました。
質の高いマニュアルは、業務の標準化、教育コストの削減、顧客満足度の向上といった多くのメリットをもたらす、組織にとっての重要な資産です。成功の鍵は、利用者の視点に立って「分かりやすく」「見つけやすい」マニュアルを作成し、それを継続的に更新していく仕組みを整えることにあります。
しかし、作成したマニュアルが「探すのが面倒」という理由で使われなければ、その価値は半減してしまいます。FAQシステムなどで検索性を高めることに加え、DAPのようなツールで「探させない」仕組みを構築することで、従業員の自己解決を促し、問い合わせ業務全体のデジタルトランスフォーメーションを実現できるでしょう。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行