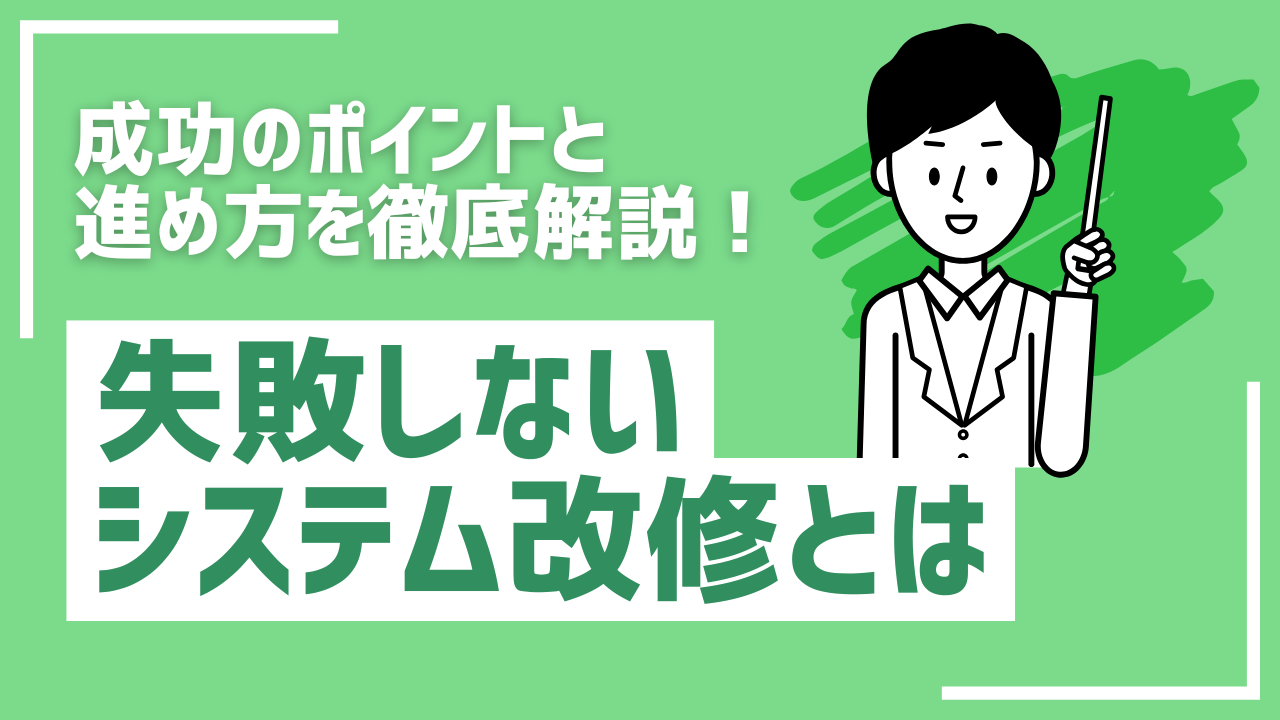

社内システムを導入・リプレイスする方へ
システムを導入・リプレイスは高額なコストがかかるからこそ、失敗できません。
おさえておくべきシステム導入チェックリストと、導入後の定着浸透のための手法を知りましょう
【社内システム担当のお悩みを解決します】
あらゆるシステムの「導入しただけ」を防ぎませんか?
システム画面上に「吹き出しガイド」や「チュートリアル」を”あとのせ設置”することで、システム習熟度の向上と問い合わせ対応コストの削減を実現。
「問い合わせ90%削減」や「申請差し戻し47%削減」、「95%がマニュアル以上に分かりやすいと回答」など、具体的な取り組み事例とツールを資料にまとめました。
◆詳細と事例はこちら >
目次
近年、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する中で、既存の業務システムに課題を感じているケースが増加しています。 「動作が遅い」「使い勝手が悪い」「セキュリティに不安がある」といった課題に直面しながらも、新規システムへの全面移行はコストやリスクの観点からハードルが高い…そんな状況において、システム改修は実効性の高いソリューションです。 本記事では、情報システム部門・社内ヘルプデスク・DX推進担当者が知っておくべき、システム改修の基礎から実践的な進め方までを網羅的に解説します。
システム改修とは、既存の業務システムに対して、業務要件の変化や技術的課題に対応するために機能追加・修正・性能向上などを行うプロセスです。完全な新規開発ではなく、現状のシステム資産を活かしながら改善を図る点が最大の特徴です。
以下は代表的な改修内容です。
システム改修を検討する際、しばしば「新システムの開発」や「リプレイス(全面刷新)」との違いが問われます。
それぞれの特徴を正しく理解することで、現状に最適な選択肢を見極めることが可能です。
| システム改修 | 新システム開発 | リプレイス | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 改善・最適化 | ゼロからの構築 | 全面入れ替え |
| コスト | 低~中 | 高 | 非常に高 |
| リスク | 低 | 高 | 非常に高 |
| 期間 | 短~中期 | 長期 | 長期 |
| 適用ケース | 既存システムの機能改善 | 新規事業・業務改革 | 老朽化システムの刷新 |
システム改修は、既存資産を活かしつつ、現実的なコストで業務ニーズに応える手段として有効です。
一方、新規開発やリプレイスは抜本的な変革を要する場合に選択されます。
以下のような状況では、システム改修の検討が急務となるケースが多いです。
これらに対処するため、段階的に改善を進められるシステム改修は、コスト効率が高く現実的な選択肢です。
システム改修の成功には、改修の種類や範囲を明確にし、最適な方法を選ぶことが不可欠です。
ここでは、ハード・ソフトの区分、改修規模ごとの分類、内製か外注かの選択といった観点から詳細に解説します。
ハードウェア改修
サーバーの老朽化やストレージ容量の逼迫は、パフォーマンス低下や障害リスクを引き起こします。こうした場合、クラウド移行やサーバースペックの増強、ネットワーク帯域の拡張を行うことで、インフラ面からのシステム改善が実現します。
ソフトウェア改修
ソフトウェア面では、アプリケーションのコード最適化やデータベースのチューニング、UI改善などが該当します。とくにレガシー言語による開発資産を最新言語・フレームワークに置き換えることで、保守性と拡張性を高める効果が期待されます。
部分改修(局所対応)
特定業務プロセスや機能に絞った改修です。例えば、帳票出力機能のみの強化や、ログイン画面の認証方式の変更など。短期間・低コストで実施可能なため、限られたリソースで効果を出したい場合に有効です。
全体改修(アーキテクチャ刷新)
システム全体の設計見直しを行い、場合によってはモノリシック構造からマイクロサービス構造へ移行するなど、中長期的な競争力を見据えた改修です。ハード・ソフトの全面的な見直しが伴うため、リプレイスに近い工数と費用がかかるケースもあります。
リファクタリングとの違い
リファクタリングはコードの内部構造を改善する作業であり、新機能の追加や業務プロセス変更には対応しません。あくまで保守性やパフォーマンス向上を目的とした内部改修です。
内製(自社開発)
自社の業務フローに精通した開発メンバーにより、柔軟かつスピーディーな対応が可能です。
さらに、改修ノウハウが蓄積されるため、将来的な改修にも強くなります。
ただし、リソースや技術面で制約がある場合、対応範囲が限定されがちです。
外部委託(ベンダー活用)
高度な専門知識が必要な領域や、期間・品質を重視するプロジェクトでは外部委託が有効です。
特に最新技術導入やクラウド移行、セキュリティ強化を目的とした改修では、実績のあるパートナー選定が成功のカギとなります。
システム改修は、既存システムを活用しながら業務効率を高め、運用負荷を軽減する有効な手段です。特に、全面リプレイスには至らないが「現状に明確な課題がある」場合、コストやリスクを抑えて柔軟に対応できる選択肢となります。
まず、メリットとして以下が挙げられます。
一方で、注意すべきデメリットも存在します。
このように、改修は「的確な課題抽出」と「適切な対応範囲の設定」が成否を分けるポイントです。
システム改修は、場当たり的に行うのではなく、計画的・段階的に進めることが成功のカギとなります。
まず、改修の第一歩は「現状分析」です。どこにボトルネックがあるのか、どの機能が使いにくいのか、具体的な課題を洗い出します。そのうえで、改修の目的やゴールを明確に設定し、要件定義で仕様や範囲を固めます。ここで関係部門との認識のズレを無くすことが、プロジェクトの成否を左右します。
設計と計画策定では、システム全体への影響を考慮し、必要なリソースやスケジュールを具体的に設定します。実装フェーズでは、影響を最小限にするため段階的なリリースやテストを行い、本番移行後は運用サポート体制を整えて、問題が発生した場合に即時対応できる仕組みが求められます。
成功のポイント
改修にかかる費用と期間は、対象範囲やシステム規模、外部委託の有無によって大きく異なります。多くの企業では「費用感が掴みにくい」との声が聞かれますが、あらかじめ目安を持っておくことで、予算計画とリソース配分がしやすくなります。
費用の主な内訳は以下の通りです。
部分的な改修であれば、数百万円程度の投資で実現可能なケースもあります。一方、全体のアーキテクチャを刷新するような改修であれば、数千万円規模になることもあります。
期間については、機能の追加やUI改善などの小規模改修で1〜3ヶ月、中規模で3〜6ヶ月、大規模では半年から1年以上を要することもあります。
コストと期間の適正化を図るには、「改修目的を明確にし、必要最小限から着手する」ことが効果的です。
日々の業務において、システムに「使いづらさ」や「非効率さ」を感じる場面が増えてきたら、それはシステム改修のタイミングかもしれません。特に、以下のような兆候が見られる場合には、早めに対策を講じることが重要です。
このような課題を放置してしまうと、将来的により大きな障害やコストを生む可能性があります。改修のタイミングを見極め、戦略的に対応を進めることが、安定した業務運用の基盤になります。
システム改修は、業務改善・コスト削減・セキュリティ強化を、現実的な手段で実現できる有力なアプローチです。特に情報システム部門やDX推進部門にとっては、限られたリソースで最大限の効果を引き出す手段として、積極的に活用すべき選択肢といえます。
成功には、課題の可視化、計画的な実行、業務部門との協力が不可欠です。
そして、システム改修は単なる「対応」ではなく、「企業の競争力を高める戦略的な投資」と位置付けることが、これからの時代には求められます。
今こそ、システム改修を通じて、業務の質を高め、未来志向のIT環境づくりを進めていきましょう。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行