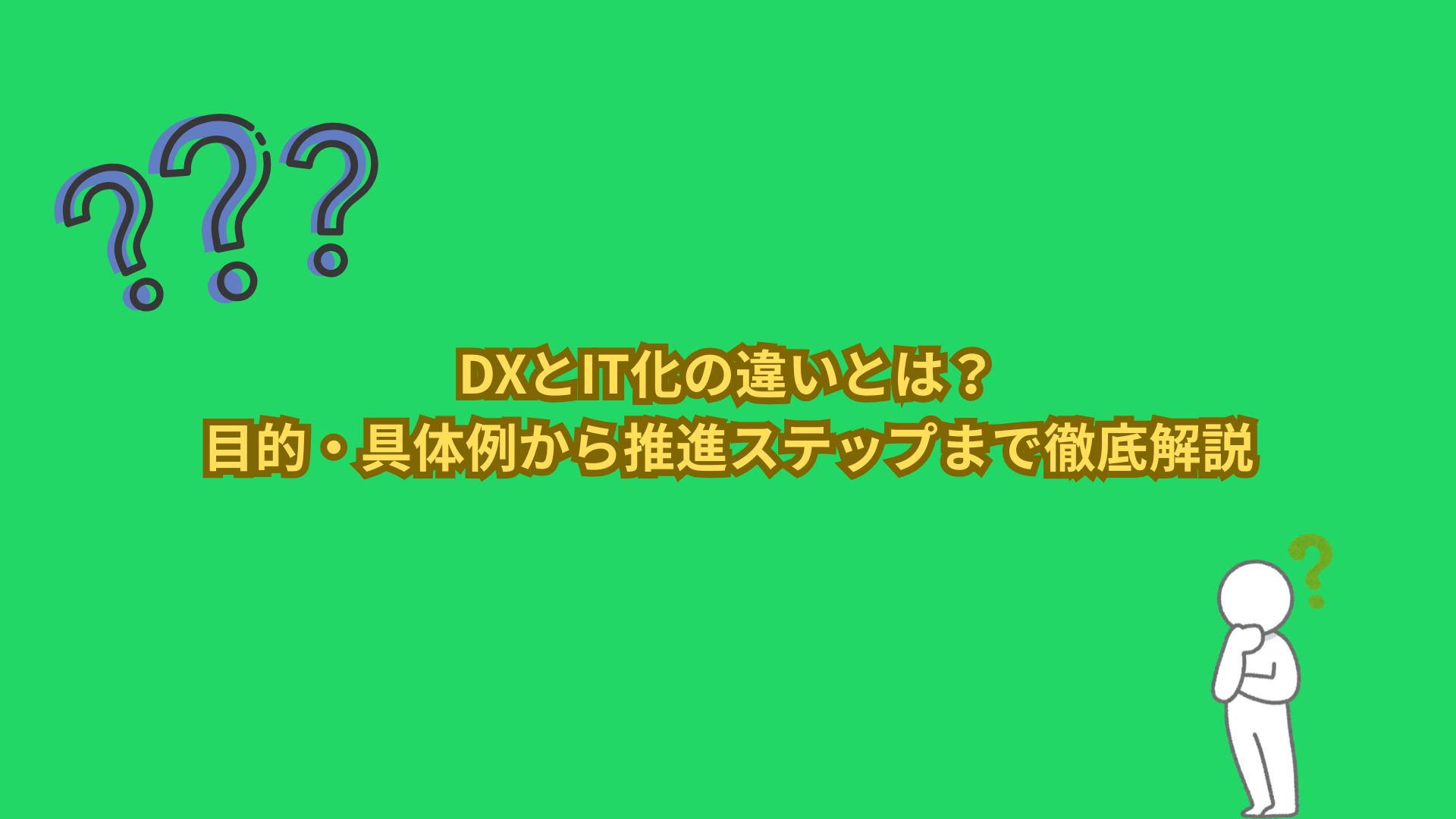
DX(デジタルトランスフォーメーション)とIT化の違い、明確に説明できますか?両者は混同されがちですが、その目的と目指すゴールは全く異なります。IT化が既存業務の効率化を主眼に置くのに対し、DXはデジタル技術を駆使してビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造することを指します。
本記事では、「DXとIT化の違い」を4つの明確なポイントで解説し、なぜ今DXが求められるのか、そして成功への具体的な5ステップまでを網羅的にご紹介します。
この記事は、特に次のような課題をお持ちの方におすすめです。
また、本記事の内容に加え、DX推進におけるシステム導入後の「定着化」の課題と、その解決策であるDAP(デジタルアダプションプラットフォーム)について詳しく解説した資料もご用意しております。ぜひ、貴社のDX推進にお役立てください。
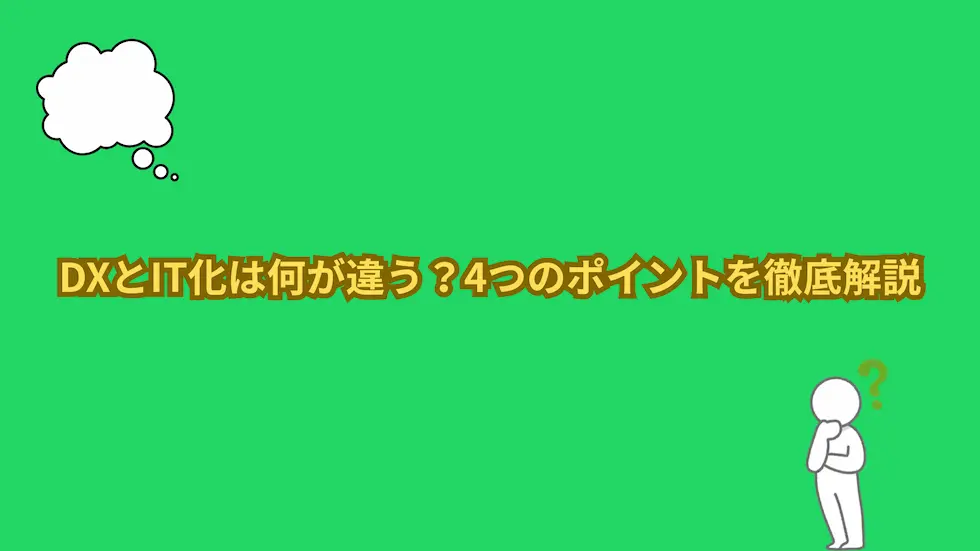
DXとIT化の違いを理解することは、自社のデジタル戦略を正しく推進するための第一歩です。これらは関連性があるものの、目指す方向性が大きく異なります。IT化が「守り」の施策である一方、DXは「攻め」の経営戦略と言えるでしょう。この章では4つのポイントからDXとIT化の違いを明確にします。
DXとIT化の最も根本的な違いは、その「目的」にあります。
IT化の目的は、既存業務の効率化・自動化です。例えば、これまで手作業で行っていた勤怠管理をシステム化したり、紙の書類を電子化してペーパーレスにしたりすることが挙げられます。これは、デジタルツール(IT)を導入することで、業務プロセスをより速く、より正確に、より低コストで行うことを目指す活動であり、「部分最適」のアプローチと言えます。あくまで既存の業務プロセスを前提とした改善活動です。
一方、DXの目的は、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造することにあります。市場や顧客のニーズが多様化・高速化する現代において、競争優位性を確立し続けることが最終的なゴールです。例えば、ある製造業が、製品にセンサーを付けて稼働データを収集・分析し、故障予測やメンテナンスサービスといった新たな収益源を生み出すケースはDXの典型例です。これは、IT化のように単に製造ラインを効率化するだけでなく、ビジネスのあり方そのものを変革する「全体最適」の取り組みです。
目的の違いは、取り組みの「対象範囲」の違いにも直結します。
IT化が対象とするのは、特定の部署や個別の業務プロセスです。経理部門の会計システム導入、営業部門のSFA(営業支援ツール)導入など、範囲が限定的であることがほとんどです。これにより、対象業務の生産性は向上しますが、その効果が全社的なインパクトにつながるとは限りません。
対してDXは、一部門に留まらず、複数の部門を横断し、時にはサプライチェーンや顧客、パートナー企業まで巻き込んだ組織・事業全体が対象範囲となります。先に挙げた製造業の例では、製品開発、製造、営業、カスタマーサービスといった全部門が連携しなければ、新たなサービスモデルは構築できません。このように、DXはサイロ化(部門間の壁)された組織構造を打破し、全社的な変革を促す活動なのです。
プロジェクトを誰が主導するかも、DXとIT化で大きく異なります。
IT化は、多くの場合、情報システム部門が主導します。各事業部門からの「この業務を効率化したい」という要望を受け、最適なITツールを選定・導入・運用することが主な役割となります。あくまで業務部門のニーズに応える「支援者」としての立場が中心です。
しかし、DXはビジネスモデルの変革そのものであるため、経営トップの強いリーダーシップと、事業部門が主体となって推進する必要があります。どのような価値を顧客に提供し、どのようにビジネスを変革していくのかというビジョンを描くのは、経営者や事業責任者の重要な役割です。情報システム部門は、そのビジョンを実現するための技術的なパートナーとして協働しますが、あくまで主役は経営・事業部門となります。経営層のコミットメントなくしてDXの成功はありえません。
最終的にどのような「成果」を重視するかという点も、両者の違いを明確にします。
IT化で重視される成果は、コスト削減、業務時間の短縮、ヒューマンエラーの削減といった、主に社内向けの定量的指標です。例えば、「ペーパーレス化により、印刷コストを年間XX円削減した」「システムの導入で、データ入力時間が月間XX時間削減できた」といった効果測定が中心となります。これらは生産性向上に直結する重要な成果です。
一方、DXで重視される成果は、売上向上、顧客満足度の向上、新規顧客の獲得、新たな収益モデルの確立といった、社外向けの価値創出にあります。DXの成果は、顧客や市場にどれだけ新しい価値を提供できたかで測られます。もちろん、その過程で業務効率化が実現することもありますが、それはあくまで副次的な効果です。DXの本質は、IT化による社内効率化の先にある、企業の成長と競争力強化に他なりません。
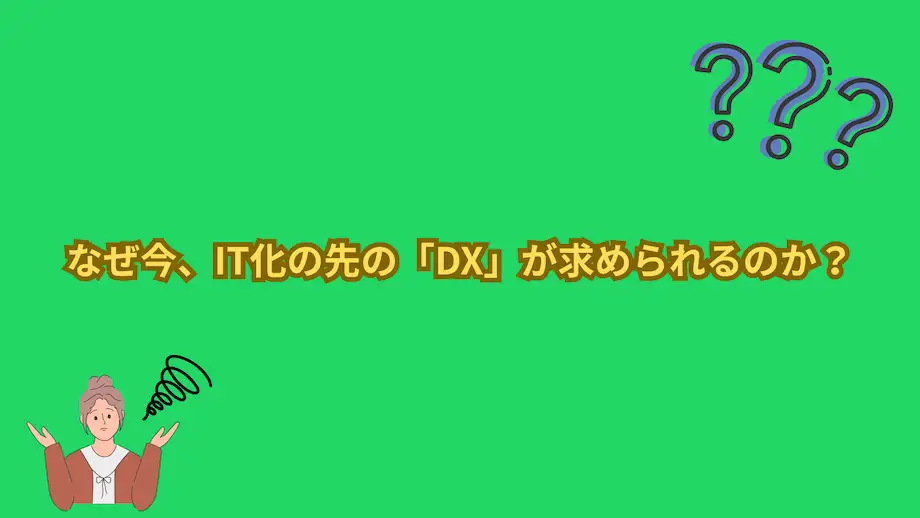
多くの企業がIT化による業務効率化を一通り進めてきたいま、なぜさらにその先にある「DX」への取り組みが不可欠とされているのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く環境の劇的な変化があります。放置すれば企業の存続すら危うくなる可能性がある、避けては通れない3つの大きな理由について解説します。
現代のビジネス環境は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取って「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。スマートフォンやSNSの普及により、顧客の価値観や購買行動は多様化し、変化のスピードもかつてないほど速くなっています。
このような時代において、従来のやり方を踏襲し、社内の業務効率化に終始するIT化だけでは、市場の変化に対応しきれません。顧客のインサイトをデータに基づいて迅速に把握し、新しい製品やサービス、顧客体験を継続的に提供していく必要があります。例えば、顧客データを活用してパーソナライズされた商品をおすすめするECサイトや、サブスクリプション型のサービスモデルへの転換などは、まさにDXによる変化対応の事例です。IT化による効率化を土台としつつも、ビジネスのあり方を柔軟に変革していくDXこそが、VUCA時代を生き抜くための鍵となります。
「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で指摘された問題です。多くの日本企業が抱える既存の基幹システムが、度重なるカスタマイズによって複雑化・ブラックボックス化し、その維持管理費が高騰する一方で、貴重なIT予算や人材が割かれてしまい、新たなデジタル投資の足かせになっているという課題を指します。
この老朽化したシステムを放置し続けた場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告されています。この問題を解決するには、単にシステムを新しくする(IT化)だけでなく、システムの刷新を機に、時代に合わなくなった業務プロセスや組織構造そのものを見直す「DX」の発想が不可欠です。レガシーシステムから脱却し、データを柔軟に活用できる新たなIT基盤を構築することは、DX推進の前提条件であり、多くの企業にとって喫緊の経営課題となっています。
日本は深刻な労働人口の減少という課題に直面しています。限られた人的リソースでこれまで以上の成果を出すためには、生産性の向上が不可欠です。個別の業務を効率化するIT化ももちろん重要ですが、それだけでは限界があります。
DXは、人にしかできない創造的な業務に集中できる環境を生み出します。例えば、RPA(Robotic Process Automation)やAIといった技術を活用して定型業務を自動化するだけでなく、蓄積されたデータを分析して需要予測の精度を高めたり、新たなマーケティング戦略を立案したりすることが可能です。これにより、従業員一人ひとりの生産性を飛躍的に高めることができます。労働人口の減少という社会的な課題に対応し、企業が持続的に成長していくためにも、IT化の先のDXへの取り組みが求められているのです。
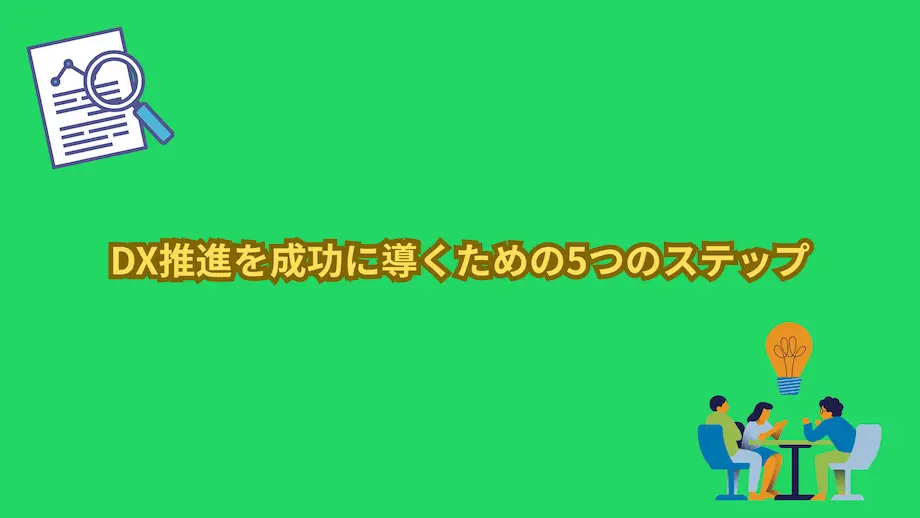
DXの重要性を理解しても、「何から手をつければ良いのか分からない」という担当者の方は少なくありません。DXは全社的な変革活動であり、明確なロードマップなしに進めることは困難です。ここでは、DXプロジェクトを成功に導くための、実践的な5つのステップをご紹介します。これらを順に実行することで、着実にDXを推進することが可能になります。
DXは、情報システム部門任せのIT化とは異なり、全社を巻き込んだ変革活動です。そのため、何よりもまず経営トップがDXの重要性を理解し、強力なリーダーシップを発揮することが不可欠です。経営層が「自社はDXによって、どのような姿を目指すのか」「顧客や社会にどのような新しい価値を提供するのか」という明確なビジョンを策定し、それを全従業員に対して繰り返し発信し続ける必要があります。このビジョンが、DX推進における判断の拠り所となり、従業員の向かうべき方向を一つにします。トップの明確なコミットメントがなければ、部門間の壁を越えた協力や、変革に伴う痛みを乗り越えることはできません。
経営トップのビジョンを実現するためには、それを実行する専門の推進体制が欠かせません。CEOやCDO(Chief Digital Officer)をトップとした全社横断的な推進組織を立ち上げ、各事業部門、情報システム部門、人事、経理などからメンバーを招集します。この組織が、DX戦略の具体化、各プロジェクトの進捗管理、部門間の調整役などを担います。 同時に、DXを推進するための人材、いわゆる「DX人材」の確保・育成も急務です。データサイエンティストやUI/UXデザイナーのような専門スキルを持つ人材だけでなく、ビジネスの課題を理解し、デジタル技術を活用して解決策を企画できる人材も重要です。社内での育成プログラムの実施や、外部からの専門人材の登用を計画的に進める必要があります。
次に、自社の現状を客観的に把握し、どこに課題があるのかを洗い出します。業務プロセス、組織体制、利用しているITシステム、顧客からの評価など、多角的な視点から分析を行います。「As-Is(現状)」を正しく理解することで、目指すべき「To-Be(あるべき姿)」とのギャップが明確になります。 このギャップを埋めるための具体的な道筋が「DX戦略」です。Step1で掲げたビジョンに基づき、「どの事業領域で」「どのような課題を」「どのデジタル技術を使って」「いつまでに解決するのか」といった具体的なアクションプランに落とし込みます。すべての課題に一度に取り組むことは不可能なため、重要度と緊急度の観点から優先順位を付けることが成功の鍵です。
壮大なDX戦略も、最初から大規模なプロジェクトとして開始すると、失敗のリスクが高まります。まずは、成果が出やすく、かつ影響範囲を特定しやすいテーマに絞って、小規模なプロジェクトから始める「スモールスタート」が有効です。 例えば、「特定製品の顧客満足度を向上させるために、チャットボットを導入して問い合わせ対応を自動化する」といった具体的なテーマです。小さなプロジェクトでPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを高速で回し、成功体験を積むことで、関係者のDXに対するモチベーションが向上します。また、その過程で得られた知見やノウハウは、より大きなプロジェクトを展開する際の貴重な財産となります。この「小さな成功」を積み重ね、社内に成功の機運を醸成することが重要です。
スモールスタートで得られた成果や学びを定期的に評価し、DX戦略全体にフィードバックしていくプロセスが不可欠です。導入したデジタルツールが計画通りに使われているか、目標としていたKPI(重要業績評価指標)は達成できているかを定量的に測定します。 もし、計画通りに進んでいない場合は、その原因を分析し、迅速に改善策を講じます。この「評価と改善」のサイクルを継続的に回すことで、DXの取り組みは徐々に洗練されていきます。そして、一部のプロジェクトで確立された成功モデルを、他の部門や事業へと横展開していくことで、DXの取り組みは全社的な大きな変革のうねりへと成長していきます。DXに終わりはなく、継続的な改善活動そのものであると認識することが大切です。
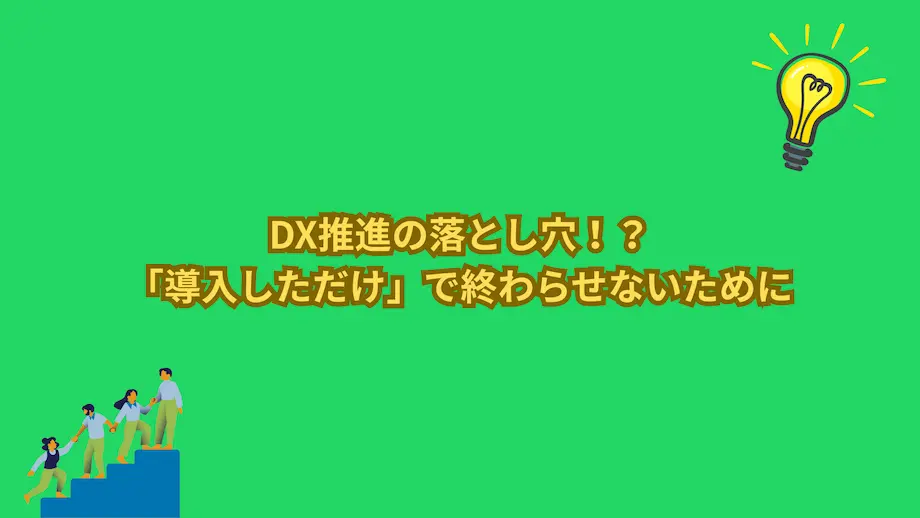
多額の投資を行い、鳴り物入りで最新のシステムを導入したにもかかわらず、現場ではほとんど使われず、結局Excelや紙の業務に戻ってしまった…。これは、多くの企業が経験するDX推進の典型的な失敗パターンです。なぜこのような「導入しただけ」の状態に陥ってしまうのでしょうか。それは、ツールの導入が目的化してしまい、現場の従業員が「どう使えば良いのか分からない」「使うメリットを感じない」という根本的な課題が放置されているからです。この課題を解決する一つの有効な選択肢をご紹介します。
こうした「導入したけど使われない」という課題を解決する新たなソリューションとして注目されているのが、DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)です。DAPとは、SFAやERPといった様々なウェブシステムの画面上に、操作方法をガイドするチュートリアルや、入力ルールを示すツールチップなどを後付けで表示させることができるツールです。 これまでのシステム導入では、分厚いマニュアルを作成したり、集合研修を実施したりするのが一般的でした。しかし、これらの方法は、いざシステムを使う場面ですぐに役立つとは限らず、担当者への問い合わせが殺到する原因にもなっていました。DAPを活用すれば、ユーザーがシステムを操作するまさにその画面上で、リアルタイムに疑問を解決できます。これにより、マニュアルを読む手間や研修の時間を削減し、従業員がスムーズに新しいシステムを使いこなせるよう支援します。
数あるDAPの中でも、当社の提供する「Fullstar」は、ノーコード(プログラミング不要)で直感的にガイドを作成できる手軽さと、利用状況のデータ分析機能を両立している点が特長です。 「Fullstar」を導入することで、DX推進・管理部門の方は、以下のようなメリットを得られます。
DXの成功は、導入したシステムが現場で「定着」し、日々活用されることで初めて実現します。システムの投資対効果を最大化し、「導入しただけ」の失敗を避けるために、DAPという選択肢をぜひご検討ください。

フォーム入力後、資料を閲覧できます。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行