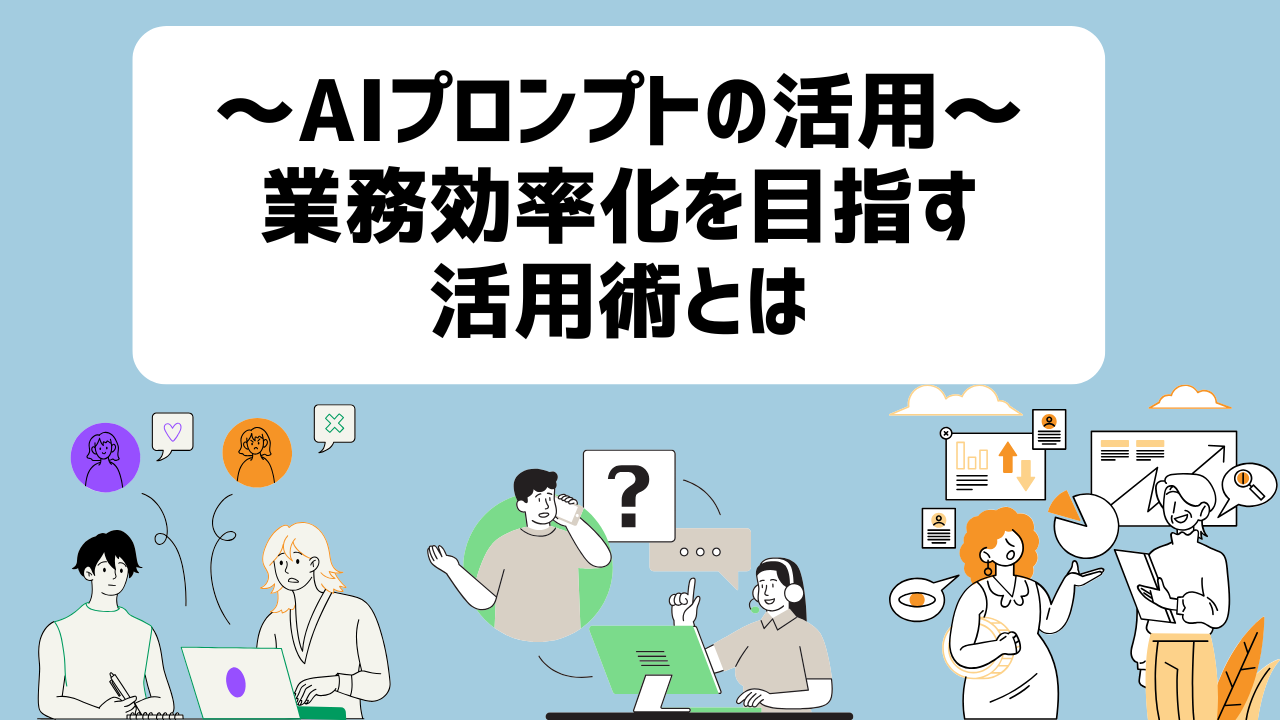

生成AIが急速に普及するなか、企業の中でもAI活用がますます注目されています。とはいえ、「AIを導入したはいいけれど、成果が出ない」「結局一部の社員しか使いこなせていない」といった声が聞かれるのも事実です。その背景にあるのが、“プロンプトの属人化”と、“社内全体での運用ルールの欠如”です。
本記事では、社内AI活用の成果を最大化するために不可欠な「プロンプトの標準化」について、情シス・総務・DX推進・経営企画部といった組織横断的な立場の方々に向けて、分かりやすく解説します。さらに、AI活用を組織に定着させる「DAP(Digital Adoption Platform)」の有効性と、ツール「Fullstar」を活用した実践的な取り組みもご紹介します。
目次
ここ数年、生成AIの進化は目を見張るものがあります。特にChatGPTをはじめとしたツールは、文章の生成だけでなく、要約・翻訳・アイデア出しなど、多くの業務シーンで活用されるようになりました。これにより、企業の中でもAIを業務に取り入れようとする動きが一気に加速しています。
一方で、「AIを導入したけれど、うまく活用しきれていない」「期待していたような業務効率化にはつながっていない」といった声も少なくありません。その理由として多く挙げられるのが、“プロンプト設計の難しさ”です。AIは、人間のように曖昧な指示を理解するわけではありません。求めている答えを的確に引き出すためには、「何を、どう伝えるか」が極めて重要になります。
たとえば、議事録の要約を依頼するときでも、「会議内容をまとめて」とだけ指示した場合と、「以下の会議内容を300文字以内で要点を絞って要約してください」と伝えた場合では、出力される内容に大きな差が出てきます。つまり、AIの力を引き出せるかどうかは、プロンプトの質次第なのです。
しかし現状では、このプロンプト作成が属人的になっていることが多く、使う人によって成果がバラバラになってしまいます。結果として、「AIを上手に使える一部の人だけが恩恵を受ける」という状態になり、社内全体に活用が広がりません。だからこそ、今あらためて注目されているのが、「プロンプトの標準化」なのです。AIを“誰でも使える道具”として定着させるために、避けて通れない取り組みといえるでしょう。
AIを活用する上で欠かせない「プロンプト」とは、AIに対する“指示文”のことを指します。たとえば、「この議事録を300文字で要約して」といった依頼文もプロンプトですし、「マーケティング部の新卒向け研修資料を構成案つきで作ってください」といった少し複雑な依頼もプロンプトにあたります。
生成AIは非常に賢い一方で、与えられたプロンプトによって成果物の精度が大きく変わるという特徴があります。そのため、「どんなプロンプトを、どのように作るか」が、AI活用の成否を左右する大きな要素となるのです。
ここで課題になるのが、プロンプトが属人化しやすいという点です。AIを上手く使いこなす人は、ごく一部に限られており、「あの人だけがAIで上手に資料を作れる」「この部門だけAIが活用できている」といった偏りが起きてしまいます。この属人化が進むと、社内でのAI活用が広がらず、全社的なDX推進の足かせになってしまうのです。
そこで今、注目されているのが「プロンプトの標準化」です。これは、業務ごとに有効だったプロンプトの“成功パターン”をテンプレート化し、誰でも同じ成果が得られるように整備することを意味します。以下にわかりやすく整理してみましょう。
| 項目 | 標準化されていない状態 | 標準化された状態 |
|---|---|---|
| プロンプトの設計 | 各自が自己流で作成 | テンプレートをベースに作成 |
| 成果の安定性 | ユーザーによってバラバラ | 誰でも一定水準の成果が出る |
| ナレッジ共有 | 担当者の頭の中に留まる | 全社で共有・改善が可能 |
| 教育コスト | 使い方を一から教える必要あり | テンプレートで即習得が可能 |
このように、プロンプトの標準化は属人性を排除し、再現性を高めるための重要な取り組みです。特に、複数部署にまたがる業務や、マニュアル化しづらいクリエイティブ業務での効果は絶大です。
たとえば、社内でこんなテンプレートを整備しておけばどうでしょう?
「この議事録を、5つのトピックに分けて要点を抽出し、箇条書きで300文字以内にまとめてください」
このように表現を工夫するだけで、AIのアウトプットは驚くほど安定し、業務の効率も飛躍的に向上します。そしてその成果を他の社員と共有し、「あのプロンプト、うまくいったよ!」といったナレッジが循環するようになれば、AI活用が“個人技”から“組織力”へと変化していきます。
プロンプトの標準化は単なる「マニュアル作り」ではなく、企業全体の生産性と競争力を左右する“仕組み作り”です。ここに早期から着手できるかどうかが、これからのAI活用における成否の分かれ目になると言っても過言ではありません。
AIを活用する中で多くの企業が直面しているのが、プロンプトの属人化による「組織内格差」です。AIに関心が高く、自ら試行錯誤している一部の社員は、非常に精度の高いプロンプトを作り、業務効率を飛躍的に高めています。しかしその一方で、「どうやって使えばいいのか分からない」「うまく使えなかったからやめてしまった」といった社員も多く、社内でのAI活用が均等に進んでいない現状があります。
この状態が長く続くと、次のようなリスクが顕在化してきます。
プロンプトの作り方が共有されていないため、特定の社員だけが高い成果を出すようになり、他のメンバーはその再現ができないという状況に陥ります。これにより、業務効率や成果のばらつきが生まれ、組織としての一体感や生産性が損なわれてしまいます。また、プロンプトの設計スキルが個人の経験と勘に依存しているため、その人が異動・退職した場合にはナレッジも一緒に失われてしまうというリスクもあります。これは、属人的なExcel管理や手順書に頼っていた時代とまったく同じ問題構造です。
AIツールは導入したものの、実際に使いこなしているのは一部の現場にとどまり、全社的な活用にはつながらない。このような“点の活用”では、企業全体の生産性向上にはつながりません。たとえば、ある部署では「プロンプトを活用して議事録作成が1/3の時間になった」という事例があっても、そのノウハウが他部署に伝わらなければ、会社全体としての価値は限定的です。ナレッジが共有されずにサイロ化してしまうことは、DX推進における大きなブレーキとなります。
属人化したプロンプト運用では、「AIを使っても、誰かのようにうまく使えない」「変な回答しか返ってこない」といったネガティブな体験をする社員も増えます。このような経験が蓄積すると、社内に“AI不信”が広がり、せっかく導入したAIツールが放置されてしまうケースも。実際、社内でこんな声が出てくることも少なくありません。「AIって、結局“得意な人”だけが使えるものでしょ?」「時間をかけても成果が出ないし、むしろ効率が悪くなる」「結局、手でやった方が早いよね」こうした声が現場で定着してしまうと、AIの活用そのものに対するモチベーションが下がり、“活用されないAI”として社内ツールのひとつに埋もれてしまうリスクが高まります。
プロンプトが属人化すると、せっかく蓄積できるはずのナレッジが、社員個人の中に留まり続けます。これでは、AIを使えば使うほど「組織として賢くなる」未来から遠ざかってしまいます。本来であれば、使えば使うほど洗練されていくはずのプロンプト。それが共有されず、活かされないまま埋もれていくと、企業としての競争力も伸び悩んでしまいます。
このように、プロンプトの属人化は単なる業務効率の問題ではなく、企業のAI活用基盤そのものを弱体化させる重大なリスクをはらんでいます。だからこそ、組織全体で「標準化されたプロンプト運用」を実現し、誰もが安心してAIを使える状態をつくることが、いま求められているのです。
プロンプトの標準化を社内で実現しようとしたとき、何から手をつければいいのか分からない、という声をよく耳にします。ただテンプレートを配布するだけでは浸透せず、「形だけの施策」で終わってしまう可能性もあるため、きちんと段階を踏んだ設計と運用が不可欠です。ここでは、実際の企業導入の現場でも効果が出ている「5つのステップ」をご紹介します。
最初の一歩は、「何のために」「どの業務で」プロンプトを標準化するのかを明確にすることです。全社で一斉に始めるよりも、まずは効果が出やすい領域からスモールスタートする方が成功確率は高まります。
といった、“定型化しやすく成果が見えやすい業務”から始めるのがおすすめです。
次に、現場で“うまくいっている”プロンプト事例を集めます。AIを使いこなしている社員にヒアリングしたり、チャットログを分析したりして、成果が出ているパターンや表現方法を可視化しましょう。この段階では、使われ方にクセやバラつきがあるのが普通です。だからこそ、「どの表現が、なぜ成果につながったか?」という視点で、プロンプトの質を見極めていくことが大切です。
収集・分析した情報をもとに、業務別のテンプレートを作成します。テンプレートは“かっちりしすぎず、現場でそのまま使える形”がベストです。
「以下の議事録を読み取り、3つの要点に分けて300文字以内で要約してください。トーンはビジネスライクにしてください」
また、テンプレートには簡単な使い方ガイドや文脈の説明を添えることで、AI初心者でも使いやすくなります。
テンプレートが完成したら、それを全社で活用できるようにナレッジベース化します。社内ポータルや業務ツール内にカテゴリ分けして配置すると、検索性・使いやすさが向上します。加えて、「このプロンプト、意外と便利だった!」といったフィードバックを投稿できるようにすることで、ナレッジが“生きた情報”として循環しやすくなります。
プロンプト標準化は、1度作って終わりではなく、継続的な改善サイクルの中で育てていくものです。AIのバージョンアップや業務の変化に応じて、プロンプトも進化させる必要があります。そこで有効なのが、定期的な見直しの「仕組み化」。たとえば、
などを導入することで、テンプレートの“鮮度”を保ちつつ、常に現場にフィットした形での運用が可能になります。
このように、プロンプトの標準化は「作って終わり」ではなく、「作り、広げ、育てる」プロセスが重要です。特に情シスや経営企画、DX推進のような横断組織がこの流れを主導することで、全社的な活用基盤として強く根付きます。次のステップでは、「なぜ推進役が情シス・総務・経営企画であるべきなのか?」という視点から、その役割と可能性を掘り下げていきましょう。
プロンプトの標準化は、単なる「AI活用のテクニック」の話ではありません。それは、全社でAIを“当たり前に使える状態”をつくるための土台であり、組織的な変革を伴うDX施策の一部です。そして、その推進役として最も適任なのが、情シス・総務・経営企画といった横断的な立場にある部門です。
情シスや経営企画は、特定の業務に閉じない「全体最適」を考える立場にあります。そのため、各部門の業務内容や課題を把握しており、「どのプロンプトが、どの部門に役立ちそうか?」というマッピングができるポジションです。また、プロンプトのテンプレート化や活用ルールの整備には、全社的な合意形成や運用設計が欠かせません。こうした調整能力や情報統制の面でも、情シスや総務、経営企画の存在は欠かせないのです。
生成AIの活用には、情報漏洩や著作権、倫理的な問題などのリスクも伴います。たとえば、「社外秘の内容をAIに入力してしまった」「意図せず差別的な表現が含まれていた」といった事故も、現実に発生しています。こうしたリスクを最小限に抑えるためには、プロンプト設計の段階からリスク管理の目線を入れる必要があります。社内のITリテラシーを底上げするという意味でも、情シスやリスクマネジメント部門の関与は極めて重要です。
単にテンプレートを配って「はい、活用してください」では、AIは現場に定着しません。必要なのは、現場で“自走”できる仕組みの設計です。
これらを整えるためには、運用ルールやIT基盤、情報フローの設計に長けた部門が主導することが不可欠です。まさに、情シス・総務・経営企画が持つ“設計力・構築力”が活きる領域なのです。
最後に強調したいのは、プロンプト標準化は単なる効率化の手段ではなく、“企業のAI文化”を育てるプロジェクトであるということです。そして、それを形にできるのは、全社の未来を設計する責任と視野を持った、あなたたちのような部門の役割なのです。
次章では、こうしたAI活用と親和性の高い「DAP(Digital Adoption Platform)」という考え方について、さらに掘り下げてご紹介します。AIと社内業務を“つなぎ”、現場の活用を定着させる新しい視点を、ぜひチェックしてみてください。
プロンプトの標準化によって、誰でも一定の品質でAIを活用できる「仕組み」が整ったとしても、それだけでは現場での“定着”までは保証されません。むしろ、整えたテンプレートやナレッジが「誰にも使われていない」「結局いつものやり方に戻ってしまった」というケースは少なくありません。そこで今、注目されているのがDAP(Digital Adoption Platform)=デジタル定着支援ツールです。
DAPとは、簡単に言えば社内ツールやAIなどのデジタル技術を、社員が“迷わず・自然に・継続的に”使いこなせるようにサポートする仕組みのことです。
「ツールは導入したけど使われない…」
「使い方が分からず現場に定着しない…」
こうした“ラストワンマイル”の課題を解決するのがDAPの役割です。
| 領域 | 具体的な支援内容 |
|---|---|
| 利用促進 | ツールやAIを操作する際に、画面上でリアルタイムに使い方を案内 |
| 学習支援 | ポップアップ・チュートリアル・動画などで操作方法を説明 |
| 利用状況の可視化 | どの機能が、誰に、どれだけ使われているかを可視化 |
| 継続利用の促進 | 行動データに基づき、必要なタイミングでリマインドや案内を表示 |
たとえば、「このプロンプトテンプレートはこの画面でこう使います」とAIの使い方を業務フローの中でリアルタイムにガイドできるので、マニュアルを読む手間なく誰でもすぐに使いこなせるようになります。
プロンプトの標準化が「何をどう使えば良いか」を整える仕組みだとすれば、DAPはそれを「現場で実行に移す」ための仕組みです。
このように、どちらか一方だけでは成果に結びつきません。特に、ツール導入に不慣れな現場や、部署間でリテラシー格差のある企業ほど、DAPによる“デジタル定着支援”が不可欠です。
プロンプトやAI活用の知見を整備しても、それが社員に伝わらず、現場で“止まってしまう”のは非常にもったいないことです。DAPを導入することで、以下のような課題が解決されます👇
この“現場のリアルな壁”に対し、DAPは自然なタイミング・自然な導線で支援を差し込むことができるため、AI活用の定着率が大きく向上します。
AIやSaaSなどのデジタルツールに対し、近年の経営層が求めているのは「導入の有無」ではなく、“導入後、ちゃんと使われているか?”という定着状況です。この視点からも、プロンプト標準化に加えて「どのように現場で使われ続けるか」を設計するDAPは、まさにDX施策の“最後のピース”といえます。
プロンプトの標準化に取り組む企業が増える中で、「社内にどう定着させるか」という次なる課題に直面する企業も多くなっています。そんな中、今注目を集めているのが、プロンプト活用とデジタル定着支援の両立を実現できるツール、それが「Fullstar」です。
Fullstarは、社内に導入されているあらゆるデジタルツールの使い方を、リアルタイムでガイドするDAPです。画面上にポップアップやチュートリアルを表示し、社員が迷わず操作できるようサポートします。生成AIの活用においても、以下のような使い方が可能です。
つまり、Fullstarはプロンプトの“活用促進”と“定着支援”をセットで実現できるDAPなのです。
プロンプトをいくら整備しても、それが「使われなければ意味がない」──この課題を解決するのがFullstarの強みです。
| プロンプト標準化 | Fullstarとの連携効果 |
|---|---|
| テンプレートの整備 | 画面上でリアルタイムにテンプレート提示・説明が可能 |
| 利用ガイドの配布 | 実際の操作画面に沿ってステップバイステップで案内 |
| 利用状況の把握 | 誰が・どこで・どのテンプレートを使ったかを可視化 |
| 社内展開 | 自然な導線で活用を促進、定着率が大幅向上 |
特に、AI活用が“属人的になりやすい”という課題に対して、Fullstarは「誰でも迷わず使える環境」を実現する頼れるパートナーとなります。
「Fullstarを実際に見てみたい!」という方には、無料デモや資料請求のご案内も行っています。自社の課題や運用状況に合わせて、最適な導入方法をご提案することも可能です。
👉 詳しくは、こちら からご案内を行っております✨

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行