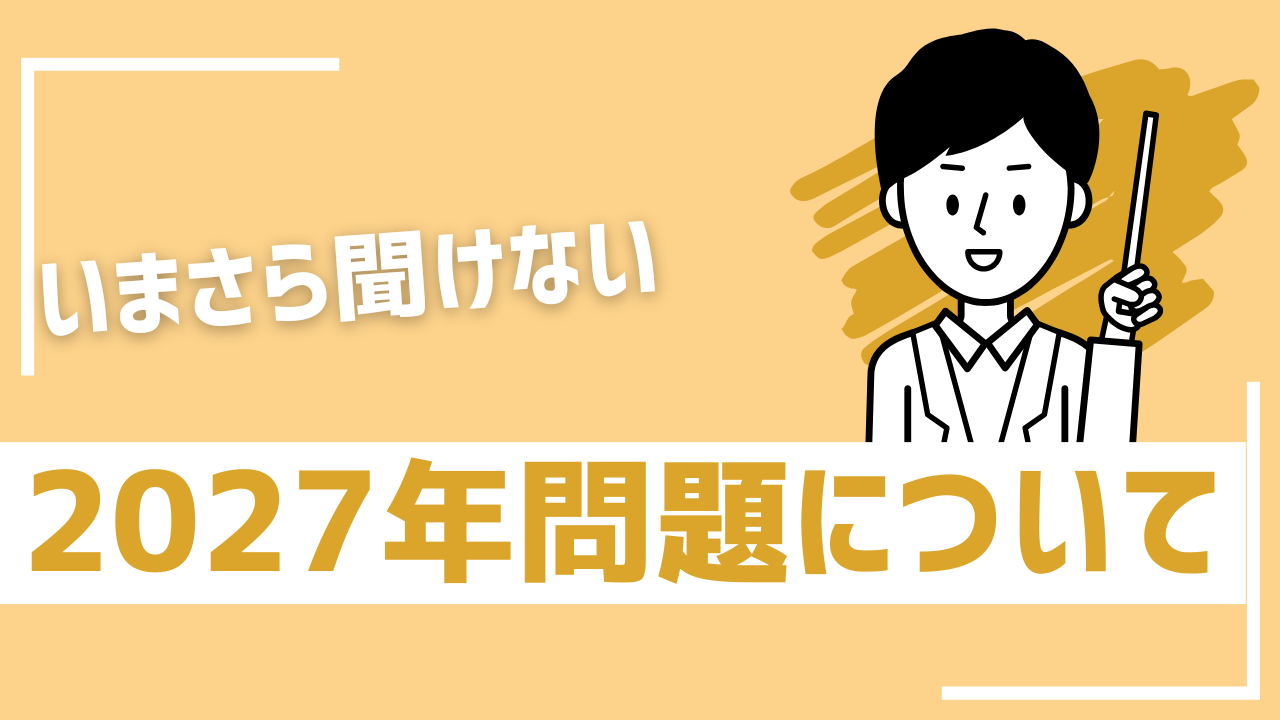

本記事では、SAP ERP 6.0のサポート終了により生じる「2027年問題」について解説します。影響の大きさ、企業が取り得る選択肢、移行プロジェクトにおけるリスク、そして成功に向けた準備方法までを網羅的に紹介。全社的な視点での対応が求められるこの課題に対し、今からできる実践的なアプローチを解説します。
目次
2027年問題とは、SAP社のERP製品「SAP ERP 6.0(SAP ECC)」の標準サポートが2027年末に終了することを指します。世界中で多数の企業が導入してきたこの基幹システムは、今後の利用継続にあたって大きな転換点を迎えています。 本来、SAP ERP 6.0のサポート終了は2025年末に予定されていましたが、顧客企業の移行準備が進んでいないことから、2年間の延長が決定しました。しかし、いずれにせよ、2027年末という「終わりの時」は確実に訪れます。 この問題は単なるITのアップデートにとどまらず、企業の業務基盤・経営戦略全体を見直す契機ともなります。ERPは単なるシステムではなく、企業の業務フロー、データ、意思決定を支える中枢神経系ともいえる存在です。つまり、サポート終了という出来事は、企業の体幹に大きな影響を与えることを意味します。 そのため、情報システム部門を中心に、経営企画、業務部門、さらにはDX推進チームまで巻き込んだ全社的な対応が求められるテーマなのです。
SAP ERP 6.0の標準サポート終了がもたらす影響は、単なるシステム更新の枠を超えた経営課題です。サポート終了後は、以下のような深刻なリスクが現実化する可能性があります。 まず最も顕著なのが、セキュリティリスクの増大です。標準サポートが終了すると、セキュリティパッチの提供が受けられなくなり、新たに発見された脆弱性に対応できません。サイバー攻撃が巧妙化する現在において、パッチ未適用の基幹システムは格好の標的となりえます。 次に、障害発生時の対応困難という問題もあります。バグやシステムトラブルが起きた際、SAPからの技術的支援が受けられず、障害復旧に時間とコストがかかります。これは情報システム部門や社内ヘルプデスクにとって大きな負担となるだけでなく、業務の遅延や停止に直結します。 また、業務効率の停滞も見過ごせない影響です。SAP ERP 6.0は古いアーキテクチャで構築されており、最新の業務要件や法令対応に適応する柔軟性が乏しいため、DX推進の足かせになりかねません。 さらに、人材確保の問題も深刻です。SAP ERP 6.0を熟知している技術者は年々減少傾向にあり、保守・運用を継続するにも専門人材の確保が困難になるでしょう。これは属人化を助長し、将来的なシステム運用リスクの温床となります。 このように、2027年問題は“未来の問題”ではなく、今から着手すべき“現在進行形の課題”です。特にDXを推進する立場の部門にとっては、システム刷新の是非を超えた、戦略的な判断が求められます。
2027年のサポート終了を見据え、企業が検討すべき主な対応策は大きく3つあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の業務要件、IT資産、リソース状況に応じた適切な判断が求められます。 1. SAP S/4HANAへの移行 SAPが次世代ERPとして提供している「SAP S/4HANA」への移行は、もっとも推奨されている選択肢です。HANAデータベースによるインメモリ処理で、リアルタイム分析や高速なトランザクション処理を実現。クラウド対応や最新技術との連携性も高く、DXの基盤として有力です。 移行方式は「Brown Field(既存環境の活用)」と「Green Field(新規構築)」に大別され、どちらを選ぶかによってプロジェクトの内容も大きく異なります。前者は移行コストを抑えやすく、後者は業務改革を含む抜本的な再設計に向いています。 2. 他社ERPへの移行 自社の業務にフィットする他社製ERPへのリプレイスを選択する企業もあります。オラクル、マイクロソフト、ワークデイなどの製品が代表例で、それぞれに特長があります。ただし、完全なゼロベース設計となるため、導入コストや業務移行負担は大きく、検討には慎重さが求められます。 3. 現行システムの延命 SAPは追加コストを支払うことで、2027年末以降も2030年末までの延長サポートを提供しています。これは移行準備のための猶予期間として活用可能ですが、根本的な解決にはなりません。延命策に頼りすぎると、いずれ後戻りできない技術的負債として企業にのしかかります。 いずれの選択肢にも一長一短がありますが、共通して言えるのは「早期の意思決定がすべての成功の鍵になる」という点です。放置は最大のリスクであり、今すぐにでも社内で議論を始める必要があります。
ERP移行プロジェクトは、企業の中でも特に困難かつ複雑な取り組みです。単なるシステム更新ではなく、業務フロー、組織、文化、人材すべてに影響を及ぼす大規模変革であることを理解する必要があります。 まず立ちはだかるのがコストの壁です。SAP S/4HANAへの移行は、システム構築・データ移行・教育・保守を含めて数千万円〜数億円規模になるケースも珍しくありません。費用対効果の見積もりや、経営層への説明責任をどう果たすかが重要です。 また、人材不足とナレッジの断絶も深刻です。SAP ERP 6.0に詳しい人材が定年退職や配置転換で現場を離れている中、新たな技術に精通したメンバーを確保・育成する必要があります。 さらに、長年にわたって複雑化・属人化してきたレガシー業務フローも移行の障壁になります。カスタマイズされた業務プロセスやスプレッドシート管理が氾濫している現場では、標準化への抵抗も根強く、業務部門との調整がプロジェクト成功のカギを握ります。 データ移行の難しさも見過ごせません。マスターデータの不整合、トランザクション履歴の断片化、設計思想の異なる新旧システム間での整合性確保など、多くの技術的課題が待ち構えています。 これらのリスクを過小評価せず、初期段階から十分な調査・分析・体制整備を行うことが、後々のコストと混乱を最小化する唯一の方法です。
成功するERP移行プロジェクトの多くは、移行そのものよりも「事前準備」に多くのリソースを割いています。準備こそが成否を分ける鍵であり、軽視してはなりません。 まず取り組むべきは、現行システムと業務プロセスの可視化です。業務フロー、システム構成、データ構造、インターフェースの棚卸しを行い、どこに課題があり、何を変えるべきかを明確にします。ここでの精度が高ければ高いほど、後続の設計フェーズがスムーズに進みます。 次に必要なのが、業務の標準化とルール整備です。長年の運用で複雑化したカスタマイズや部門ごとの独自運用を見直し、可能な限り標準機能で運用できるよう再構成します。これにより、保守性・拡張性が向上し、将来的なコスト削減にもつながります。 また、ステークホルダーの巻き込みと合意形成も忘れてはなりません。情報システム部門だけで移行を進めようとせず、業務部門や経営層を巻き込み、全社横断的なプロジェクト体制を築くことが重要です。 さらに、ITパートナーの選定も移行成功を左右します。単なるベンダーではなく、業務理解・導入実績・トラブル対応力を備えた「伴走者」を選ぶことが不可欠です。複数社によるコンペや提案比較を通じて、自社に最適なパートナーを見極めましょう。 最後に、スケジュールとロードマップの策定です。すべてを一度に移行する必要はありません。段階的移行(フェーズドアプローチ)や、業務ごとの優先度に応じたスケジューリングを行い、現場負荷とリスクを分散することが望まれます。 移行準備は時間がかかるプロセスです。しかし、確実に成果を出すためには「急がば回れ」の姿勢で、地に足のついた準備が求められます。
2027年問題は、単なるソフトウェアのサポート終了という技術的な話にとどまりません。それは、企業の業務プロセス、組織構造、そして将来の成長戦略にまで関わる、全社的な課題です。 情報システム部門、社内ヘルプデスク部門、そしてDX推進部門にとって、今この瞬間からどのように準備を始めるかが、3年後のリスクを最小限に抑え、変革を好機へと変えるカギとなります。 移行の決断には、確かに大きなコストと手間が伴います。しかし、旧システムを放置し続けることの「見えないコスト」や「将来の機会損失」の方が、はるかに大きいかもしれません。 2027年は避けようのないタイムリミットです。だからこそ、今、現場の声を拾い上げ、経営層を巻き込み、社内全体での合意形成と準備を始める必要があります。 “2027年問題”を、“2027年チャンス”へ──。未来を見据えた基幹システム刷新こそが、これからの企業の持続的成長を支える柱となるでしょう。

無料プランで始める
書類不要!最低利用期間なし!
ずっと無料で使えるアカウントを発行